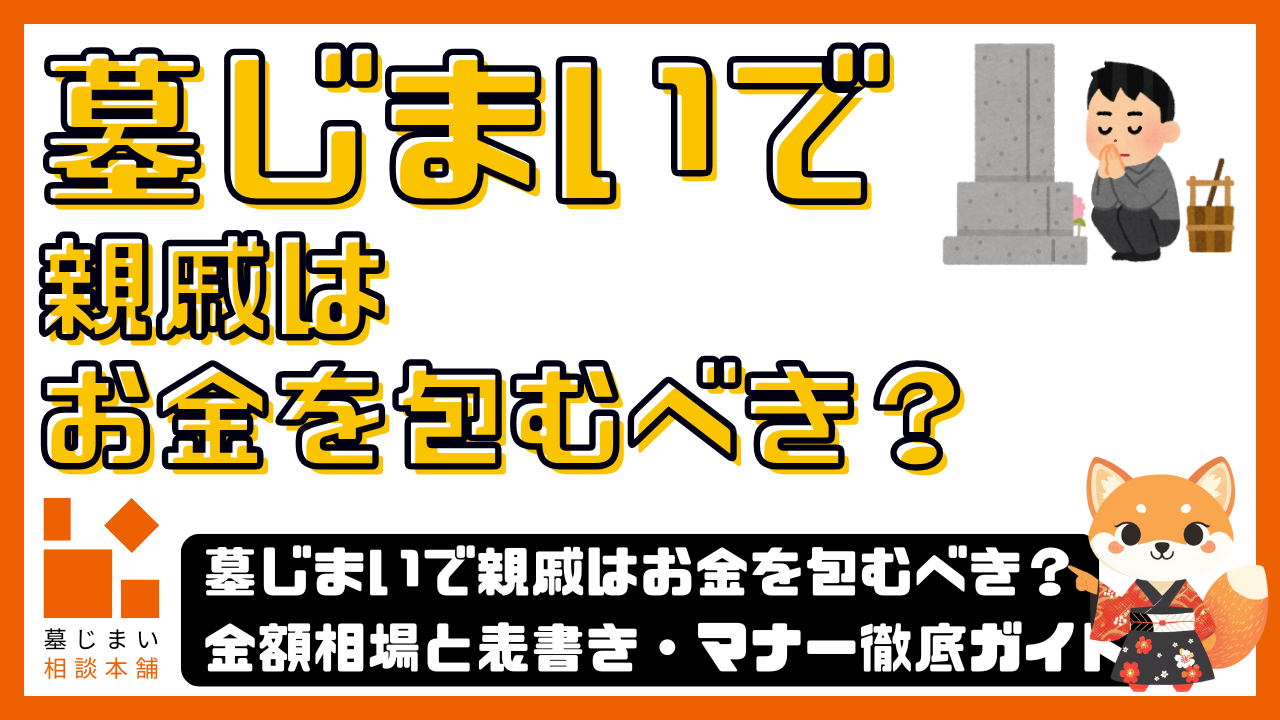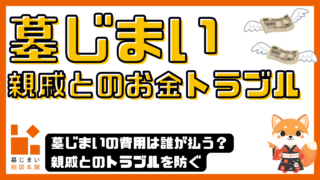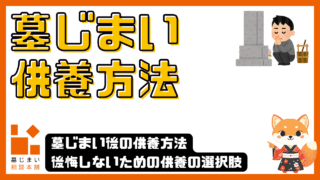本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいで親戚がお金を包むべき場面とは?
墓じまいの場面では、呼ばれた親戚が金銭を包む機会があります。とはいえ、すべての場面でお金を包む必要があるわけではなく、参加する儀式の内容によって対応が異なります。ここでは、代表的な4つの場面と、それぞれにおける包む金額や表書きの例を紹介します。
閉眼供養(魂抜き)に参列する場合
閉眼供養は、墓石に宿っているとされる故人の魂を抜くための大切な儀式です。この儀式に招かれた親戚は、不祝儀袋に「御供」と書いて1万〜3万円程度を包むのが一般的です。水引は黒白または双銀、関西では黄白が使われることもあります。
撤去工事に立ち会う場合
墓石の撤去工事そのものに親戚が呼ばれることは少ないですが、閉眼供養と併せて行われるケースが多く見られます。この場合、閉眼供養と工事の両方を「御供」でまとめて渡せば問題ありません。撤去工事だけに参加する場合でも、5千円〜1万円程度を目安に「御供」として包むのが丁寧です。
開眼法要(建碑式)に招かれた場合
墓じまいに伴って新しい供養先(納骨堂や永代供養墓)にお墓を移した場合には、開眼法要が行われることがあります。これは新しい墓石に魂を入れる儀式で、お祝い事にあたります。親戚として参加する場合は、祝儀袋に「建碑祝」や「建碑設立御祝」と書き、5千円〜3万円程度を包むのが基本です。水引は紅白、袋は金銀も可とされ、新札を用意します。
納骨式に同席する場合
納骨式は、閉眼供養とは別の日に行われることもあります。この場合、不祝儀袋に「御仏前」と記載し、5千円〜1万円が相場となります。納骨後に会食がある場合には、さらに1万円程度を加えることが一般的です。

親戚として包むお金は、参列する行事によって異なるため、事前に祭祀承継者や他の親戚と確認を取ることが大切です。また、同日に複数の儀式がある場合には、弔事を優先して「御供」や「御仏前」とまとめて包むことが基本です。間違えて「御香典」など葬儀用の表書きを使わないよう注意しましょう。
包む金額の相場一覧|立場や地域でどう違う?
墓じまいに参列する際に包む金額は、故人との関係性、行事の内容、地域の慣習などによって大きく異なります。ここでは一般的な金額の目安と、よくある地域差、組み合わせパターンをご紹介します。
親戚の立場別・包む金額の目安
| 関係性 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 両親・兄弟 | 10,000〜30,000円 | 最も近しい関係。多めに包むのが一般的 |
| 姉妹・義兄弟 | 5,000〜20,000円 | 家族に準じる扱い |
| いとこ | 3,000〜10,000円 | 地域によって差が出やすい |
| 甥・姪 | 3,000〜5,000円 | 学生や若年層の場合は少額でも問題なし |
同じ立場でも、地域や家の慣習によって上下することがあります。迷った場合は、他の親戚に相談して金額を揃えるのが無難です。
行事の内容による違い
| 行事 | 表書き | 相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 閉眼供養 | 御供 | 10,000〜30,000円 | 法要メイン。僧侶の読経あり |
| 撤去工事のみ | 御供 | 5,000〜10,000円 | 工事業者への心付けとしての意味合いも含む |
| 納骨式 | 御仏前 | 5,000〜10,000円 | 会食の有無によって追加包みが必要なこともある |
| 開眼法要(建碑式) | 建碑祝 | 5,000〜30,000円 | 慶事扱い。紅白の水引を使用 |
なお、これらの行事が同時に行われる場合は、原則として「弔事が優先」とされ、表書きや金額も弔事の形式に揃えます。
地域差による金額の変動
地方によっては、「御供は最低1万円」とされる地域もあれば、「5000円程度でも十分」というエリアもあります。特に関西と関東では、水引の色や新札・旧札の扱いにも違いがあるため、地域に根差したマナーを事前に確認しておくと安心です。
行事の組み合わせと表書きのパターン
複数の行事が同日に行われる場合、それに応じて表書きと金額を調整する必要があります。
| 行事の組み合わせ | 推奨される表書き | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 閉眼供養+撤去工事 | 御供 | 10,000〜20,000円 |
| 閉眼供養+納骨式 | 御仏前 | 15,000〜30,000円 |
| 閉眼供養+撤去+納骨+開眼 | 御仏前 | 20,000〜30,000円以上 |

金額に迷う場合は、祭祀承継者または参列予定の親戚と事前に相談しておくのがベストです。立場や状況に応じて柔軟に判断し、無理のない範囲で包むことが、故人への敬意とご遺族への配慮につながります。
表書きマナーと包み方|御供・御仏前・建碑祝の正しい使い分け
墓じまいに参列する際には、法要や儀式の内容によって使う表書きが異なります。不適切な表書きを選ぶと失礼になることもあるため、マナーに則った正しい使い分けが重要です。ここでは、表書きの種類・使う場面・包み方のマナーについて詳しく解説します。
使用する表書きと使い分けの基本
| 参列する儀式 | 表書き | 水引の色 | 使用する袋 | 金額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 閉眼供養 | 御供 | 黒白(または双銀) | 不祝儀袋 | 1万〜3万円程度 |
| 撤去工事のみ | 御供 | 黒白(または双銀) | 不祝儀袋 | 5千〜1万円程度 |
| 納骨式(永代供養含む) | 御仏前 | 黒白(または双銀) | 不祝儀袋 | 5千〜1万円程度 |
| 建碑式(開眼法要) | 建碑祝 | 紅白 | 祝儀袋 | 5千〜3万円程度 |
閉眼供養や納骨式は弔事にあたるため、黒白の水引を使った不祝儀袋を用意します。一方、新たな墓石の開眼法要(建碑式)は慶事に分類されるため、紅白の水引の祝儀袋に包み、「建碑祝」と記載します。
なお、同日に複数の儀式が行われる場合は弔事を優先し、「御供」や「御仏前」の表書きを使うのが一般的です。
表書きで避けるべきNGワード
「御香典」「御香料」「御弔料」などの表書きは、葬儀専用であり、墓じまいでは不適切です。あくまで「お墓を閉じる」「供養を終える」儀式であるため、こうした言葉を使うと誤解や失礼になる可能性があります。
また、「祝」とつく表書き(例:「御祝」)も、開眼法要以外では避けるべき表現です。
お札の選び方と記入マナー
不祝儀の場合は使用済みのお札(旧札)を用いるのがマナーです。折り目が入っているお札の方が、「不幸を予期していなかった」ことを示すとされているためです。ただし、極端に汚れた紙幣やボロボロのものは避け、できるだけきれいな旧札を用意しましょう。
一方で、祝儀の場合は新札を使うのが基本です。特に建碑祝などのお祝いごとでは、新札を使用し、気持ちを込めて包むことが求められます。
表書きや氏名を書く際は、毛筆または筆ペンを使い、濃い黒色で丁寧に書きましょう。ボールペンや薄墨は不適切です。
包み方の基本マナー
中袋がある場合は、表に金額(「金壱萬円」など)を縦書きで、裏に住所と氏名を記入します。中袋がない場合は、外包みの裏側に同様の情報を書き添えます。記入の際は略字を避け、正式な漢数字(壱・弐・参など)を使うのが正式です。
袋に入れたお金は、表書きが見えるように包み、上下の折り方も慶弔で変えるのがマナーです。弔事では下を先に折り、慶事では上を先に折ります。
ケース別の対応ポイント
- 複数の儀式に参加する場合:原則として弔事を優先し、「御供」または「御仏前」で統一します。
- 会食がある場合:会食代込みで1万円程度を加算して包むと丁寧です。
- 表書きに迷ったら:同席する親戚や詳しい高齢の親族に確認するのが安心です。
地域の風習や宗派によって異なる場合もあるため、不安なときは事前に祭祀承継者や寺院に確認しておくとトラブルを防げます。

正しい表書きと包み方を知っていれば、親戚としての礼を尽くすことができ、祭祀承継者にも安心して受け取ってもらえます。場面に応じた丁寧な対応を心がけましょう。
服装と渡し方のマナー|失礼にならない立ち居振る舞い
墓じまいに親戚として参列する際は、場面に応じた服装と現金の渡し方に注意が必要です。立場や地域性、儀式の性質をふまえたマナーを守ることで、失礼のない印象を与えられます。
服装の基本マナーと選び方
墓じまいに関係する法要や儀式は、「弔事」と「慶事」が混在する場合があります。参列する内容ごとに、適切な服装が異なります。
| 行事名 | 種別 | 推奨される服装 |
|---|---|---|
| 閉眼供養 | 弔事 | 準喪服(ブラックスーツなど) |
| 撤去工事 | 弔事 | 略式礼装(地味な平服) |
| 納骨式 | 弔事 | 準喪服 |
| 開眼供養 | 慶事 | 準礼服(グレーやネイビー系) |
略式礼装とは、カジュアルすぎない地味な服装を指し、男性はダークスーツ、女性は濃色系のワンピースやセットアップが基本です。「平服で」と言われた場合も、ジーンズや柄物は避けましょう。
慶弔が重なる場合(例:閉眼供養と開眼法要を同日に行うなど)は、弔事の服装を優先するのが通例です。
金封の扱い方と渡すタイミング
お金は不祝儀袋や祝儀袋に入れて持参します。袋の種類・表書きは事前に確認し、間違いのないようにします。袋の扱いには以下の注意点があります。
- 渡す前に袱紗(ふくさ)に包む
- 封筒の表面が人目に触れないように持つ
- 名前は薄墨ではなく、濃い黒インクで書く
- 新札は避ける(ただし「建碑祝」など慶事の場合は新札)
渡すタイミングは、祭祀承継者やその家族にあいさつをする場面が自然です。読経や儀式が始まる前、控室や受付で渡すのが一般的で、「本日はお声がけいただきありがとうございます」などの言葉を添えると丁寧です。
気をつけたい立ち居振る舞い
儀式中やその前後の立ち居振る舞いにも配慮が必要です。
- 到着時は静かに挨拶し、私語を控える
- スマートフォンの電源は必ず切る
- 式後の会食では、主催者側へのねぎらいの言葉を忘れずに
親戚間での会話も、費用や遺産などのデリケートな話題は避け、場にふさわしい節度を保つことが大切です。

墓じまいは形式にとらわれすぎる必要はありませんが、参列者としてのマナーを押さえておくことで、故人と遺族への敬意をきちんと伝えることができます。
墓じまい費用を親戚が負担するケースとは?
墓じまいの費用は一般的に祭祀承継者が負担しますが、状況によっては親戚が一部または全額を支援するケースもあります。ここでは、親戚が費用を負担する代表的なパターンや、トラブルを避けるための工夫について解説します。
よくある支援パターン
費用を親戚が負担する背景には、墓じまいにかかる金額の大きさがあります。墓石の撤去、供養、改葬などを含めると、30万円以上かかることも珍しくありません。以下のようなケースでは、親戚が積極的に協力することがあります。
- 兄弟で費用を折半するケース
特に実家の墓じまいの場合、兄弟で費用を分け合うことが多く見られます。長男や次男といった「実子」間での協力が基本ですが、話し合い次第で平等に負担する合意が成立することもあります。 - 親族が高齢の祭祀承継者を支援するケース
高齢の承継者が資金面で困っている場合、甥・姪や従兄弟などの若い世代が援助する例もあります。特に、財産分与を受けていない親族が「せめて費用だけでも」と支援する形です。 - 親族全体での“志”として出し合うケース
「一族のお墓」として代々守ってきた背景がある場合、費用を一部ずつ出し合って完了させることがあります。この場合は金額にこだわらず、できる範囲で協力するという柔軟な姿勢が取られます。
援助をお願いする際の伝え方と注意点
お金の話はデリケートです。支援をお願いする際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 感謝の気持ちを明確に伝えること
「負担を強いる」印象を与えないように、あくまで「助けていただけたらありがたい」という姿勢が大切です。 - 具体的な金額と用途を伝えること
漠然と「お金がかかるから」と頼むのではなく、「撤去工事に◯万円、永代供養に◯万円」など、内訳を提示することで誠実さが伝わります。 - 相手の負担にならない範囲で相談すること
無理に求めるのではなく、相手の事情に配慮したうえで「もし可能であれば」と話すのがポイントです。
揉めないための工夫|書面化と共有
費用の分担でトラブルを避けるためには、事前の合意と「見える化」が重要です。
- 費用の内訳と分担を一覧にして書面化する
後々「言った・言わない」の争いを避けるためにも、書面やメモの形で残し、全員で共有しておくことが大切です。 - コピーを配布し、認識のズレを防ぐ
関係者全員が同じ情報を持っていることで、信頼関係を保ちつつスムーズな墓じまいが実現します。 - 支援を受けた際のお礼や報告も丁寧に
完了後には簡単な報告書や挨拶状を送り、支援への感謝を伝えると関係がより良好になります。

親戚が墓じまい費用を負担するケースでは、「相手の立場を尊重しつつ、きちんと筋を通すこと」が円満に進めるコツです。事前に誤解を防ぐ工夫をしておくことで、後悔のない墓じまいに近づけます。
御供や御仏前へのお返しは必要?
墓じまいに参列した親戚から「御供」や「御仏前」として金銭を受け取った場合、基本的には香典返しと同様にお返しをするのがマナーとされています。形式的ではありますが、いただいたご厚意に対して感謝の気持ちを伝える意味でも、お返しは重要です。
お返しの相場と時期
お返しの金額は「いただいた金額の半額程度」が目安です。たとえば1万円を受け取った場合は、5千円相当の品を用意するのが一般的です。ただし、3千円以下の少額であれば、お返しを省略するケースもあります。
渡すタイミングは法要から1週間〜1か月以内が適切とされており、郵送でも手渡しでも構いません。地域や家庭の慣習によっては「当日返し(即日返し)」として、受付の場で品物を渡すこともあります。
お返しに適した品物
品物としては、消えもの(消耗品)が好まれる傾向にあります。具体的には以下のようなものが一般的です。
- お茶・海苔・菓子詰め合わせ
- 洗剤やタオルセット
- カタログギフト(3千〜5千円程度)
無難なものを選べば、年齢や性別を問わず喜ばれます。
のし紙と表書きの書き方
水引は黒白または双銀の結び切りを使用し、のし紙の表書きは地域により次のいずれかを使います。
- 「志」:全国的に多く使われる
- 「粗供養」:関西地方に多い
表書きの下段には祭祀承継者の姓または「〇〇家」と記します。なお、「香典返し」や「御礼」といった表記は使用しないよう注意しましょう。
お返しが不要なケースもある
親戚との関係性や地域の風習によっては、「気を遣わないで」と事前に伝えられることもあります。そのような場合でも、お礼の言葉や挨拶状を添えることで丁寧な対応になります。
また、費用を折半している兄弟間などでは、形式的なお返しは省略し、代わりに簡単なお礼の品や手紙で感謝を伝えるケースも見られます。

御供や御仏前は故人を偲ぶ気持ちの表れです。お返しを通じてその心に応えることは、遺族としての大切な務めでもあります。形式にとらわれすぎず、気持ちのこもった対応を心がけましょう。
墓じまい当日の流れと、親戚が注意すべきポイント
墓じまい当日は、閉眼供養や撤去工事、納骨式など複数の工程が行われることがあります。親戚として参列する際には、それぞれの場面で求められるマナーや振る舞いに配慮することが大切です。ここでは、一般的な当日の流れと、親戚が注意すべきポイントを解説します。
一般的な墓じまい当日の流れ
- 集合・挨拶
予定時間の10〜15分前には現地に到着し、主催者や僧侶へのあいさつを済ませます。服装は閉眼供養がある場合、略喪服や地味な平服が基本です。「平服で」と案内された場合も、ジーンズやカジュアルな服装は避けましょう。 - 閉眼供養(魂抜き)
僧侶が読経を行い、墓石から魂を抜く儀式です。親戚は静かに見守り、「御供」と表書きした不祝儀袋を用意しておくと安心です。お布施は施主が支払うため、親戚が渡す必要はありません。 - 墓石の撤去工事
閉眼供養のあと、業者による墓石撤去が行われます。この工程には立ち会わずに解散するケースもありますが、見届けたい場合は、業者の作業の妨げにならないよう距離を取って静かに見守るのがマナーです。 - 納骨式(新しい供養先へ移す場合)
永代供養墓や納骨堂への移転がある場合、当日中に納骨式が行われることがあります。この際の表書きは「御仏前」が一般的です。僧侶の読経がある場合は、再び焼香や合掌の機会があります。 - 会食・解散
式のあと、施主側で会食を用意している場合があります。辞退する場合は早めに伝え、参加する場合は節度ある振る舞いを心がけましょう。
親戚として注意すべき3つのポイント
1. 儀式の内容を事前に確認しておく
閉眼供養・納骨式・工事のどれに立ち会うのかで、持参する金封の表書きや金額が変わります。「御供」「御仏前」のどちらを使うべきか迷ったら、祭祀承継者や年長の親族に相談して確認しておきましょう。
2. お金を渡すタイミングと言葉遣いに配慮する
金封は袱紗(ふくさ)に包み、式が始まる前の控え時間に、祭祀承継者へ「本日はお疲れさまです。ささやかですがお供えです」などと丁寧に手渡すのが良いとされています。読経の直前や工事中のタイミングは避け、静かな場面を見計らいましょう。
3. 故人や施主への敬意を忘れずに行動する
儀式中の私語やスマートフォンの操作は避け、焼香・合掌の場面では丁寧な所作を意識します。また、会食の場では費用や相続などの話題を持ち出さないことも、親戚間の良好な関係を保つうえで重要です。

墓じまい当日は、儀式の種類や地域によって流れや作法が異なる場合もありますが、親戚としての気配りと思いやりが何より大切です。静かに、丁寧に、故人とご遺族への敬意を持って参加しましょう。
まとめ|親戚として失礼のない対応をするには?
墓じまいに参列する親戚として、最低限押さえておきたいのは「金額の相場」「表書きのマナー」「立ち振る舞い」の3つです。儀式の種類によって包む金額や袋の選び方が異なるため、事前に確認し、迷った場合は祭祀承継者や他の親族に相談しましょう。
表書きには「御香典」など葬儀用の言葉を使わず、閉眼供養では「御供」、納骨式では「御仏前」、新しいお墓への開眼法要では「建碑祝」を用いるのが基本です。袋の水引の色やお札の種類(新札・旧札)も、弔事・慶事に応じて選びます。
また、渡す際のタイミングや服装にも気を配る必要があります。略喪服や地味な平服を選び、金封は袱紗に包んで丁寧に渡すのがマナーです。声かけの一言も忘れずに。
さらに、費用の負担が必要なケースでは、金額や分担割合をあいまいにせず、必ず事前に話し合いの場を設けることが大切です。書面にしておくと、後々の誤解やトラブルを防げます。

親戚としての礼儀を尽くすことは、故人への敬意だけでなく、遺族への配慮にもつながります。不安があれば一人で抱え込まず、他の親族と協力して進める姿勢が、円満な墓じまいへの第一歩です。