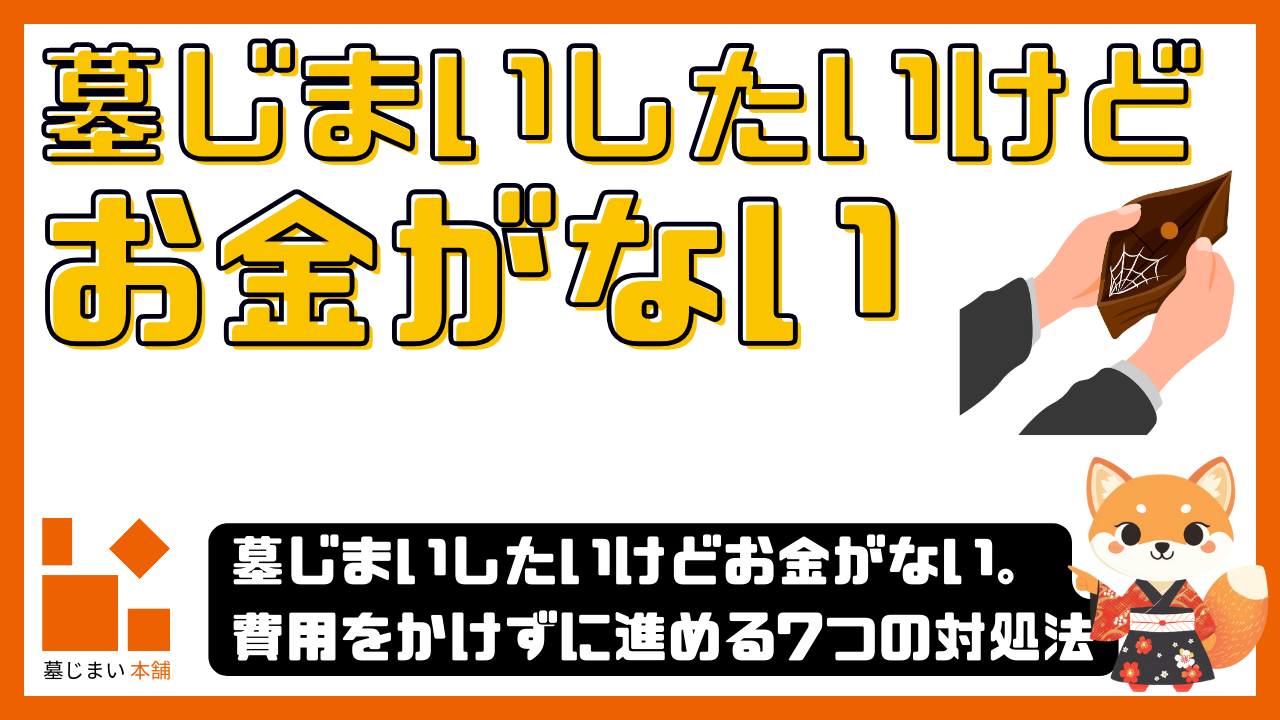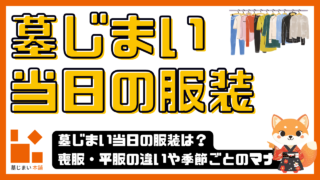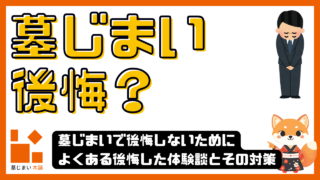本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいにお金がかかる理由とは?
墓じまいは「お墓を片づけるだけ」と考えてしまいがちですが、実際には複数の工程と費用が発生します。
そのため、想像以上に高額になるケースが多く、「お金がない」と悩む方が増えています。
ここでは、墓じまいにお金がかかる主な理由と費用の内容を詳しく解説します。
墓石の解体・撤去費用
墓じまいで最も大きな費用となるのが、墓石の解体と撤去費用です。墓石は一つひとつが重く、専用の機械や人手を使って丁寧に撤去しなければなりません。作業する場所が山間部や道が狭い場所であれば、重機の搬入ができず、人力での作業となり費用がさらに高くなります。
解体費用は、一般的に1平方メートルあたり7万円〜20万円程度が相場です。お墓の広さや石の量、立地条件によっては、50万円以上かかることもあります。
閉眼供養(魂抜き)の費用
墓じまいの前には、仏教の儀式である「閉眼供養(へいがんくよう)」を行います。これは、墓石に宿っているとされる魂を抜くための供養です。仏式では、この供養が済まなければ墓石の撤去作業ができない場合もあります。
閉眼供養では僧侶を招いて読経をしてもらい、お布施として数万円をお渡しするのが一般的です。さらに、交通費(御車代)や御膳料が必要となることもあります。お布施の相場は3万円〜5万円程度ですが、宗派や地域によって異なります。
離檀料がかかる場合もある
お墓が菩提寺(檀家として所属している寺)の墓地にある場合、墓じまいをするとお寺から離れることになります。このとき、これまでの供養や管理に対する感謝の意味を込めて「離檀料(りだんりょう)」を渡すことが多いです。
離檀料に明確な金額の基準はありませんが、3万円〜20万円ほどが一般的です。中には「気持ちだけで良い」と言ってくださる寺院もありますが、反対に高額を請求されるケースもあり、トラブルに発展することもあります。事前に丁寧に相談し、納得のうえで進めることが大切です。
改葬先によってはさらに費用がかかる
墓じまいは「終わり」ではなく「移転」の始まりでもあります。取り出した遺骨を納める新しい供養先(永代供養墓、納骨堂、樹木葬など)を用意する必要があります。これを「改葬」と呼びますが、その費用も墓じまいに含まれると考えるべきです。
新しい供養先の費用は2万円〜数十万円と幅がありますが、複数体の遺骨がある場合や、立地・形式によって大きく異なります。
見積もり外の追加費用にも注意
墓じまいの費用には、工事費や供養費のほかに、行政手続きに関する手数料、遠方からの出張費、撤去後の整地費用などが加算されることがあります。また、墓石に使われている素材や装飾の有無によっても作業量が変わるため、見積もり以上の費用を請求されるケースもあります。
費用を正確に把握するには、現地での事前調査と詳細な見積もりが欠かせません。書面で契約を交わし、追加料金の有無や内訳をしっかり確認することが重要です。

墓じまいには、多くの工程と予想外の出費が伴います。家族や親族と十分に相談し、信頼できる業者に依頼することで、無理のない計画を立てて進めることができます。
「墓じまいしたいけどお金がない」…よくある悩みとは?
「お墓をきちんと片づけたい」「遠方の墓を将来誰も見られないのは不安」と思っても、現実的な問題として立ちはだかるのが「費用」の壁です。墓じまいは一度きりの大きな出費になるため、金銭的に余裕がないと感じる方にとっては、なかなか踏み切れない問題でもあります。ここでは、実際によくある「墓じまいしたいけどお金がない」という悩みの背景を見ていきます。
実家のお墓が遠方にあり、管理が難しい
地方にお墓があり、自分や家族が都市部に暮らしている場合、「年に一度行けるかどうか」というケースが少なくありません。帰省やお墓参りにかかる交通費・宿泊費も負担となり、管理のたびに時間とお金がかかってしまいます。
「母が一人で管理しているが、高齢で墓まで通うのも限界」「お墓の前に行っても草が伸び放題で申し訳ない」——そうした状況から墓じまいを検討し始める方が多くいます。しかし、いざ動こうとしても費用のことが頭をよぎり、踏み出せないまま年月が過ぎてしまうのです。
管理していた親が高齢に…継承に悩む子世代
「これまで親が管理してくれていたが、自分の代になったとき引き継げるのか不安」という声は非常に多く聞かれます。特に、親が元気なうちに墓じまいを進めたいと思っても、費用の負担を一人で背負うのは難しいものです。
兄弟姉妹がいたとしても、「誰がどれだけ出すか」「そもそも賛成してくれるのか」という点で話し合いが進まず、結果的に「自分でなんとかしよう」と思い悩む方も少なくありません。
家計のやりくりに追われ、まとまった費用が出せない
「子どもの教育費や住宅ローンがあり、数十万円を一括で出す余裕がない」「定年後の生活設計が不安で、大きな出費は避けたい」といった悩みも多く見られます。墓じまいにかかる費用は平均で50万円〜100万円ほどかかるケースもあり、収入の少ないシニア世代や単身者にとっては、大きな負担になります。
また、金額だけでなく「この出費は本当に今必要なのか?」「もっと安くできる方法はないのか?」と迷いが生じて、なかなか決断できない方も多いのが実情です。
墓じまいを放置することで起きる“次の問題”も気がかり
お金の問題から墓じまいを先送りにしていると、次第に「このまま何もしないでいたらどうなるのか」という新たな不安も出てきます。
例えば「親が亡くなった後、誰が墓を管理するのか?」「遠方にあるお墓に、将来子どもたちは通えるのか?」などです。さらに、管理費の支払いが滞れば、お墓が無縁仏として扱われ、強制撤去されてしまうリスクもあります。
このように、「今はお金がないから」と先延ばしにしていると、後々のトラブルやさらに大きな費用負担につながることもあります。

「墓じまいをしたいけどお金がない」という悩みは、金銭的な負担だけでなく、心の葛藤や将来への不安も含んでいます。ですが、状況を整理し、正しい情報を知ることで、負担を軽くしながら進める道は必ずあります。次のステップとして、具体的な対処法を一つずつ見ていきましょう。
お金がなくても墓じまいできる?7つの対処法
「お金がないから墓じまいをあきらめるしかない」と思っていませんか? 実は、工夫次第で費用の負担を抑えながら墓じまいを進めることは可能です。ここでは、できる限りお金をかけずに墓じまいを行うための7つの現実的な対処法を紹介します。
1. 家族・親族に相談して協力を仰ぐ
まずは、家族や親戚に率直に現状を伝え、協力をお願いしましょう。墓じまいは個人の問題ではなく、先祖を祀る一族全体の課題です。「自分だけで費用を抱えるべき」と思い込まず、関係する親族に事情を話すことから始めてください。
金銭的な協力が難しい場合でも、情報収集や手続き面で助けてもらえることもあります。できるだけ早い段階で話し合うことが、無理のない進め方につながります。
2. 自治体の補助金制度を調べる
一部の自治体では、墓じまいにかかる費用の一部を補助してくれる制度があります。主に「過疎化対策」や「無縁墓の予防」を目的とした取り組みで、条件を満たせば数万円から十数万円の補助を受けられる可能性があります。
ただし、補助対象地域や支給要件は自治体ごとに異なり、事前申請が必要な場合がほとんどです。お墓のある地域、または自分の居住地の市区町村役場に問い合わせて、利用できる制度があるかを確認してみましょう。
3. 永代供養や樹木葬など、費用を抑えた改葬先を選ぶ
墓じまいをした後、遺骨をどこに納めるかによって費用が大きく変わります。新しくお墓を建てると数十万円〜数百万円かかることもありますが、永代供養墓や樹木葬、納骨堂を選べば、初期費用だけで後の管理費が不要なケースもあります。
特に、合祀(ごうし)タイプの永代供養墓は費用が抑えやすく、数万円程度で利用できるものもあります。費用面だけでなく、後々の管理負担を軽減できる点でも有効な選択肢です。
4. 複数の石材店に相見積もりを依頼する
墓じまいの費用は、業者によって大きく差が出ます。少しでも安く抑えるためには、複数の石材店から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
同じ作業内容でも数万円〜十万円単位で差が出ることがあります。見積書には「追加費用が発生する条件」や「費用に含まれていない項目」なども確認し、納得できる業者を選びましょう。また、現地を実際に見て見積もりを出してもらうと、後からのトラブルを防げます。
5. メモリアルローンの活用を検討する
まとまった資金をすぐに用意できない場合、「メモリアルローン」という選択肢もあります。これは葬儀や供養、墓じまいなどの目的で使える専用のローンで、一般的なフリーローンより金利が低めに設定されているのが特徴です。
年金収入でも審査に通る場合があり、高齢の方でも利用しやすいのがメリットです。ローンには抵抗があるかもしれませんが、「今やらなければいけない」という状況であれば、背負いすぎない返済計画のもとで検討してみてもよいでしょう。
6. 両家墓やネット墓で供養費用を抑える
墓じまい後の供養で費用を抑える手段として、「両家墓」や「ネット墓」も選択肢に入ります。両家墓とは、親族や配偶者の家族と一緒に1つの墓を持つ形で、費用・管理の両面で負担を軽減できます。親族内で話し合い、共同で新たな供養場所を設けるのも方法の一つです。
また、近年はオンライン上で供養ができる「ネット墓」も注目されています。物理的な墓を持たないため初期費用が非常に安く、遠方の親族でも手軽に供養できる利点があります。
7. 墓じまい専門サービスの無料相談を活用する
墓じまいは専門的な知識が必要なため、「どこに相談すればいいかわからない」と悩む方も多いです。そんなときは、墓じまいに特化した専門サービスの無料相談を利用してみましょう。
無料で見積もりをチェックしてもらえたり、安くできる供養方法を提案してもらえたりするケースもあります。無理な営業をされることなく、安心して情報収集できる窓口を使うことで、想像よりもスムーズに進められるかもしれません。

費用の問題で墓じまいを諦める前に、できる対策は数多くあります。大切なのは「一人で抱え込まないこと」。家族や専門家の力を借りて、無理のない形で進めていくことが、後悔のない選択につながります。
墓じまいの費用を抑えるコツと注意点
費用を少しでも抑えたいという思いは、多くの方に共通する願いです。しかし、目先の安さだけを追いかけてしまうと、後々トラブルを招いてしまうこともあります。ここでは、墓じまいを無理なく、かつ安全に進めるためのコツと、特に注意しておきたいポイントを解説します。
業者選びは「価格」よりも「信頼性」が大切
格安の業者に飛びつきたくなる気持ちはわかりますが、極端に安い業者には注意が必要です。実際に、「作業後に高額な追加費用を請求された」「墓石の処分が不法投棄されていた」というケースも報告されています。
費用だけで判断せず、以下の点を確認してから契約するようにしましょう。
- 見積もりの内訳が明確か
- 追加費用の発生条件が書かれているか
- 過去の実績や口コミは信頼できるか
可能であれば、1社だけでなく2〜3社に相見積もりを取り、内容と対応を比較して決めることが大切です。
「追加費用ゼロ」の契約内容を必ず確認する
墓じまいでは、契約時の見積もりよりも費用が高くなるケースがあります。たとえば、工事現場で重機が使えず手作業になる場合や、想定外の埋設物が見つかった場合などです。
こうした「追加費用」のリスクを避けるには、以下の点を事前に確認しましょう。
- 見積書に「追加料金なし」と記載があるか
- 工事範囲や料金に含まれる項目が明記されているか
- 不測の事態が起きたときの対応について業者に説明を求める
契約前には、必ず書面で内容を取り交わし、口頭だけの説明で済ませないことが基本です。
親族や寺院との相談を怠らない
費用面に集中しすぎて、親族や寺院との話し合いを軽視してしまうと、別の問題を引き起こす可能性があります。たとえば、親族間で「聞いていなかった」「勝手に決めた」といった不満が生まれることや、寺院から高額な離檀料を請求されることもあります。
トラブルを避けるためには、以下のような事前相談が不可欠です。
- 親族には費用負担や改葬先について早めに共有する
- 菩提寺がある場合は、丁寧に説明し感謝の気持ちを伝える
- 可能であれば、供養の方向性について合意形成を図る
とくに寺院とは、日頃からの関係性も大切です。相談を通じて離檀料の金額が見直されたり、協力的な姿勢を示してくれることもあります。
無理のないスケジュールで進める
費用を急いで用意しようとすると、焦りから不利な条件で契約してしまうこともあります。時間に余裕を持って計画を立てることで、補助金の申請や複数業者からの見積もり取得なども落ち着いて行えます。
また、工事の繁忙期(春秋のお彼岸・お盆前後)を避けることで、費用が抑えられることもあります。可能な限りスケジュールにゆとりをもたせ、冷静に判断することが重要です。

費用を抑えるための工夫は多くありますが、「安く済ませること」だけを目的にすると、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。大切なのは、ご先祖様への感謝の気持ちを大切にしながら、無理のない方法で、後悔のない選択をすることです。
費用が払えないからといって墓じまいを放置すると?
「今はお金がないから」と墓じまいを先延ばしにしたままにしておくと、さまざまなリスクや問題が発生する可能性があります。墓じまいをしないこと自体は違法ではありませんが、維持管理を放置することで、故人への供養だけでなく、家族や親族に将来的な負担がのしかかってくることになります。ここでは、墓じまいを放置することで起こりうる代表的なリスクについて解説します。
無縁仏になる可能性がある
お墓の管理者(寺院や霊園の管理事務所)と連絡が取れなくなったり、管理費の未納が続いたりすると、そのお墓は「無縁墓」として扱われることがあります。無縁墓と判断されると、管理者の判断で墓石は撤去され、遺骨は他の遺骨と一緒に「合祀墓(ごうしぼ)」に納められることがほとんどです。
合祀墓では個別に遺骨を取り出すことができず、今後、別の供養先へ移すこともできません。つまり、ご先祖様の遺骨を「自分たちの手で供養する」という選択肢を失うことになるのです。
墓地の管理者による強制撤去も
無縁墓と判断された場合、墓地の管理者は法的手続きを経て墓石を撤去することが可能です。このとき、遺族への事前連絡がなされるケースもありますが、音信不通である場合には告知看板の掲示のみで処理が進められることもあります。
強制撤去後には、墓石の破棄や整地費用が別途発生し、その費用を遺族が請求されることもあります。つまり、墓じまいをしなかったからといって「お金がかからない」わけではなく、結果的に予期しない負担が降りかかるケースもあるのです。
管理費用は払い続けなければならない
墓じまいをしない限り、お墓のある霊園や寺院との契約は継続しており、管理費の支払い義務も続きます。支払いが遅れれば、延滞金や催促が届く可能性もあり、心理的なストレスになることもあります。
さらに、今は払えていても、将来的に収入が減少したり、支払いをする人がいなくなったりすれば、その管理費が未納となり、無縁墓扱いへの道をたどるリスクが高まります。
遺族や子ども世代への負担が大きくなる
墓じまいを放置してしまうと、将来的には子どもや孫の世代にそのまま問題が引き継がれてしまいます。「親が亡くなったあと、突然墓の維持を任された」「何十万円もの費用がいきなり必要になった」といったトラブルは実際に多く報告されています。
また、遠方に住んでいる子ども世代が管理費の支払いや掃除、供養のために定期的に通うことは現実的ではありません。遺された家族にとっては、心理的にも経済的にも大きな負担となってしまいます。
墓じまいを放置することで、ご先祖様を望まぬかたちで合祀にすることになったり、費用をさらに膨らませる結果になったりする可能性があります。金銭的な理由で悩んでいる方こそ、早めに対処法を知り、無理のない範囲で計画を立てておくことが大切です。墓じまいは、残された家族を守る「最後の片づけ」の一つとして、できるだけ後回しにしないことが望ましいのです。
よくある質問とリアルな相談事例
墓じまいを考え始めると、「お金がないけど、どうすればいいの?」「他の人はどうしてるの?」といった不安や疑問が次々に湧いてくるものです。このセクションでは、実際に寄せられた相談事例をもとに、特に多い3つの質問とその現実的な対応策を紹介します。同じような悩みを抱えている方の参考になるよう、できる限り具体的にお伝えします。
離檀料が払えないときはどうすれば?
「寺院墓地にあるお墓を墓じまいしたいけれど、離檀料が高すぎて払えない」という相談は非常に多く見られます。離檀料には明確なルールがなく、寺院によっては数万円〜20万円程度を求められることもあります。
このような場合は、まずお寺に対して丁寧に事情を説明することが重要です。「費用が用意できず困っている」「それでもこれまでのお世話に感謝している」といった気持ちを率直に伝えることで、金額の相談に応じてもらえるケースも少なくありません。
また、近年は離檀料を「任意の寄付」とする寺院も増えています。感情的にならず、冷静かつ誠意をもって話し合いをすることが、円満に墓じまいを進める鍵となります。
見積もりが高すぎる…本当に妥当?
「複数の業者に見積もりを取ったけれど、どれも予想以上に高額」「この金額が相場なのかわからない」という声もよく聞かれます。実際、墓じまいの費用は立地・墓の大きさ・作業の難易度などで大きく変わります。
目安として、墓石の解体・撤去費用は1平方メートルあたり10万円前後。ただし、山間部や重機が入らない場所、特殊な墓石構造の場合は倍以上になることもあります。高額な見積もりに不安を感じたら、必ず「内訳」を確認しましょう。
内訳に不明な点がある場合は、業者に遠慮せず説明を求めましょう。「閉眼供養費」「整地費」「交通費」などが含まれているか、他社の見積もりと比べてどの項目が高いのかを確認することで、交渉や業者選びの判断材料になります。
また、墓じまい専門の第三者相談窓口に見積もりを見せて、客観的なアドバイスを受ける方法もあります。
墓じまいを先延ばしにするとどうなる?
「今すぐにはお金が用意できない」「少し落ち着いてから」と先延ばしにするケースもありますが、何年も放置すると問題が複雑になることがあります。
たとえば、墓地の管理費を払わずに放置していると、無縁墓として扱われ、最終的には合祀されてしまう可能性があります。そうなると、遺骨を個別に取り出すことはできなくなり、自分の意思で供養方法を選ぶこともできなくなります。
また、墓地の強制撤去に関する通知が出た場合、短期間で対応を求められ、急な出費を強いられることもあります。そうなる前に、無料相談サービスを活用して「今できる最低限の準備」を始めることが、将来の負担を減らす第一歩です。

費用の悩みは、墓じまいを考える上で避けては通れない問題です。しかし、同じように悩みながらも前に進んでいる方が多くいます。一人で抱え込まず、少しでも早く、少しずつでもいいので行動を始めることが、後悔しない選択につながります。
まとめ:お金がないなら“今すぐ行動”が未来を変える
「お金がないから墓じまいは無理」と考えて、何年も手をつけられないままにしてしまう方は少なくありません。しかし、墓じまいは先送りにすればするほど負担が膨らみ、状況は悪化していくばかりです。費用の問題を抱えているからこそ、“今すぐ行動する”ことが何よりも大切です。
墓じまいの費用は、調べてみると想像以上に差があるものです。石材店によって金額が大きく異なることもあれば、改葬先を工夫することで数十万円単位で費用を抑えることも可能です。補助金制度やメモリアルローン、無料相談サービスなど、公的・民間の支援制度も活用できます。
また、家族や親族との話し合いを早めに始めておけば、費用の分担や協力体制が整い、精神的な負担も軽減されます。墓じまいは家族の未来に関わる重要な決断だからこそ、一人で抱え込まず、できることから一歩を踏み出すことが重要です。
「まずは誰かに相談してみる」「見積もりだけ取ってみる」「改葬先を見学してみる」——こうした小さな行動の積み重ねが、最終的には納得のいく墓じまいにつながります。無料で利用できる窓口や情報収集サービスを活用しながら、焦らず、自分たちのペースで前へ進んでください。

お金がなくても、知識と行動力があれば、墓じまいは決して不可能ではありません。今の一歩が、ご先祖様と家族を守る未来につながります。
平日10時~18時