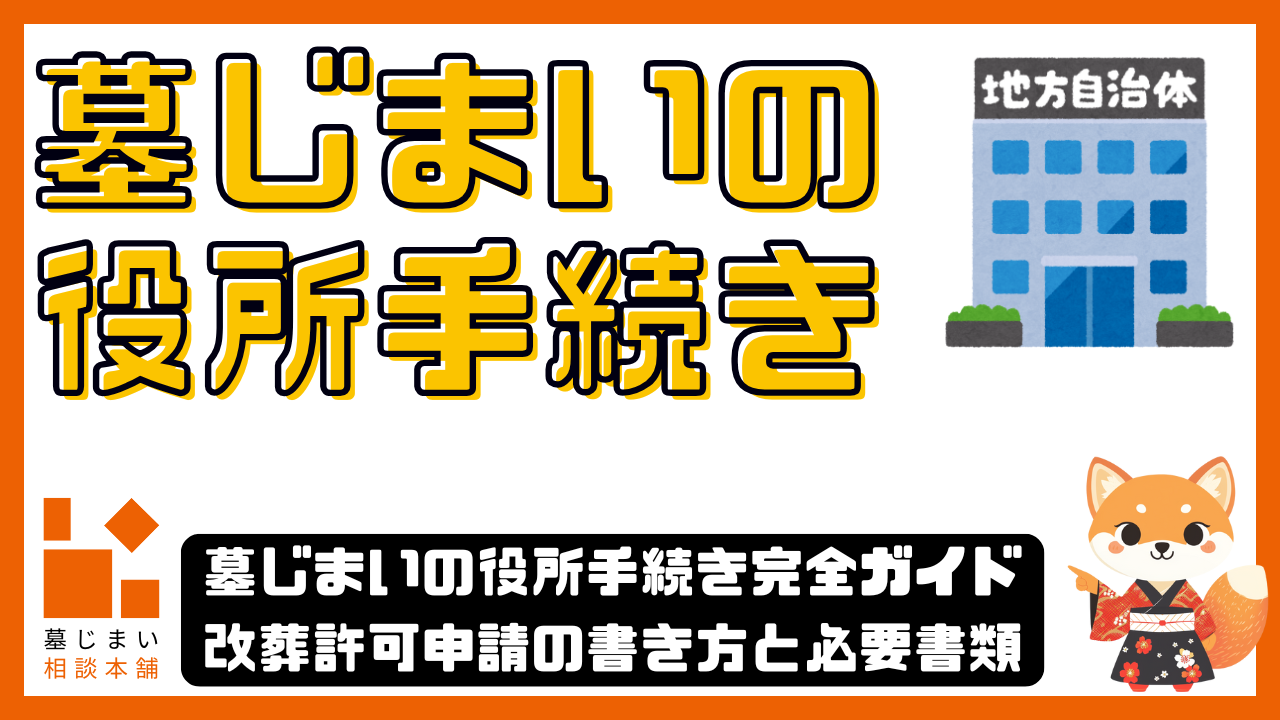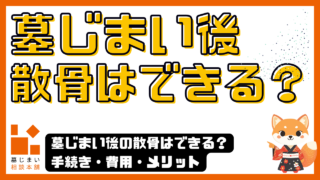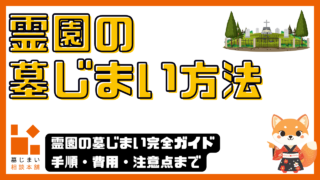本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいに必要な役所手続きとは?
墓じまいを行う際、避けて通れないのが自治体での役所手続きです。これは単なる形式ではなく、法律で定められた「改葬許可」を得るための正式な手続きとなります。墓じまいとは、墓石を撤去し、遺骨を別の場所へ移す一連の流れですが、その中核にあるのが役所での申請です。
まず、改葬には現在のお墓がある市区町村の役所での「改葬許可申請」が必要です。勝手にお墓を撤去したり遺骨を移動することは法律で禁じられており、無許可の移動は罰則対象にもなります。これを規定しているのが、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律です。
手続きの窓口は「環境衛生課」や「市民生活課」「福祉課」など、自治体によって異なります。申請には所定の書類が複数必要で、主に以下のようなものが求められます。
- 改葬許可申請書(役所で入手またはホームページからダウンロード可能)
- 埋蔵証明書または申請書内の墓地管理者による署名・捺印
- 新しい墓地(改葬先)の受入証明書
- 墓地の使用者の承諾書(申請者と使用者が異なる場合)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証や保険証のコピーなど)
なお、書類の記載内容には、埋葬されている方の氏名や没年月日、現在の墓地の所在地、改葬先の情報などを含みます。もし不明な情報がある場合でも、「不詳」や「不明」と記載することで受理されるケースが多く見られます。
改葬許可申請書の提出方法は、窓口持参または郵送で対応できる自治体が多いため、遠方に住んでいても手続き可能です。ただし、郵送での申請を希望する場合は、返信用封筒(切手付き)を同封するなど、細かな指定があることもあるので、あらかじめ自治体のホームページで確認するか電話で問い合わせると安心です。
また、1体の遺骨につき1枚の改葬許可証が発行されます。たとえば3体の遺骨を移す場合は3枚分の手続きが必要です。これらの許可証は、移転先の墓地や納骨堂に遺骨を受け入れてもらう際に提出が求められます。散骨や手元供養を希望する場合でも、自治体によっては改葬許可証の取得を求められるケースがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

このように、墓じまいは単なる作業ではなく、自治体との調整や必要書類の収集・作成など、一定の事務手続きが必要となります。不備があると再提出を求められることもあり、事前の準備がスムーズな進行の鍵となります。特に書類の内容や署名・押印の不備が多く見られるため、記入例や相談窓口を活用しながら、丁寧に進めることが大切です。
行政手続きの流れをわかりやすく解説
墓じまいにおける行政手続きは、「改葬許可申請」に関する書類のやり取りが中心となります。ここでは、申請のタイミングから許可証の交付まで、どのように進めていくのかを具体的にご説明します。
1. 手続き開始のタイミング
行政手続きは、墓地の管理者・親族の了承が取れ、改葬先が決まった後に行います。改葬先が未定のままでは手続きが進められないため、「新しい納骨先を決めてから」が原則です。また、墓石の解体工事より前に、必ず改葬許可証を取得しておく必要があります。
2. 改葬許可申請の一般的な流れ
手続きは以下の6ステップで進みます。
- 改葬許可申請書を入手する
申請書は、お墓のある自治体の役所(環境衛生課など)でもらえます。自治体のホームページからダウンロードできることも多いです。 - 必要事項を記入する
申請書には、申請者の氏名・住所、遺骨の埋葬情報(氏名、埋葬年月日など)、改葬先の住所や墓地名、改葬理由などを記入します。不明な情報がある場合は「不明」と記載すれば受理されるケースもあります。 - 墓地管理者の署名・捺印をもらう
現在の墓地の管理者(霊園の管理事務所やお寺など)に書類を持参し、署名・捺印をしてもらいます。一部の自治体では、代わりに「埋蔵証明書」を発行してもらう形式もあります。 - 改葬先から受入証明書をもらう
新しい納骨先の管理者から、遺骨を受け入れることを証明する「受入証明書」を発行してもらいます。墓地の契約完了後に発行されることが一般的です。 - 申請者と墓地使用者が異なる場合、承諾書を添付する
申請者と現在の墓地の名義人(使用者)が違う場合は、名義人からの承諾書が必要になります。承諾書は役所でテンプレートが配布されていることが多いです。 - 書類一式を提出する
全ての書類が揃ったら、役所の窓口または郵送で提出します。郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付済み)を同封するよう求められる場合もあります。
3. 書類提出後の流れ
提出後、役所で内容の確認が行われ、不備がなければ「改葬許可証」が交付されます。許可証の発行には数日〜1週間程度かかる自治体もあるため、余裕を持って申請しましょう。
改葬許可証は、1体の遺骨につき1通必要です。複数の遺骨を同時に改葬する場合は、それぞれに申請と許可証が必要になる点に注意してください。
また、許可証は新しい墓地や納骨堂へ納骨する際に提出を求められます。散骨や自宅供養を希望する場合も、自治体によっては改葬許可証の提出が必要になるため、事前に確認しておくことが重要です。
4. 窓口・郵送の選択肢について
多くの自治体では、郵送による手続きにも対応しています。遠方に住んでいる方や、仕事などで時間が取れない方にとっては負担の少ない方法です。ただし、原本書類の紛失防止や押印漏れには十分注意してください。

このように、行政手続きには複数の関係者との連携と、段階を踏んだ進行が求められます。焦らず一つずつ確認しながら進めることで、スムーズに手続きを終えることができます。
墓じまいで必要になる書類一覧
墓じまいの手続きを進めるうえで、役所に提出すべき書類は非常に重要です。不備があると手続きが遅れる原因となるため、必要書類を事前にしっかりと把握しておきましょう。ここでは、実際に提出が求められる書類の一覧と、その入手先、記載上の注意点について詳しく解説します。
改葬許可申請書
墓じまいの中心となる書類です。現在のお墓がある自治体の役所で配布されており、多くの場合はホームページからダウンロードも可能です。記入内容には、申請者の情報、埋葬されている故人の氏名・没年月日・火葬場所、改葬先の情報などがあります。
記入欄には空欄がないよう注意し、不明な項目がある場合は「不詳」と記入することで受理される自治体もあります。署名・押印も忘れずに行ってください。
埋蔵(埋葬)証明書または改葬許可申請書内への管理者の署名・捺印
現在の墓地に埋葬されている遺骨の存在を証明するための書類です。墓地の管理者に発行を依頼する必要があります。
自治体によっては、改葬許可申請書の所定欄に墓地管理者の署名・捺印があれば、別途証明書は不要とされる場合もあります。民営霊園であれば管理事務所、公営霊園であれば市区町村、寺院墓地の場合はお寺に確認しましょう。
受入証明書
改葬先である新しい墓地や納骨堂などが、遺骨を受け入れることを証明する書類です。改葬先の管理者に発行してもらいます。墓地の契約時に発行されることが一般的です。
自治体によっては、改葬許可申請書内に改葬先の名称・所在地などを記載するだけで済む場合もあります。必ず自治体のホームページや窓口で確認してください。
承諾書(申請者と墓地使用者が異なる場合)
申請者が墓地の使用者(名義人)と異なる場合には、使用者の承諾が必要です。自治体によっては、所定の様式が用意されており、ホームページや役所窓口から入手できます。
承諾書には、使用者本人の署名と押印が必要です。実印での押印を求められる自治体もありますので、印鑑の種類にも注意しましょう。
申請者の身分証明書の写し
運転免許証や健康保険証など、本人確認ができる書類のコピーが求められます。原本の提示を求められるケースもあるため、窓口で手続きする場合は持参しましょう。
身分証明書が不要とされる自治体もあるため、事前の確認が重要です。
その他、自治体が指定する書類
墓じまいをする墓地の種類や、遺骨の数、申請者と故人との関係性などによって、追加で書類の提出を求められる場合があります。たとえば以下のようなケースです。
- 墓地使用許可書のコピー(墓地の使用者を確認するため)
- 墓地返還届(公営霊園などで墓所を返却する際に必要)
- 墓地の管理者からの承認書類
- 委任状(代行者が手続きする場合)
また、申請書類1セットごとに手数料が発生する自治体もあります。300円前後が一般的ですが、現金書留や定額小為替が必要になる場合もあります。
自治体による書式の違いに注意
書類名や様式は全国で統一されておらず、自治体ごとに異なります。たとえば「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「収蔵証明書」など呼び方もさまざまです。必ずお墓のある自治体のホームページまたは窓口で最新情報を確認しましょう。

これらの書類は、1体の遺骨ごとに必要になるのが基本です。複数体を同時に改葬する場合は、それぞれに対して書類一式を揃える必要があります。不備があると手続きが遅れるため、書類はコピーを取りながら慎重に準備してください。自治体や墓地管理者とこまめに連絡を取りながら進めることが、スムーズな墓じまいの第一歩となります。
墓じまい後に改葬許可証が必要になる場面とは
改葬許可証は、墓じまいの手続きが完了した証明となる書類であり、遺骨の移動先で正式に納骨や供養を行うために必要不可欠です。行政から交付されるこの証明書は、単なる通過点ではなく、墓じまい後も重要な役割を果たします。ここでは、具体的にどのような場面で改葬許可証が必要になるのかを解説します。
新しい墓地や納骨堂に納骨する場合
最も基本的かつ重要な用途が、新たな納骨先での提出です。改葬許可証がなければ、遺骨の受け入れを断られるケースもあるため注意が必要です。多くの霊園や納骨堂では、受入証明書の確認とともに、改葬許可証の原本の提示を求められます。
特に、次のような施設では提出が必須となるのが一般的です。
- 公営墓地(市営・町営の霊園など)
- 民間霊園
- 寺院墓地
- 納骨堂(屋内型霊園など)
万が一、許可証を紛失してしまった場合、再発行の可否は自治体の判断により異なります。紛失を防ぐため、納骨が完了するまで厳重に保管しましょう。
自宅で一時保管する場合(手元供養)
墓じまい後、すぐに新しいお墓が決まっていない方や、しばらく自宅で保管したいという方も少なくありません。いわゆる「手元供養」と呼ばれる形です。この場合、自治体によっては「自宅保管を改葬先と見なす」として、改葬許可証の取得が必要になることがあります。
また、自宅での保管を経て将来的に改めて納骨をする場合、改葬許可証の提示を求められる可能性があります。トラブルを避けるためにも、保管中であっても許可証は保有し続けましょう。
遺骨を散骨する場合
近年、海や山への「散骨」を選ぶ方も増えています。散骨は法律上「葬送の一つ」とされ、特別な許可は不要とされていますが、多くの自治体では散骨に先立って「改葬許可証を取得すること」を求めています。
たとえば、寺院や霊園から遺骨を取り出すには、改葬許可証がなければならず、散骨をするしないに関わらず行政手続きが必要ということです。さらに、散骨業者によっては、依頼時に改葬許可証の提示を義務付けているケースもあります。
海外に遺骨を移す場合
故人の意思や家族の事情により、遺骨を海外に持ち出して供養する場合もあります。この場合、入国先の国によっては日本側で発行された改葬許可証を必要書類として求められることがあります。航空会社によっても、遺骨の輸送時に改葬許可証の提示が義務付けられていることがあるため、国際移動に際しても許可証は非常に重要です。
複数の遺骨をまとめて改葬する場合
家族の遺骨を一つの墓地や永代供養施設にまとめて移す際には、遺骨の人数分だけ改葬許可証が必要です。それぞれの故人について別個の申請と許可証が発行されているため、移転先ではすべての許可証を提示しなければならない点に注意してください。

このように、改葬許可証は墓じまいを終えたあとも、さまざまな場面で提出が求められる重要な書類です。散骨や自宅供養のように、一見すると不要に思える供養方法であっても、手続き上必要とされるケースがあるため、軽視せず丁寧に保管しておきましょう。許可証を取得した日付や内容も、家族で共有しておくことをおすすめします。
自治体によって違う手続きのポイント
墓じまいの手続きは、全国一律ではなく、自治体ごとに書式や提出先、必要書類などが異なります。そのため、同じように進めたつもりでも「この書類では受け付けられません」と返されることも珍しくありません。ここでは、自治体ごとに異なる具体的な違いと、注意すべきポイントを解説します。
窓口が異なる
改葬許可申請の窓口は、「環境衛生課」「市民生活課」「福祉課」「戸籍課」「住民課」など自治体によってさまざまです。役所に行く前に必ずホームページで担当課を確認し、できれば電話で事前相談しておくと安心です。
改葬許可申請書の様式がバラバラ
改葬許可申請書は全国共通のフォーマットではなく、各自治体が独自の様式を採用しています。必要な記載事項も異なり、たとえば「改葬の理由」や「火葬場の名称」など、細かい項目がある場合もあります。
また、手書きでの記入を推奨している自治体もあれば、パソコン入力を許可している自治体もあります。書類の不備による差し戻しを防ぐため、申請書の記入要領も事前に確認しておきましょう。
「埋蔵証明書」が不要なケースもある
一部の自治体では、「埋蔵証明書」を別紙で提出するのではなく、改葬許可申請書内の欄に墓地管理者の署名と押印があればよいとされています。逆に、署名・押印ではなく、必ず証明書を添付するよう求める自治体もあります。
お墓が公営墓地や民間霊園にある場合、証明書の発行元は管理事務所です。寺院墓地の場合は住職から発行してもらいます。いずれにせよ、どの方式が必要かは役所で事前に確認が必要です。
「受入証明書」の扱いも異なる
改葬先の受入証明書についても、自治体ごとに運用が異なります。たとえば、
- 書式の有無(自由書式可か、指定のものがあるか)
- 契約書のコピーで代用できるか
- 改葬先が決まっていない場合の扱い(受理不可か、仮申請可か)
など、対応が分かれます。特に永代供養や樹木葬のような新しい形態の供養先では、受入証明の形式が分かりにくい場合もあるため、注意が必要です。
「承諾書」への印鑑の種類に注意
墓地の使用者と申請者が異なる場合に必要な「承諾書」ですが、押印の条件も自治体によって異なります。
- 認印で可の自治体
- 実印が必要な自治体
- 印鑑登録証明書の添付を求められる自治体
実印が必要な場合、使用者が高齢だったり遠方に住んでいたりすると取得が難しいこともあるため、早めの確認が重要です。
特殊なケースへの対応がまちまち
以下のようなイレギュラーケースでは、自治体によって対応が異なります。
- 改葬先がまだ決まっていない
- 土葬された遺体を火葬して納骨し直す場合
- 無縁墓地で使用者が不明な場合
- 遺骨がすでにないお墓を撤去する場合
たとえば、土葬されたお墓を墓じまいする場合でも、改葬許可は不要とする自治体もあれば、形式上の申請を求めるところもあります。また、お墓の使用許可書や古い戸籍の写しが追加で求められることもあるため、少しでも不安がある場合は窓口に事前相談することが大切です。
書類の提出方法にも違いがある
書類の提出についても、
- 郵送可能か
- 窓口持参のみか
- 電子申請に対応しているか
など、運用ルールはまちまちです。郵送に対応していても、「返信用封筒に切手を貼って同封」など細かな指定があるため、誤ると手続きがストップします。

このように、墓じまいの役所手続きは「自治体ごとのルールに沿うこと」が成功のカギです。少しでも不明点がある場合は、自己判断せず、お墓のある自治体の担当窓口に早めに問い合わせましょう。最初のひと手間が、スムーズな墓じまいへの第一歩となります。
墓じまい手続きが不安な方へ|代行サービスも選択肢
墓じまいの役所手続きには、改葬許可申請書の作成をはじめ、関係書類の収集や各所への確認・連絡など、思った以上に細かな作業が発生します。特に、離れた地域にお墓がある場合や、仕事や家庭の都合で動けない方にとっては、大きな負担となることもあります。こうした不安や負担を軽減する手段として、「代行サービスの利用」という選択肢があります。
行政書士など専門家に依頼できる内容
墓じまいに関する代行サービスは、主に行政書士や墓じまい専門の業者が提供しています。依頼できる内容は多岐にわたり、以下のような作業を任せることができます。
- 改葬許可申請書の作成・提出
- 墓地管理者や改葬先との連絡・書類の取り寄せ
- 埋蔵証明書や受入証明書など、関係各所とのやり取り
- 墓地の解体業者の選定と見積もり取得
- 必要に応じて寺院との連絡や離檀交渉
- 書類の不備があった場合の再提出対応
役所とのやり取りや書類作成に不安がある方、高齢で役所に出向くのが難しい方、家族が遠方にいて調整が困難な方などにとって、代行サービスは心強い存在です。
代行費用の目安とメリット・デメリット
代行サービスの費用は、依頼する内容や地域によって異なりますが、以下が一般的な相場です。
- 書類作成・申請代行のみ:3万円~6万円程度
- 墓地管理者・改葬先との交渉を含む場合:5万円~10万円程度
- 墓石の解体・現地立ち会いなどを含めたフルサポート:10万円~15万円以上
【メリット】
- 自分で複雑な書類を調べて準備する手間が省ける
- 行政や墓地関係者との連絡や調整を任せられる
- 法律に基づいた正確な手続きが可能
- 遠方でも現地に行かずに完了できる場合がある
【デメリット】
- 自分で手続きするよりも費用がかかる
- 業者の選定を誤ると、必要な書類が不十分なまま進められるリスクがある
- 業務範囲外の対応をしてもらえない場合もある(例:宗教的儀式の代行など)
費用の負担はあるものの、精神的・時間的な余裕が得られるという点で、多くの利用者が満足しているという声もあります。
依頼する際に注意すべきポイント
代行サービスを利用する際は、以下のような点に注意しておくと安心です。
- 行政書士の資格を確認する
正式な代行には行政書士などの国家資格が必要です。無資格の業者に依頼してしまうと、トラブルや手続きのやり直しになる恐れがあります。 - 見積書の内訳を事前に確認する
どの作業にいくらかかるのか、明確に説明してもらいましょう。「一式●万円」のような曖昧な表記には注意が必要です。 - 対応範囲をしっかり聞く
役所手続きのみ対応する業者もあれば、現地の解体工事や閉眼供養の手配まで含む業者もあります。自分の希望する範囲が対応可能か、事前確認が重要です。 - キャンセル規定や追加料金の発生条件を確認する
途中で事情が変わった場合に備え、契約書や規約に目を通しておくことをおすすめします。

自分での手続きに不安がある方や、家族全員が忙しく手が回らないと感じている方にとって、代行サービスは非常に有効な選択肢となります。お金をかけてでも「確実に、丁寧に」進めたいという方は、信頼できる専門家への依頼も前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
よくある質問(Q&A)
Q1. 遠方に住んでいても手続きはできますか?
はい、可能です。多くの自治体では、改葬許可申請書や必要書類を郵送でやり取りできる体制が整っています。申請書のダウンロードや郵送先などの詳細は、お墓のある自治体の公式サイトで確認できます。返信用封筒(切手付き)や本人確認書類のコピーが求められることもあるため、事前に電話などで問い合わせておくとスムーズです。
Q2. 墓地の使用者(名義人)が亡くなっている場合はどうなりますか?
使用者がすでに亡くなっている場合は、祭祀承継者(お墓を継ぐ権利のある方)が手続きを行います。承継者が決まっていない場合や不明な場合は、役所で所有者変更の手続きが必要になることがあります。親族間で合意を得たうえで、戸籍謄本などを用意し、まずは役所の担当課に相談しましょう。
Q3. 役所に行くのは何回くらいですか?
窓口での申請を行う場合、通常は1~2回です。書類の提出と改葬許可証の受け取りが主な用件になります。ただし、書類に不備があった場合や追加書類の提出を求められた場合は、再度訪問が必要になることがあります。郵送手続きを選べば、役所に出向く必要はありません。
Q4. 改葬許可証は何枚必要ですか?
遺骨1体につき1枚の改葬許可証が必要です。たとえば、3名分の遺骨を改葬する場合は、申請書・証明書なども3体分ずつ用意し、許可証も3枚発行されます。申請時に提出書類が重複しないよう、きちんと整理しておくことが大切です。
Q5. 書類に不明な項目がある場合はどうすればいいですか?
故人の火葬場や埋葬日などが不明な場合でも、「不明」や「不詳」と記載することで受理される自治体もあります。可能であれば、古い戸籍を取り寄せて確認する方法もありますが、無理にすべてを埋める必要はありません。記載に不安がある場合は、申請前に役所に確認しましょう。
Q6. 改葬先が決まっていなくても申請できますか?
基本的には改葬先が決まっていないと申請は受け付けられません。改葬許可証の発行には、遺骨の受け入れ先を証明する「受入証明書」が必要です。改葬先が未定のままでは手続きが進まないため、先に納骨先を決めてから申請の準備を始めてください。
Q7. 自宅保管や散骨の場合も手続きは必要ですか?
はい、多くの自治体では必要とされています。手元供養や散骨であっても、現在のお墓から遺骨を取り出すためには改葬許可証が必要になるのが一般的です。特に散骨業者によっては、改葬許可証の提出を必須としている場合もあります。
Q8. 土葬されているお墓も墓じまいできますか?
土葬のお墓も墓じまいは可能ですが、掘り起こしや火葬が伴うケースでは、事前に自治体へ相談する必要があります。火葬を行う場合は改めて火葬許可が必要になる可能性があります。お墓の状態や地域によって対応が異なるため、まずは墓地管理者と役所へ確認しましょう。
Q9. 無縁墓や個人墓地の場合はどう手続きすればいいですか?
使用者や管理者が不明な無縁墓や、個人所有の墓地の場合は、まず役所に相談してください。墓地台帳や登記記録で確認できる場合もありますが、情報がない場合は手続きの前に墓地の承認や許可を受け直す必要があることもあります。ケースによっては行政書士などの専門家の協力が必要になります。
Q10. お寺にあるお墓を墓じまいする場合、何か特別な注意点はありますか?
寺院墓地の場合は、墓じまいが檀家離脱を意味するため、事前に丁寧に説明することが大切です。離檀料が必要になることもあり、金額に関してトラブルが発生するケースもあるため、早めにお寺と相談し、書面などで確認を取ることをおすすめします。交渉が難しい場合は、専門家に相談して対応してもらうと安心です。
まとめ|失敗しないための準備ポイント
墓じまいを円滑に進めるためには、事前準備と関係者との連携が欠かせません。とくに自治体によって手続きの流れや必要書類が異なるため、「どこから手をつけてよいかわからない」と感じる方も多いでしょう。ここでは、実際に役所手続きを始める前に押さえておくべき準備のポイントを整理してお伝えします。
墓地管理者・改葬先・役所の三者を早めに確認する
役所手続きの中心は「改葬許可証」の取得ですが、そのためには「現在の墓地」「新しい墓地」「自治体窓口」の三者が関係します。
どれか一つでも不明確なままだと手続きは進みません。まずは以下を明確にしておきましょう。
- 現在の墓地の管理者(お寺・霊園管理事務所など)と連絡が取れるか
- 改葬先(新たな納骨先)が決まっているか、契約が済んでいるか
- 墓地所在地の自治体のホームページで、必要書類や申請窓口を確認済みか
この三者の情報が揃えば、手続きはぐっと進めやすくなります。
書類は余裕をもって準備し、コピーも控えておく
申請に必要な書類は、遺骨の数や関係者の状況によって異なります。
特に注意すべきは以下の点です。
- 改葬許可申請書:不明な項目は無理に空欄を埋めず、役所に確認する
- 埋蔵証明書や受入証明書:管理者の署名・押印が必要。郵送可能かも確認
- 承諾書:使用者と申請者が異なる場合に必須。印鑑の種類に注意
- 書類一式はコピーをとり、提出後のトラブル防止に備える
自治体によっては申請1件ごとに手数料が発生します。費用や書類の形式を事前にチェックしておくと安心です。
不安な場合は無料相談や代行サービスを積極的に活用する
「遠方に住んでいて現地に行けない」「親が亡くなって名義の確認が難しい」など、家族構成や状況によって手続きが複雑になるケースもあります。
そのようなときは、以下のようなサポートを活用しましょう。
- 自治体の電話窓口での無料相談
- 墓じまいの見積もりや相談を受け付けている石材店や霊園サービス
- 行政書士などの有資格者による代行サービス
代行費用はかかりますが、自分での負担やトラブルを減らすことができます。特に高齢者や多忙なご家族には、時間と労力の節約として有効な選択肢です。

墓じまいは心の整理をともなう大切な節目ですが、役所手続き自体は「書類の準備」と「関係者との調整」に尽きます。ひとつずつ着実に確認しながら進めることで、不安や混乱を減らし、後悔のない形で故人を新たな場所へ送り出すことができるでしょう。