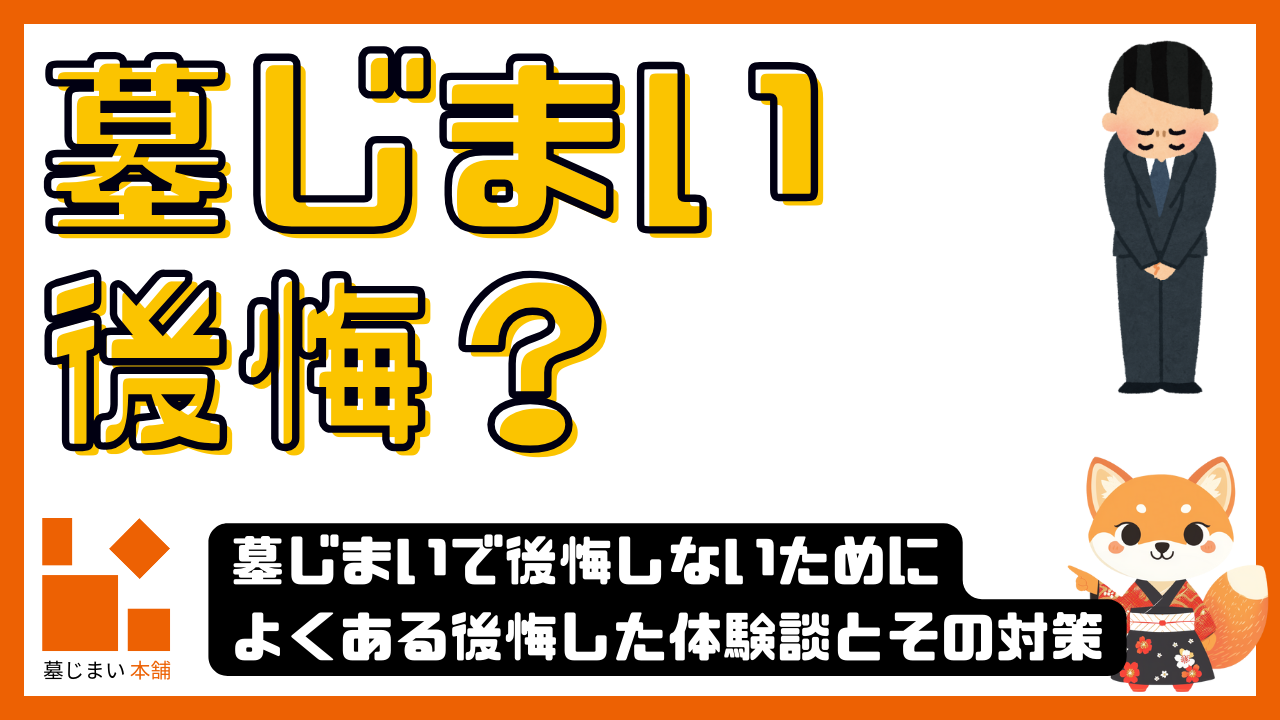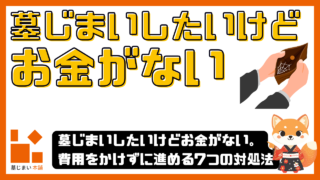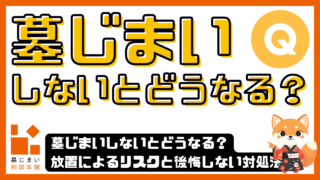本ページはプロモーションが含まれています。
「墓じまいをしてよかった」と心から思える人がいる一方で、実際には「やるんじゃなかった」と後悔してしまう方も少なくありません。特に、終活の一環として墓じまいを検討している方や、親の意向を受けて動こうとしているご家族にとっては、非常に慎重に判断すべき大きな選択です。
お墓は単なる石の建造物ではなく、先祖を敬い、家族の絆を感じる象徴でもあります。そうした存在を手放す決断は、想像以上に心身への負担が大きく、また法的・金銭的な手続きも複雑です。そして何より、墓じまいは一度実行すれば元に戻せないという点で、大きな責任を伴います。
「親族から強く反対された」「納骨先を合祀にしたら遺骨が戻せなかった」「費用が予想以上にかかって生活が圧迫された」など、実際に後悔した方の声からは、感情面だけでなく準備不足や情報不足も浮かび上がっています。多くの場合、「もっと早く調べておけばよかった」「誰かに相談すればよかった」という声が後を絶ちません。
一方で、早い段階から情報収集を始め、家族とよく話し合い、プロのサポートをうまく活用した人たちは、「すっきりした」「将来の不安が減った」と前向きな結果を得ています。つまり、墓じまいで後悔するかどうかは、選び方や準備の質によって大きく変わるのです。

この記事では、墓じまいに踏み切る前に知っておくべき注意点や、実際に多くの人が悩み苦しんだ後悔の実例をもとに、「どうすれば後悔しない墓じまいができるのか」をわかりやすく解説していきます。ご自身のために、またご家族のために、納得のいく選択ができるよう、後悔しないための視点をここで一緒に整理していきましょう。
墓じまいで後悔した体験談とその背景
親族と大モメに…独断で進めたことで関係にヒビが入った
「自分が墓主だから、手続きさえ済ませれば問題ない」と考え、親族に相談せずに墓じまいを進めた結果、激しい反発にあい、長年の信頼関係が壊れてしまったというケースがあります。特に兄弟姉妹との間で「相談がなかった」「勝手に決められて傷ついた」といった感情的な対立に発展することが多く、家族のつながりに深い溝が生じてしまいます。
背景には、供養やお墓に対する価値観の違いがある場合が多く、特に地方に住む親族ほど「お墓は家の象徴」「先祖の居場所をなくすのは申し訳ない」と考える傾向があります。そうした感情を無視して事後報告だけで済ませると、「自分たちの気持ちはないがしろにされた」と受け取られてしまうのです。
また、費用や管理負担を理由に墓じまいを決断した場合でも、十分に説明がなければ「金銭的な都合だけで判断したのか」と誤解される恐れもあります。信頼関係の破綻は修復に時間がかかり、のちの相続や法事にまで影響することもあるため、慎重な対応が求められます。
合祀を選んでしまい、遺骨を戻せずに後悔
「なるべく費用を抑えたかった」「管理が不要だから楽そうだった」といった理由で合祀墓を選び、のちに「遺骨を取り戻せない」と気づいて後悔するケースが後を絶ちません。合祀とは、他のご遺骨と一緒に埋葬する供養方法で、個別の管理がされないため、遺骨の返還や再納骨は基本的にできません。
合祀にしてしまうと、たとえ家族が後から「やっぱり個別に供養したい」と思っても、故人の遺骨だけを取り出すことは不可能です。また、墓標や名前のプレートが用意されない合祀墓も多く、「どこに眠っているか分からないまま」という状態になることもあり、精神的な喪失感に苦しむ人も少なくありません。
さらに、親族や子ども世代が「もっとちゃんとした場所にお墓を作りたかった」と後から思うケースもあり、十分な話し合いや確認をせずに合祀を選んだことが、家族間の後悔やトラブルにつながることもあります。費用だけで判断するのではなく、心のよりどころとしての供養の場について、長期的な視点で考えることが重要です。
想定以上の出費で生活が圧迫された
「お墓の撤去費用が20万円程度で済むと聞いていたのに、最終的には100万円近くかかった」というように、費用面で大きな誤算があったという体験談は非常に多く見受けられます。実際には、墓石の解体撤去費用に加えて、閉眼供養や離檀料、改葬許可申請、納骨先への費用などが重なり、思った以上の出費になりがちです。
また、取り出してみたら想定以上に多くのご遺骨があったというケースでは、1柱あたりで費用が発生する永代供養などでは費用が何倍にも膨れ上がる可能性があります。事前に内部調査や見積もりを取らずに話を進めてしまい、作業の途中で「こんなはずじゃなかった」と気づいても、すでに業者と契約を交わしていて後戻りできない…というケースも少なくありません。
さらに、寺院墓地では離檀料として10万円〜20万円程度を請求されることもあり、これを想定していなかったために資金計画が破綻してしまった人もいます。こうした費用トラブルを避けるには、複数業者の相見積もりや、費用項目の細かい内訳の確認が欠かせません。手間を惜しまず、事前の情報収集を丁寧に行うことが、後悔を防ぐ最大のポイントです。
手続きが複雑で心が折れた
墓じまいにはさまざまな手続きが必要で、その煩雑さに途中で疲れてしまい、後悔したという声もあります。特に多いのは「改葬許可証の申請手続きが思ったよりも手間だった」「どこに何を届け出ればよいのか分からず、時間ばかりかかった」というケースです。
たとえば、現在のお墓がある市区町村で「埋葬証明書」を取得し、新しい納骨先から「受入証明書」を取り寄せ、これらをまとめて役所に提出して「改葬許可証」を得る必要があります。この一連の流れは、特に高齢の方にとっては難解で、「誰かに頼めばよかった」「こんなに手間がかかるならやらなければよかった」と後悔する要因となっています。
さらに、寺院墓地にあるお墓の場合、菩提寺との関係性を大切にしながら丁寧に相談を進めなければならず、「断られたらどうしよう」「話が通じない」といった精神的な負担も大きくなります。こうした心理的ストレスが積み重なることで、途中で投げ出してしまったり、墓じまいそのものを断念してしまう人もいるほどです。
行政手続きや寺院との交渉は、一見些細に見えても、慣れていないと非常に時間と労力を奪われます。そのため、最初から専門家のサポートを受けるか、家族や信頼できる第三者と一緒に進める体制を整えることが、ストレスの軽減につながります。
「もっと早く動けばよかった」と悔やむ声
墓じまいを終えた人の中には、「こんなに気力と体力がいるなら、もっと若いうちにやっておけばよかった」と話す方が少なくありません。実際、終活の一環として70代以降で墓じまいに着手した人の多くが、手続きや調整、寺院や役所とのやりとりに疲弊し、「自分一人ではとても無理だった」と語っています。
さらに、親族が高齢だったり、すでに他界していた場合には、相談すべき相手が不在となり、判断が一人に委ねられてしまうことで、精神的なプレッシャーが増すケースもあります。「もっと元気なうちに、話し合っておくべきだった」「親が健在なときに意向を確認しておけばよかった」といった後悔の声は非常に多いです。
また、時間的にも墓じまいは決して短期間で完結するものではなく、半年から1年程度かかることが一般的です。業者とのやりとり、親族との調整、行政の許可申請、新しい納骨先の確保など、複数の工程が重なるため、思っていたよりも時間とエネルギーが必要になります。

こうした体験談を踏まえると、終活の初期段階から墓じまいを意識し、元気なうちに家族と話し合いを重ねながら計画を立てておくことが、後悔しない最大の対策になります。行動を先延ばしにせず、思い立った今が最良のタイミングだと考えて、早めに準備を始めることが大切です。
墓じまいで後悔しないための7つの具体策
1. 家族・親族との丁寧な話し合いを重ねる
墓じまいを決断する前に、まず家族や親族と時間をかけて話し合うことが不可欠です。たとえ墓主としての権利を持っていても、お墓は家族や一族にとって「心のよりどころ」であるため、誰か一人の独断で進めると、思わぬ反発を受ける可能性があります。
特に地方にルーツのある家庭では、墓を大切にする意識が強く、「お墓をなくす=先祖をないがしろにする」と感じる人もいます。そのため、「なぜ墓じまいを考えているのか」「将来の管理や費用にどんな不安があるのか」などを率直に共有し、気持ちの温度差を埋めていくことが大切です。
話し合いでは、墓守の負担、金銭的な問題、今後の供養の方法など具体的な情報を示すと理解が得やすくなります。
2. 改葬先(納骨先)を早めに決めておく
墓じまいを後悔しやすいポイントのひとつが、改葬先を明確に決めないまま動いてしまうことです。遺骨の移動先が決まっていないと、行政手続きが進まず、遺骨の一時保管場所に困ったり、急いで合祀墓などを選んでしまい後悔する事例もあります。
永代供養墓、納骨堂、樹木葬、手元供養などさまざまな選択肢があるため、それぞれの費用、供養方法、管理体制を比較し、家族の価値観や宗教観に合った方法を早めに選ぶことが重要です。
また、最初から「一部は手元に残し、残りは永代供養する」といった分骨の活用も視野に入れると、心の整理がつきやすくなります。
3. 複数の業者から見積もりを取り比較する
墓じまいは複数の業者による「石材工事」や「遺骨の取り出し・移送」、「行政手続き」などが含まれ、トータルで数十万円〜100万円以上かかることもあります。費用トラブルを避けるためには、必ず2~3社以上から見積もりを取り、内容を比較しましょう。
業者によっては「内部調査」を事前に行ってくれるところもあり、納骨されている遺骨の本数や状態、必要な作業内容が把握できるため、予算のブレを防げます。
また、「指定石材店しか工事できない」とする霊園もあるため、事前に墓地の規約も確認しましょう。安さだけで選ばず、実績や対応力、口コミ評価なども参考にすることが大切です。
4. 菩提寺や霊園との調整を早めに行う
現在の墓地が寺院に属している場合は、墓じまいを決める前に、必ず菩提寺に相談しましょう。「報告」ではなく「相談」として話を持ちかけ、丁寧な姿勢で感謝の意を伝えることが、スムーズな手続きにつながります。
また、寺院によっては「離檀料」を求められることもあります。これは感謝の気持ちとして支払うのが一般的ですが、金額に幅があるため、事前に確認し、予算に含めておく必要があります。
民間霊園でも、管理者とのやりとりや契約解除の手続きが発生することがあるため、早めの連絡・確認が不可欠です。
5. 遺骨の扱いは「分骨」も選択肢にする
合祀や自然葬では、いったん埋葬された遺骨を後から取り出すことは基本的にできません。特に家族にとって思い入れのある故人の遺骨を、完全に手放してしまった後に「やはり残しておけばよかった」と後悔するケースは多く見られます。
そのため、供養の方法に迷いがある場合や家族間で意見が割れている場合は、遺骨の一部を手元供養用に分けておく「分骨」という選択肢が有効です。小さな骨壺やアクセサリー型の遺骨入れなどもあり、気持ちを整理しながら供養を続けることができます。
分骨には自治体への届け出が必要になる場合もあるため、事前に確認し、法的な手続きをしっかりと踏むことが大切です。
6. 必要書類と手続きの流れを事前に整理しておく
墓じまいは、行政・宗教・業者との連携が求められるため、流れを把握しておかないと混乱しがちです。主な流れとしては以下のようになります。
- 家族・親族との合意形成
- 改葬先の決定
- 菩提寺・霊園への相談と許可取得
- 改葬許可申請(埋葬証明書・受入証明書の取得)
- 閉眼供養(魂抜き)
- 墓石の撤去・遺骨の取り出し
- 新たな納骨・供養
特に「改葬許可証」の発行は、すべての準備が整っていなければ役所に申請できないため、遺骨の受け入れ先と調整を済ませておく必要があります。
事前にチェックリストを作り、どの段階で誰が何を行うのかを整理しておくことで、ストレスを大きく減らすことができます。
7. 専門家や無料相談サービスを活用する
墓じまいは人生で何度も経験するものではないため、ほとんどの人が「初めて」で不安を抱えています。ネットで情報を集めても不明点が多く、手続きや費用の見通しが立たないまま進めると、後悔する結果にもなりかねません。

最近では、墓じまい専門の相談窓口や無料相談サービスを提供している業者や自治体、寺院もあります。そういった第三者のアドバイスを受けながら、最適な手順や費用の相場を把握することで、自分たちに合った進め方が見えてきます。
また、行政書士や終活アドバイザーなどの専門家に依頼することで、書類の準備や業者選び、寺院とのやりとりまでサポートを受けることも可能です。特に高齢の方や、親族との調整が難しい方にとっては、大きな助けとなります。
平日10時~18時
墓じまいに関するQ&A(よくある疑問と不安)
Q. 親族が納得してくれないときはどうすればいい?
A. 墓じまいは墓主の判断で進められますが、家族や親族の理解なしに進めると、後々のトラブルや感情的なしこりを残しかねません。まずは「なぜ墓じまいを考えているのか」を具体的に伝え、管理の負担や今後の供養方法など、現実的な問題を丁寧に説明しましょう。それでも反対意見が強い場合は、墓守の役割を引き継いでもらう選択肢や、改葬せずに維持する代案を一緒に検討するのも方法です。時間をかけて話し合いを重ねることが、信頼関係を保つ鍵になります。
Q. 合祀にすると遺骨は取り戻せないって本当?
A. はい、基本的に合祀(ごうし)にされたご遺骨は、他の方の遺骨と混ざった状態で埋葬されるため、個別に取り出すことはできません。「あとから家族で改葬し直したい」「個別の墓に移したい」と思っても、それは叶いません。費用が安く管理が不要という理由だけで合祀を選ぶと、後から強い喪失感に襲われる方もいます。迷いがある場合は、遺骨の一部を分骨して手元に残しておくなど、後悔しないための方法も検討しましょう。
Q. 離檀料(りだんりょう)って絶対に払わないといけないの?
A. 離檀料は法律で定められた義務ではありませんが、菩提寺に対する「これまでの供養への感謝の気持ち」として支払うのが一般的です。寺院側から高額な請求を受けた場合でも、一方的に拒否するのではなく、これまでのお付き合いの経緯や家庭の事情を丁寧に伝え、納得できる金額を相談することが大切です。トラブルを避けるためにも、早い段階で菩提寺に「相談」という形で話を持ちかけると、穏やかな対応につながります。
Q. 自分だけで手続きを進めても大丈夫?
A. 手続きそのものは可能ですが、墓じまいには改葬許可証の取得や墓地管理者・寺院との調整、業者選びなど、多くの工程があります。慣れていない方が一人で進めると、手続きの漏れやトラブルが起きやすく、精神的にも大きな負担になります。高齢の方や忙しいご家族の場合は、行政書士や終活支援の専門業者に相談したり、無料相談窓口を利用することで、スムーズに進められます。不安がある場合は、最初から第三者の力を借りるのが安心です。
Q. お墓が遠方にあるのですが、それでも墓じまいはできますか?
A. はい、遠方にあっても墓じまいは可能です。ただし、現地での立ち会いが必要な場面もあるため、スケジュール調整や現地確認の段取りには注意が必要です。最近では、現地調査から行政手続き、解体工事までワンストップで代行してくれる業者も増えており、遠方在住の方でも安心して依頼できます。親族が現地にいない場合でも、代理人を立てて進める方法もありますので、事前に相談しておきましょう。
Q. 取り出した遺骨はどこに納めればいいの?
A. 納骨先には、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・自宅での手元供養など、さまざまな選択肢があります。それぞれにメリットと注意点があるため、ご自身や家族の希望、宗教的な考え、費用面を踏まえて検討することが大切です。特に永代供養は、管理の手間がかからず、近年人気が高まっています。ただし、どの納骨先でも受け入れには「受入証明書」が必要なため、墓じまいの手続きを始める前に決めておくとスムーズです。
Q. 分骨ってどんなこと?法律的に問題ないの?
A. 分骨とは、遺骨の一部を分けて、別の場所で供養する方法です。たとえば、一部を手元供養として自宅に残し、残りは永代供養するなど、柔軟な対応が可能になります。墓じまい後に「遺骨をすべて手放すのは寂しい」と感じる場合、分骨は後悔を避ける有効な手段になります。法律上は問題ありませんが、自治体によっては「分骨証明書」などの手続きが必要になるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ|後悔しない墓じまいのために大切なこと
墓じまいで後悔するケースの多くは、「情報不足」「準備不足」「思い込み」の3つが重なって起きています。どんなに正しい判断であっても、家族や親族の理解が得られなければ心にしこりが残りますし、納骨先や費用を軽視すれば、後から取り返しのつかない選択だったと気づくこともあります。
まず何より大切なのは、独断で決めないことです。お墓は個人のものではなく、家族や一族の心の拠り所であり、世代を超えて守ってきた象徴でもあります。「どうして墓じまいを考えるのか」「今後どんな供養を望んでいるのか」を丁寧に伝え、家族で気持ちを共有する時間をしっかり持ちましょう。
次に、納骨先や手続き、費用については、十分なリサーチと比較が不可欠です。合祀や樹木葬、手元供養などの選択肢はそれぞれメリットと注意点があります。価格の安さだけで判断せず、自分たちが後悔しないかどうか、将来の家族にも配慮した選び方が求められます。
そしてもうひとつ大切なのは、「早めの行動」です。体力や判断力があるうちに動けば、親族との話し合いや業者との調整、書類の準備にも余裕をもって対応できます。先延ばしにすればするほど、心身への負担は増え、判断力も鈍ってしまいます。

墓じまいは、一度きりの大きな決断です。不安や迷いがあるのは当然ですが、だからこそ焦らず、周囲と相談しながら慎重に進めていくことが、後悔を防ぐ最大のポイントです。必要に応じて専門家の力も借りながら、「やってよかった」と思える未来のために、納得のいく選択をしていきましょう。
平日10時~18時