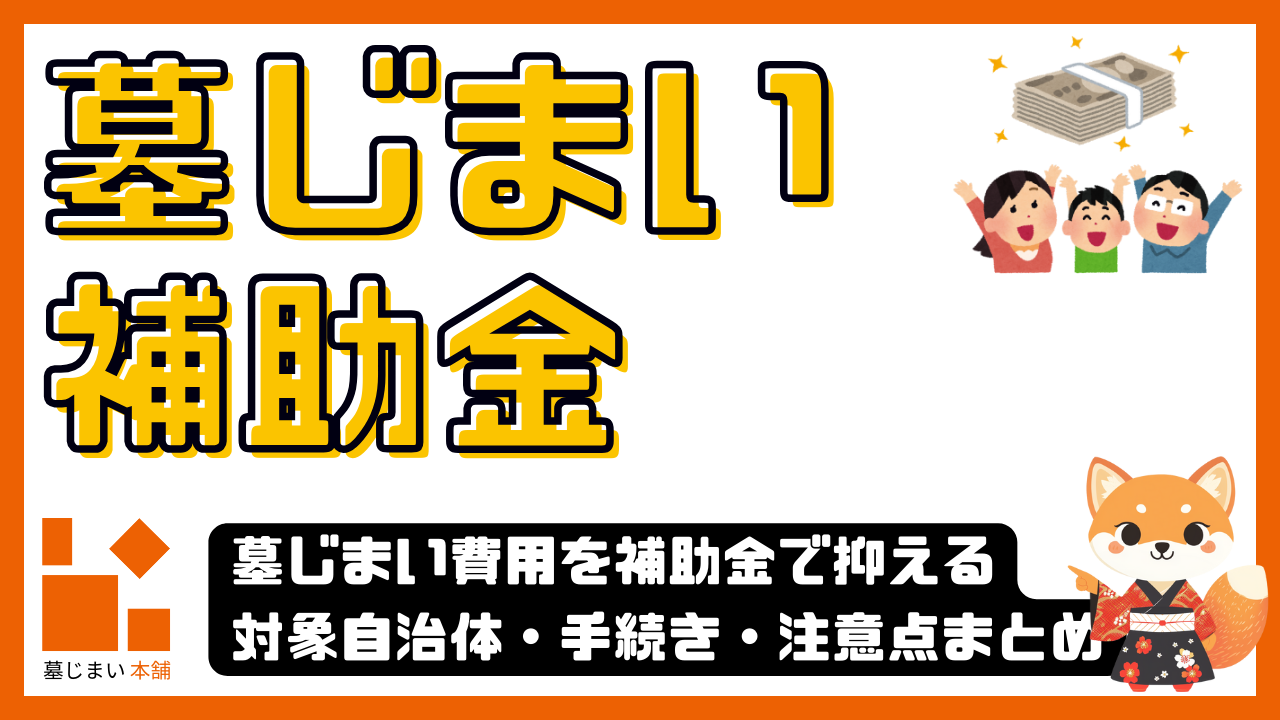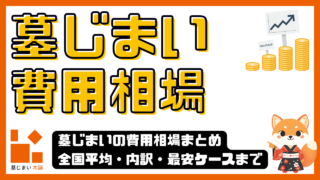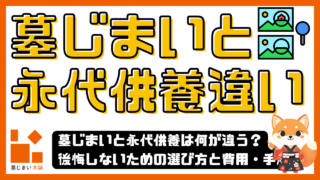本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいに補助金は出る?仕組みをわかりやすく解説
墓じまいに対して補助金が出るかどうかは、国の制度ではなく、お墓がある自治体ごとの判断によって異なります。そのため、全国一律で「誰でも補助金がもらえる」というわけではありません。
そもそも墓じまいの補助金とは、自治体が地域の墓地の無縁化を防ぐことを目的として、お墓の返還や墓石の撤去にかかる費用の一部を支援する制度です。
無縁墓が増えると、管理が行き届かず景観や治安の悪化につながる恐れがあるため、自治体としても早めの墓じまいを後押ししたいという背景があります。
この補助金は、主に市営墓地や公営霊園などの公共管理下にある墓所に対して支給されることが多く、寺院墓地や民営霊園は対象外となる場合が一般的です。また、制度の有無に加えて、補助対象となる条件や助成金額、申請に必要な書類、申請のタイミングなども自治体ごとに異なります。
例えば、千葉県市川市では原状回復費用として最大44万円、群馬県太田市では墓石撤去にかかる費用のうち20万円を上限に補助が受けられる制度があります。一方で、そもそも補助金制度が存在しない自治体も多く、調べずに進めると補助が受けられないケースもあります。
注意点として、補助金はあらかじめ申請しておく必要があるのが一般的です。多くの自治体では、墓じまいの工事完了後に「領収書」や「改葬許可証」などを添えて申請し、審査を経たのちに補助金が支給されます。つまり、いったんは全額自己負担となるため、資金計画を立てておくことが大切です。
補助金の申請には期限が設けられている場合や、年度単位で受付を締め切る自治体もあります。うっかり申請のタイミングを逃すと補助が受けられなくなるため、事前にお墓がある自治体の公式サイトや窓口で、最新の情報を確認しておくようにしましょう。
最新墓じまいの補助金がもらえる自治体一覧
現在、全国で墓じまいに対して補助金を交付している自治体はごく一部に限られています。主に市営墓地や公営霊園に対して補助が出るケースが多く、補助の対象となる条件や支給額、助成内容は自治体によって大きく異なります。以下に、2025年時点で補助金制度を設けている主な自治体を紹介します。
| 自治体名 | 対象となる墓地 | 支給内容 | 上限金額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県市川市 | 市川市霊園一般墓地 | 墓地使用料の一部返還・原状回復費用の助成 | 最大44万円 | 管理困難・無縁化の不安があること |
| 千葉県浦安市 | 浦安市墓地公園 | 墓石撤去費の助成、合葬式墓地使用料無料 | 撤去費最大15万円 | 墓所返還と改葬を伴うこと |
| 群馬県太田市 | 八王子山公園墓地 | 墓石撤去費用の助成 | 最大20万円 | 管理料に滞納がないこと |
| 岡山県玉野市 | 玉野市霊園 | 使用料の還付 | 使用状況により10〜50%還付 | 原状回復後の申請が必要 |
| 大阪府泉大津市 | 公園墓地 | 永代使用料の一部還付 | 使用年数により最大50% | 墓地の原状回復が条件 |
| 大阪府岸和田市 | 市営墓苑 | 墓地使用料の還付 | 使用年数や状況に応じて | 囲障物撤去などの条件あり |
| 東京都 | 都立霊園(青山・谷中ほか) | 原状回復義務の免除 | 金銭支給なし | 合葬式墓地への改葬が前提 |
| 千葉県市原市 | 市原市海保墓園 | 合葬墓の無料利用 | 利用料免除 | 墓地返還と焼骨の移動が条件 |
| 茨城県水戸市 | 水戸市公園墓地 | 返還協力金の交付 | 最大29万円超(区画により異なる) | 未納がなく納骨歴がない場合 |
これらの自治体はいずれも、無縁墓の増加防止や墓地の有効利用を目的に補助制度を設けています。
ただし、制度は予算や年度ごとに変更される可能性があるため、最新情報は必ず自治体の公式サイトまたは窓口で確認してください。
また、表にない地域でも今後新たに制度を設ける動きがあるため、居住地やお墓の所在地が上記以外の場合でも諦めずに情報収集を行うことをおすすめします。補助金制度の有無だけでなく、申請期間や必要書類の条件なども事前に確認しておくことで、スムーズな手続きにつながります。
補助金の対象になる費用・もらえる金額の目安
墓じまいにかかる費用のうち、補助金の対象として最も一般的なのが「墓石の解体・撤去費用」です。多くの自治体では、無縁墓の増加を防ぐためにこの部分の費用を支援しています。対象範囲は自治体ごとに異なりますが、原則として墓石や外柵の撤去、墓所の整地(原状回復)に関わる工事費が補助対象となります。
実際に支給される金額は自治体によって差がありますが、おおむね10万円~20万円前後が目安です。例えば、千葉県市川市では区画の広さによって最大44万円まで支給されるケースもある一方、群馬県太田市では最大20万円までの補助にとどまります。また、千葉県浦安市では15万円を上限に撤去費用の一部が支給されるなど、地域によって補助額の上限や条件に大きな違いがあります。
補助金の受け取り時期についても注意が必要です。多くの自治体では、墓じまいの工事がすべて完了し、支払いが済んだあとに申請を行う「後払い方式」を採用しています。そのため、一時的にでも全額を立て替えられるよう、資金の準備が求められます。補助金申請時には、領収書や工事の完了報告書などの提出が必要になるため、これらの書類は必ず保管しておきましょう。
また、補助金の対象になる墓地の種類にも制限があります。多くの場合、市営や公営の墓地が対象となり、寺院墓地や民営霊園は補助の対象外となることが一般的です。補助対象かどうかは、墓地の所在地自治体に直接確認することが確実です。

補助金の金額だけに目を向けるのではなく、「何に対して」「どの程度まで」「どのタイミングで」支給されるのかを把握しておくことが大切です。条件や対象範囲を正しく理解し、無理のない計画で墓じまいを進めましょう。
墓じまいの補助金をもらうための手続きの流れ
墓じまいで補助金を受け取るには、各自治体が定めた手順に沿って申請する必要があります。ここでは、一般的な手続きの流れを解説します。自治体ごとに若干異なる点もあるため、具体的には必ずお墓のある自治体の公式サイトまたは窓口で確認してください。
1. 自治体の制度を調べる
まずは、お墓がある場所を管轄する自治体に、墓じまいに関する補助金制度があるかを調べましょう。制度が設けられていない自治体も多いため、補助金の有無を早めに確認することが重要です。調査には自治体の公式サイトや「スマート補助金」などの検索ポータルを活用すると便利です。
2. 必要書類を準備する
補助金の申請には、以下のような書類が必要になることが一般的です。申請の段階とタイミングによって提出書類が異なるため、整理しておきましょう。
- 補助金申請書(自治体指定の様式)
- 墓じまい工事の見積書
- 改葬許可証(改葬先が決まっている場合)
- 墓地使用者の住民票や戸籍謄本
- 墓地の写真(現況確認のため)
- 墓所の使用許可証のコピー
- 印鑑証明や委任状(代理申請の場合)
なお、自治体によってはこれら以外の書類を求められるケースもあります。申請前にチェックリストなどを確認して漏れがないようにしましょう。
3. 事前申請を行う
補助金制度があることを確認し、必要書類をそろえたら、まずは自治体に「補助金交付申請書」を提出します。この時点で見積書や改葬先の情報が求められることが多いため、墓じまい業者や改葬先の手配も同時に進めておくとスムーズです。
一部の自治体では、事前審査があり、補助金が正式に交付されるかどうかの通知が後日届く仕組みとなっています。
4. 墓じまい工事を実施する
事前申請が受理されたら、業者と日程を調整し、墓石の解体・撤去工事を行います。工事の様子を記録した写真や、撤去後の原状回復を証明する資料を用意しておくと、申請時に役立ちます。
なお、補助金は「工事完了後」の支給となるため、この段階では費用をいったん全額自己負担する必要があります。事前に資金の準備をしておきましょう。
5. 完了報告と補助金交付申請
工事が完了したら、完了報告書とともに補助金の交付を申請します。ここで必要になる書類は以下のようなものです。
- 工事完了報告書
- 工事業者が発行した領収書(原本)
- 改葬許可証の写し
- 工事完了後の現地写真
- 補助金交付請求書
書類が揃い次第、自治体に提出し、審査を経て補助金が指定口座に振り込まれる流れとなります。自治体によっては、口座情報や振込依頼書の提出も求められます。
6. 注意すべき申請時期と有効期限
多くの自治体では、補助金の申請が「通年受付」ではなく、年度単位で予算が決まっている場合があります。そのため、希望する時期に申請ができないこともあるため注意が必要です。
また、事前申請から完了報告までの期間に期限が設けられている自治体もあります。申請から交付までが数か月かかることもあるため、余裕をもってスケジュールを立てておくことが大切です。

このように、墓じまいの補助金をもらうには、事前の準備と書類の整備が欠かせません。自治体の制度に合わせて正確に手続きを行えば、費用の負担を大きく軽減することができます。手続きが煩雑に感じられる場合は、墓じまい業者や終活アドバイザーに相談して、代行やサポートを依頼することも検討しましょう。
補助金以外に費用を抑える方法
補助金の対象外だったり、申請が間に合わなかったりする場合でも、墓じまいの費用を抑える方法はいくつかあります。ここでは、実際に活用されている代表的な方法を紹介します。補助金が使えないケースでも、工夫次第で負担を減らすことは可能です。
複数業者の相見積もりをとる
墓石の撤去費用は、業者によって価格差が大きく出る傾向があります。必ず複数の業者に見積もりを依頼し、金額だけでなく作業内容や追加費用の有無も比較しましょう。対応エリアや実績、口コミ評価も確認すると安心です。見積もりは無料のところが多く、比較することで適正価格が見えてきます。
費用のかからない改葬先を選ぶ
墓じまい後の改葬先によっても、総費用は大きく変わります。一般的なお墓への改葬は高額になりがちですが、以下のような方法なら費用を抑えることが可能です。
- 合祀型の永代供養墓:他人の遺骨と一緒に埋葬される形式で、費用は1万円~5万円ほどから
- 樹木葬:墓石を使わず樹木の下に埋葬するスタイル。10万円前後で収まることもあります
- 納骨堂:屋内型の供養施設で、年間利用料制と永代契約制があり、比較的安価なプランもあります
- 海洋散骨:遺骨を粉末状にして海へ撒く方法で、数万円から可能です
ただし、宗教的な考え方や家族の意向に配慮することも重要です。
家族や親族で費用を分担する
お墓を引き継いできた背景がある場合、親族で費用を分担することも一つの方法です。「両親や祖父母のお墓なので、兄弟で負担し合いたい」「遠方で通えないから、墓じまいに賛成」など、協力が得られるケースもあります。費用の全額を一人で負担するより、負担は大きく軽減されます。
寺院墓地なら離檀料を相談する
寺院墓地を墓じまいする際は、これまでの感謝の気持ちとして「離檀料」が必要とされることがあります。しかし、離檀料には明確な相場がなく、寺院によって金額に幅があります。あらかじめ誠意をもって事情を説明し、無理のない範囲で支払いができるよう相談することで、負担を軽くできる可能性があります。
メモリアルローンの活用
もし手元に資金の余裕がない場合は、金融機関の「メモリアルローン」を利用するという選択肢もあります。これは葬儀やお墓関連の費用に特化したローンで、金利や返済期間は金融機関によって異なります。補助金の支給が後払いになる場合など、一時的に立て替えが必要な場面でも役立ちます。

これらの方法を組み合わせることで、補助金が受けられない場合でも費用の負担を大きく抑えることができます。焦らずに情報を集め、できるだけ多くの選択肢を検討することが、納得のいく墓じまいにつながります。
補助金制度があるか調べる方法
墓じまいの補助金制度は全国一律ではなく、お墓の所在地を管轄する自治体ごとに設けられているため、制度の有無や内容を調べることが第一歩となります。ここでは、正確に補助金制度の有無を確認するための具体的な方法を紹介します。
自治体の公式サイトを確認する
最も信頼性の高い情報源は、該当する市区町村の公式ホームページです。「〇〇市 墓じまい 補助金」や「〇〇市 墓地返還 補助制度」などのキーワードで検索すると、対象となる制度の詳細ページが見つかる場合があります。制度がある場合、申請条件・補助額・必要書類などが掲載されています。
検索のコツとして、「墓じまい」という言葉が使われていない場合もあるため、「改葬」「墓地返還」「霊園制度」「原状回復費助成」などの表現も併せて調べると、該当ページが見つかりやすくなります。
自治体の窓口に直接問い合わせる
公式サイトで情報が見つからない場合や、掲載内容が古い可能性があるときは、市役所や町役場などの担当窓口に電話で直接問い合わせるのが確実です。お墓の管理が霊園課や市民課、生活環境課など複数の部署に分かれていることもあるため、「墓じまいに関する補助金制度について教えてください」と具体的に伝えると、担当部署にスムーズにつながります。
自治体によっては、書類を郵送で取り寄せる必要がある場合や、窓口での事前相談が必須なケースもあるため、余裕を持って準備しましょう。
補助金ポータルサイトを活用する
墓じまいに関する補助金制度を一覧で探せるポータルサイトもあります。なかでも「スマート補助金」は、全国の自治体が実施しているさまざまな補助制度を横断的に検索できる便利なサービスです。
「墓じまい」「改葬」「墓石撤去」などのキーワードを入力するだけで、対象地域の制度を調べることができます。各自治体の公式ページへのリンクも掲載されているため、そのまま詳細を確認することも可能です。
ただし、ポータルサイトはあくまで「補助制度があるかの目安」として使い、最新情報は必ず自治体の公式発表を確認するようにしましょう。
墓地所在地と居住地が異なる場合の注意点
補助金制度の対象となるのは、多くの場合「お墓の所在地の自治体」です。たとえ申請者本人が別の地域に住んでいても、補助金の可否は墓地のある地域の制度によって決まります。
たとえば「自分は東京都に住んでいるが、墓地は千葉県市川市にある」という場合、市川市の制度が適用されます。居住地の役所に問い合わせても正確な情報が得られないため、必ず墓地がある地域の自治体で確認しましょう。

このように、補助金の有無や内容を調べるには、信頼できる情報源から丁寧に確認することが大切です。制度があるかないかを正しく把握することで、無駄な手間や申請ミスを防ぎ、費用負担の軽減につなげることができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 補助金がもらえるのはどんな墓地ですか?
多くの自治体では、市営墓地や公営霊園など、自治体が管理している墓地が補助金の対象となります。寺院墓地や民営霊園は対象外となるケースが多いため、まずはお墓の所在地の自治体に問い合わせて確認しましょう。
Q. 補助金は申請すれば必ずもらえるのですか?
いいえ、補助金制度がある自治体でも、申請条件を満たしていない場合は交付されません。たとえば「管理料の滞納がないこと」や「墓じまい後に合葬墓へ改葬すること」など、自治体ごとに細かい条件が決められています。事前に詳細を確認することが大切です。
Q. 寺院のお墓でも補助金が出ることはありますか?
基本的には寺院墓地は対象外ですが、まれに自治体によっては個別対応しているケースもあります。また、墓地の返還や整備に関して別の支援制度がある場合もありますので、お寺と自治体の両方に相談してみるのが良いでしょう。
Q. 補助金だけでは足りない場合はどうすれば?
補助金の上限額は一般的に10万円〜20万円前後です。墓じまいの総費用には届かないケースも多いため、費用を抑えるために複数業者での相見積もりや、安価な改葬先(合祀墓、樹木葬など)の選択、親族との費用分担、メモリアルローンの活用などを検討しましょう。
Q. 墓じまいをしたあとに補助金の申請はできますか?
多くの自治体では、墓じまいの前に「補助金申請」を行うことが必須です。事後申請が認められない場合がほとんどのため、工事や撤去を行う前に、申請のタイミングや流れを自治体に確認してください。
Q. 補助金の申請は代理人でもできますか?
可能な自治体もありますが、委任状や本人確認書類の提出が必要になることがあります。高齢の親御さんの代わりに手続きを行う場合は、事前に代理申請が認められているかどうかを確認し、必要書類をそろえましょう。
Q. 無縁墓になるとどうなるのですか?
お墓を継ぐ人がいないまま長期間放置されると、「無縁墓」として認定される可能性があります。認定されると、管理者(自治体や霊園)によって撤去・合祀されることがあります。手続きを経ずに撤去されるため、故人を敬う形での供養ができないことも。そうなる前に、墓じまいを含めた対策を検討することが望まれます。
Q. どのくらい前から準備を始めればいいですか?
補助金の申請から支給までは数か月かかる場合もあります。また、自治体によっては申請期間が限られていたり、予算がなくなり次第受付終了となる場合もあるため、遅くとも墓じまいの半年前から情報収集と準備を始めるのが安心です。
まとめ|まずはお墓の所在地の自治体に確認しよう
墓じまいにかかる費用は決して小さくありませんが、自治体の補助金制度を上手に活用することで、負担を軽減できる可能性があります。とはいえ、補助金の制度は全国共通ではなく、あくまでもお墓がある自治体ごとの独自制度です。補助の有無や金額、条件、申請時期もそれぞれ異なるため、「どこに問い合わせればいいのか分からない」と感じている方も多いかもしれません。
このようなときは、まずはお墓がある市区町村の役所に問い合わせてみてください。「墓じまいに関する補助制度について知りたい」と伝えれば、担当部署へつないでもらえるはずです。役所のウェブサイトにも情報が掲載されていることが多く、「〇〇市 墓じまい 補助金」などのキーワードで検索することで、該当ページを見つけやすくなります。
補助金の制度がない地域であっても、費用の一部を軽減できる他の制度や、墓地使用料の還付制度などが用意されている場合があります。思い込みで「うちは関係ない」と諦めてしまわず、必ずお墓のある自治体に確認することが重要です。
また、補助金の申請には事前手続きが必要となるため、工事を始めてしまってからでは間に合わないケースもあります。準備を始めたら、できるだけ早めに確認・申請を行いましょう。

家族にとって大切なお墓の整理を、納得のいく形で進めるためにも、情報収集と相談の第一歩を踏み出すことが、後悔のない墓じまいにつながります。
平日10時~18時