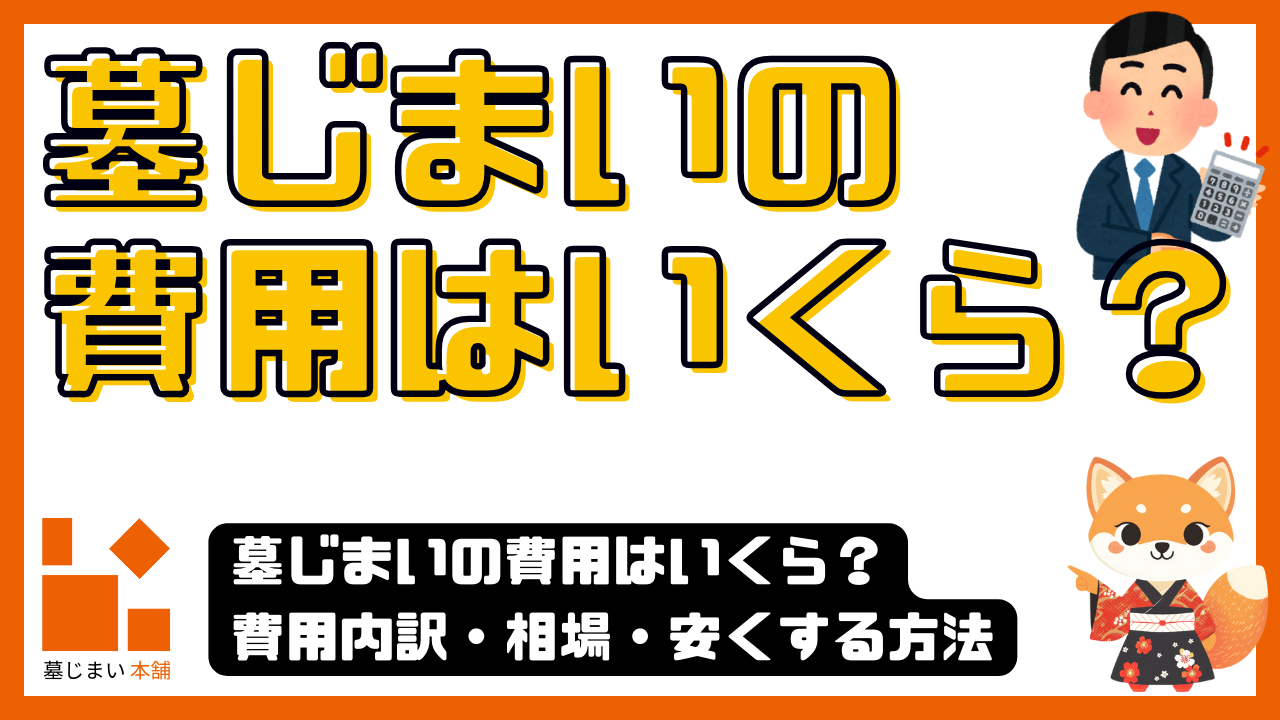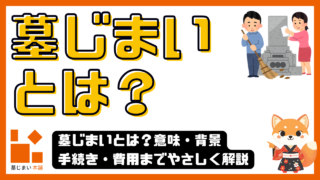本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいにかかる費用の全体像
墓じまいにかかる費用は、一般的に30万円〜150万円ほどが相場とされていますが、実際の金額は人それぞれ大きく異なります。
これは、現在のお墓の立地や状態、ご遺骨の数、移す先の納骨先の種類によって必要な作業やサービス内容が変わるためです。
まず理解しておきたいのは、墓じまいは単なる「お墓の撤去」ではないということです。墓石を解体して更地に戻すだけでなく、閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出して新たな納骨先に移すまでを含めて、はじめて墓じまいが完了します。このため、石材店だけでなく、寺院や行政、新しい納骨先など、複数の関係先に対して費用が発生します。
たとえば、墓石の解体工事は1㎡あたり10万円前後が目安となり、お墓が広い場合や、道幅が狭く機械が入らない場所での工事では費用が高くなることがあります。また、寺院に依頼する閉眼供養(魂抜き)の法要にはお布施が必要で、金額の目安は3万円〜10万円です。お墓が寺院墓地にある場合は、檀家を離れるための「離檀料」がかかるケースもあり、これは任意とはいえ5万円〜20万円ほど包むのが通例です。
さらに、行政手続きも避けては通れません。改葬(お墓の引越し)には、役所に「改葬許可証」の申請が必要で、これに伴って取得する各種証明書にも数百円〜数千円の手数料がかかります。ご遺骨が複数ある場合は、その分手続きも費用も増えます。
最後に、新しい納骨先をどうするかによって費用は大きく変わります。たとえば、伝統的な一般墓を新たに建てる場合は100万円以上かかることもありますが、合祀墓や永代供養墓であれば5万円〜30万円程度で抑えることも可能です。手元供養や散骨といった選択肢も増えており、それぞれにかかる費用やメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。
墓じまいの費用は、「撤去費用」「儀式・寺院関係費用」「行政手続き費用」「新しい納骨先の費用」の大きく4つに分かれます。人によっては最低限の30万円程度で済む場合もありますし、複数の遺骨を改葬し新しい墓を建てる場合は、100万円を超えることもあります。

このように、墓じまいの費用には大きな幅があり、ご自身やご家族の状況に合わせた選択が必要です。無理のない費用計画を立てるためには、複数の石材店や納骨先から見積もりを取り、比較検討することが第一歩です。
平日10時~18時
費用の内訳|何にどれくらいかかるのか?
墓じまいにかかる費用は、主に以下の4つに分類できます。
それぞれの項目で発生する金額の目安と、費用が高くなるケースについて詳しく見ていきましょう。
1. お墓の撤去費用(20万円〜50万円程度)
墓石を解体し、更地に戻すための費用です。多くの場合、石材店に依頼します。
- 墓石の解体・処分費用:1㎡あたり10万円前後が相場で、墓地の広さや石の量によって変動します。
- ご遺骨の取り出し作業費:3万円〜5万円ほど。ご遺骨が劣化している場合は洗浄や乾燥などの処理費が別途かかることもあります。
- 立地による追加費用:墓地が山奥にある、通路が狭く重機が入れないなどの場合、追加で数万円〜十数万円が必要になるケースがあります。
石材店によって見積もり額に差が出るため、複数社に相見積もりを取ることが大切です。
2. 閉眼供養・離檀料などの寺院関連費用(3万円〜30万円程度)
寺院墓地の場合、墓じまいには宗教的な儀式やお寺との関係整理も必要です。
- 閉眼供養(魂抜き)のお布施:3万円〜10万円が一般的です。
- 離檀料:寺院との檀家契約を解除する際の費用。法的義務はないものの、5万円〜20万円ほどを包むのが通例です。
- その他の経費:僧侶の出張にかかる御車代(3千円〜5千円)、お供え物などを別途用意することもあります。
寺院により金額の考え方が異なるため、事前に確認・相談しておくと安心です。
3. 行政手続き費用(数百円〜1,500円程度)
ご遺骨を他の場所に移すには「改葬許可証」が必要です。以下の書類取得に費用が発生します。
- 埋葬証明書(既存墓地で取得)
- 受入証明書(新しい納骨先で取得)
- 改葬許可申請書(役所で提出)
1通あたり300円〜1,500円程度。ご遺骨が複数ある場合、それぞれに書類が必要です。
4. 新しい納骨先に関する費用(5万円〜200万円以上)
墓じまい後、ご遺骨をどこへ納めるかによって費用は大きく変動します。
| 納骨先の種類 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合祀墓 | 5万円〜30万円 | 他人の遺骨と一緒に埋葬される。費用は最も安いが、遺骨は戻せない |
| 永代供養墓(個別型) | 30万円〜150万円 | 個別に供養され、管理費不要。一定年数後に合祀されることも |
| 樹木葬 | 20万円〜80万円 | 自然葬として人気。埋葬後の遺骨の取り出し不可が多い |
| 納骨堂 | 10万円〜150万円 | 屋内施設で天候に左右されない。交通アクセスが良い場所が多い |
| 散骨 | 5万円〜30万円 | 海や山へ遺骨を撒く。供養後の維持費は不要。宗教行事なし |
| 一般墓(再建) | 100万円〜200万円以上 | 伝統的なお墓。費用は高めだが、代々継承できる |
- 開眼供養(魂入れ)のお布施:新たなお墓にご遺骨を納める際には、開眼供養を行うのが一般的で、3万円〜5万円程度の費用がかかります。

それぞれの納骨先にはメリット・デメリットがあります。費用だけでなく、ご家族や親族の想いも含めて慎重に選びましょう。
費用の内訳を把握しておくことで、全体の予算感を明確にできます。特に新しい納骨先の選択が総額に大きく影響するため、家族でよく話し合い、事前に情報収集をしておくことが後悔のない墓じまいにつながります。
墓じまいの費用は誰が払うのか?
墓じまいにかかる費用は決して少額ではなく、数十万円から場合によっては100万円を超えることもあります。そのため、「誰がその費用を負担すべきか」で悩まれる方も少なくありません。法律上の明確なルールは存在しませんが、実際の現場ではいくつかのパターンが見られます。
以下に代表的な支払いパターンと注意点を紹介します。
お墓の承継者が支払うケースが一般的
最も多いのが、お墓の承継者が墓じまい費用を負担するケースです。民法第897条では、祭祀に関する財産(お墓や仏壇など)は、原則として承継者が管理するとされています。お墓の所有者として名義を引き継いだ方が、管理と合わせて墓じまいの手続きも担うことが一般的です。
長男・長女が承継者になるケースが多く、結果としてその方が費用を負担するという流れになりますが、これはあくまで「慣例」であり、必ずしも全額を支払わなければならないわけではありません。
家族や兄弟姉妹で費用を分担するケースも
お墓を先祖代々で守ってきた場合、「一人で全部負担するのは難しい」と感じるのは当然です。そのため、兄弟姉妹や近しい親族で協力して費用を分担するケースも多く見られます。
分担割合に決まりはありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、以下のようなポイントに注意して話し合いを進めるとスムーズです。
- 誰がどれだけ出すかを明確にしておく
- 書面に残すとさらに安心
- 墓じまいの目的や必要性を事前に共有しておく
感情的な対立が起きやすい場面でもあるため、第三者(専門業者や行政書士など)を交えて話し合いを進めるのも一つの方法です。
生前に本人が費用を用意していたケース
近年では終活の一環として、ご自身が元気なうちに墓じまいを決断し、費用を準備されている方も増えています。葬儀費用とあわせて、墓じまい資金を別口座に用意しておいたり、遺言やエンディングノートにその意向を残しておくことで、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
すでに故人が亡くなられている場合でも、預貯金や保険の中に費用の用意が含まれているケースもあるため、相続人でしっかり確認しておくことが大切です。
トラブルを防ぐための心がけ
墓じまいは家系の供養や思い出が関わる繊細な問題でもあるため、「費用の負担」をきっかけに親族間で対立が起きることもあります。スムーズに進めるためには、以下のような点を意識することが重要です。
- 早めに家族全体で話し合うこと
- 費用だけでなく、供養の方法や納骨先も含めて共有すること
- 必要に応じて第三者の専門家に相談すること

誰が払うかという問題は、単にお金の話だけでなく、これからのお墓のあり方や家族としての考え方も反映される問題です。一人で抱え込まず、家族全員が納得できる形での墓じまいを目指しましょう。
墓じまい費用を安く抑える方法
墓じまいは、まとまった費用が必要になるため、できる限り出費を抑えたいと考える方も多いでしょう。特に「終活」の一環として、ご自身やご家族の負担を軽減したいとお考えの場合、費用の見直しや工夫は非常に有効です。ここでは、実際に費用を抑えるためにできる具体的な方法をご紹介します。
複数の石材店に相見積もりを取る
もっとも基本的で効果的なのが「相見積もり」です。石材店によって、墓石の撤去費用や工事費の算出基準が異なるため、1社だけの見積もりで決めてしまうと、必要以上に高額な金額を支払うことになりかねません。
複数の業者に同じ条件で見積もりを依頼し、比較することで、無駄な出費を避けられるだけでなく、対応の丁寧さや実績なども把握できます。費用だけでなく「自治体の手続き代行」や「納骨先の紹介」などのサービス内容も含めて総合的に判断しましょう。
墓石の撤去作業における条件を確認する
撤去費用は、墓地の立地条件によって大きく変動します。たとえば、以下のような条件に該当する場合、追加費用が発生することがあります。
- 墓地が山間部や離島などのアクセスが悪い場所にある
- 通路が狭く、重機が入らない
- 一区画内に複数の墓石が建てられている
これらの条件に該当する場合は、できるだけ工事がしやすい日程を業者と調整するなど、費用削減につながる交渉を行うことも検討してみましょう。
納骨先の選び方を見直す
墓じまいの費用で大きな割合を占めるのが、取り出したご遺骨の納骨先の費用です。選ぶ場所によって金額に大きな差があるため、ここを見直すことで全体の出費を大幅に抑えられる可能性があります。
| 納骨先の種類 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合祀墓 | 5万円〜30万円 | 他人の遺骨と合同埋葬。費用は安いが取り出し不可 |
| 散骨 | 5万円〜20万円 | 海や山にご遺骨を撒く方法。維持費不要 |
| 手元供養 | 1万円〜10万円 | 小型の骨壷やペンダントに納めて自宅で保管 |
| 永代供養墓(合祀型) | 10万円〜40万円 | 管理費不要で費用が安価。個別管理ではない |
ただし、費用が安い納骨方法には、それぞれデメリットもあります。たとえば合祀墓は一度納骨するとご遺骨を取り出せませんし、散骨は法的な配慮や親族の同意が必要になることもあります。ご家族でよく話し合い、将来的な後悔がないように慎重に選びましょう。
寺院との費用交渉を検討する
閉眼供養や離檀料など、寺院に支払う費用も無視できません。これらは明確な料金表があるわけではなく、あくまで「お気持ち」として包むケースが多いため、住職と丁寧に相談することで費用を抑えられることもあります。
たとえば、経済的事情を正直に話し、「閉眼供養のお布施を相談できないか」「離檀料の支払い方法を分割にできないか」といった交渉をしてみると、理解を示してくれる場合もあります。これまでの感謝の気持ちを伝えた上で、誠実に話すことが大切です。
補助金制度やローンを検討する
一部の自治体では、墓じまいに対して補助金を支給している場合があります。特に「無縁仏の増加対策」として、墓石の撤去費用の一部を負担してくれるケースがあるため、お墓のある地域の役所に問い合わせてみることをおすすめします。
また、どうしても一括での支払いが難しい場合は、石材店や霊園が提携している「メモリアルローン」を利用する選択肢もあります。分割払いが可能になることで、経済的な負担を軽減できます。

墓じまいの費用は、工夫次第で大きく抑えることができます。ただし、「安ければ良い」という考えだけで選ぶと、納骨先に不満が残ったり、親族とのトラブルに発展することもあるため、事前の話し合いと情報収集を十分に行いましょう。信頼できる専門業者や相談窓口を活用することで、費用面だけでなく心の負担も軽減できます。
費用が払えないときの対処法
墓じまいにかかる費用は決して安いものではなく、平均でも30万円以上、場合によっては100万円を超えるケースもあります。そのため、「やりたくても費用が払えない」「他に優先すべき出費がある」と悩まれる方も少なくありません。しかし、諦める必要はありません。状況に応じた具体的な対処法がいくつか存在します。
自治体の補助金制度を確認する
地域によっては、墓じまいの費用を一部補助してくれる自治体があります。これは、無縁墓の増加を抑えるために設けられた制度で、主に「墓石の撤去費用」に対して適用されることが多いです。たとえば、撤去費の半額または上限10〜20万円を支給するケースもあります。
補助金の有無や内容は自治体ごとに異なるため、まずはお墓がある地域の市区町村役所やホームページで制度の有無を確認し、必要書類や申請方法を問い合わせてみてください。
メモリアルローンを活用する
銀行や信用金庫の中には、葬儀や墓石、納骨に関する費用に特化した「メモリアルローン」という商品を扱っているところがあります。通常のカードローンや消費者金融よりも金利が低めに設定されており、審査に通れば墓じまいにも利用できます。
分割払いが可能になるため、急な一括支払いが難しい方には有効な選択肢です。ローンの申請は、石材店や霊園が提携している金融機関を通じて行うケースもあるため、見積もりの段階で相談してみるとよいでしょう。
お寺や霊園に相談する
墓じまいを行うお墓が寺院にある場合は、住職に直接相談するのも一つの方法です。閉眼供養や離檀料にかかるお布施などは、基本的に「お気持ち」であるため、経済的事情を丁寧に説明することで、費用面を考慮してもらえることがあります。
長年お世話になった感謝の気持ちを伝えたうえで、分割払いの提案や、お布施額の相談をしてみると、柔軟な対応をしてくれる場合も少なくありません。
親族に協力を依頼する
墓じまいは、一人で抱え込むものではありません。本来、お墓は一族のものであり、複数の家族で支え合って管理されるものです。費用面で困っている場合は、まずは兄弟姉妹や親戚などに相談し、負担を分担できないか話し合ってみましょう。
分担割合に決まりはありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、誰がいくら負担するのかを事前に明確にし、可能であれば簡単なメモや書面に残しておくことをおすすめします。
納骨先を見直す
墓じまいの費用の中でも大きな割合を占めるのが新しい納骨先の費用です。この部分を見直すことで、負担を大幅に軽減できる場合があります。
たとえば以下のような選択肢があります。
- 合祀墓(ごうしぼ):他の方のご遺骨と一緒に埋葬する形式。費用は5万円〜30万円程度と安価ですが、ご遺骨を後から取り出すことはできません。
- 散骨:ご遺骨を自然に還す方法で、費用は5万円〜20万円程度。維持費が不要な点も特徴です。
- 手元供養:小さな骨壷やアクセサリーにご遺骨を納め、自宅で供養する方法。1万円〜10万円ほどで始められます。
これらは費用を抑えるうえでは有効ですが、それぞれに特有の注意点もあるため、親族とよく話し合い、納得のいく方法を選ぶことが大切です。

費用の問題は、墓じまいに踏み切る際に多くの方が直面する現実的な課題です。しかし、自治体や金融機関の制度、寺院との相談、親族の協力など、活用できる支援は多岐にわたります。「費用が払えない=墓じまいができない」と決めつけず、まずは一つひとつの手段を確認してみることが、解決への第一歩となります。
平日10時~18時
今あるお墓を維持する場合との比較
お墓じまいには費用がかかる一方で、「今あるお墓をこのまま維持し続けたほうが良いのでは?」と悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、お墓を維持し続けた場合にかかる費用と、墓じまいをした場合の費用を比較し、どちらが長期的に見て負担が少ないかを考えていきます。
お墓を維持する場合の費用
現在あるお墓をそのまま残す場合、毎年定期的に支払う費用や、突発的なメンテナンス費用が必要になります。代表的な費用項目は以下のとおりです。
- 年間管理費:5,000円〜1万円前後
霊園や寺院などの施設が行う草刈りや通路整備などの維持管理のための費用です。 - お墓参りにかかる交通費:数千円〜数万円(年数回)
遠方にお墓がある場合、交通費や宿泊費がかかることもあります。高齢になると自力での移動が難しくなり、タクシーや代行サービスの利用で費用が増えるケースもあります。 - 掃除・メンテナンス費用:数千円〜数万円
定期的に清掃業者に依頼する場合や、墓石の補修が必要になった場合に発生します。
たとえば、年間管理費1万円+お墓参り費用3万円+メンテナンス費用1万円とすると、年間で約5万円、30年間維持した場合の総額は約150万円にもなります。
墓じまいを行った場合の費用
一方で、墓じまいにかかる費用は一度きりの出費で済むのが特徴です。選ぶ納骨先によって差はありますが、費用の目安は以下のとおりです。
- お墓の撤去費用:20万円〜50万円
- 閉眼供養・離檀料など:3万円〜30万円
- 新しい納骨先の費用:5万円〜150万円(合祀墓や永代供養墓など)
- 行政手続き関連費用:数百円〜数千円
すべて含めて考えると、墓じまいにかかる総額は30万円〜150万円程度です。お墓の場所や状態、選ぶ納骨先によって変動しますが、「将来にわたる費用の心配がなくなる」というメリットは大きいです。
金銭面以外の比較ポイント
費用だけでなく、精神的・身体的な負担も比較において重要な要素です。
- お墓の維持
お墓参りのたびに移動が必要になり、高齢になるほど大きな負担になります。また、継承者がいない場合は将来的に無縁墓になるリスクもあります。 - 墓じまい
一度手続きを行えば、納骨先での永代供養などによって、維持管理の手間はほぼ不要になります。将来のトラブルや子世代への負担を未然に防げる安心感があります。
比較のまとめ
| 項目 | お墓の維持 | 墓じまい |
|---|---|---|
| 初期費用 | 少ない | 多め(30万〜150万円) |
| 維持費 | 毎年必要(管理費・交通費など) | ほぼ不要 |
| 手間・負担 | 継続的に発生 | 一度で完結 |
| 子どもへの負担 | 残る可能性あり | 軽減できる |
| 将来的な無縁墓リスク | 高い | 低い |

お墓を残すことはご先祖様とのつながりを守る一方で、将来にわたって負担が続く選択でもあります。一方で墓じまいは、一定の費用はかかるものの、将来の管理や相続の問題を解消できる方法です。ご自身の年齢や家族構成、生活環境を踏まえ、どちらがご自身やご家族にとって最善か、丁寧に話し合って決めることが大切です。
墓じまいを始める手順と相談先
墓じまいは一度きりの大切な手続きであり、関係者や手順も多岐にわたるため、しっかりと準備をして進めることが大切です。
ここでは、実際に墓じまいを始める際の基本的な流れと、安心して相談できる窓口についてご紹介します。
1. 親族間で話し合い、同意を得る
まず最初にすべきことは、家族や親族との話し合いです。墓じまいは故人だけでなく、ご先祖様の供養や家族の信仰にも関わるため、感情面でも大きな影響があります。以下のような点を確認しましょう。
- 墓じまいの理由と背景(承継者がいない、遠方で維持が困難など)
- 新しい納骨先の候補(永代供養、樹木葬など)
- 費用の分担について
十分な説明と納得を得ることで、後々のトラブルを避けることができます。
2. 新しい納骨先を決める
墓じまいでは、ご遺骨の行き先を確保することが必須です。改葬(お墓の引っ越し)をするには、「新しい納骨先」が決まっていなければ、行政手続きを進めることができません。
納骨先の選択肢には以下のようなものがあります。
- 永代供養墓(合祀型・個別型)
- 納骨堂
- 樹木葬
- 一般墓の再建
- 散骨
- 手元供養
費用や宗教的配慮、立地などを考慮し、ご家族でよく相談して決めましょう。
3. 墓地管理者や寺院への相談
現在のお墓がある霊園や寺院に、墓じまいの意向を伝えましょう。寺院墓地の場合は、離檀の手続きも必要となります。
- 閉眼供養(魂抜き)の日程の調整
- 離檀料の有無と金額の確認
- 必要書類の発行依頼(埋葬証明書など)
丁寧な対応が求められる場面です。誠意を持って相談すれば、柔軟に対応してくれる寺院も多くあります。
4. 行政手続きを進める
墓じまいを正式に行うためには、市区町村に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を取得する必要があります。以下の3つの書類が基本的に必要です。
- 埋葬証明書(現在のお墓の管理者から)
- 受入証明書(新しい納骨先の管理者から)
- 改葬許可申請書(自治体窓口で入手)
この手続きはご自身で行うこともできますが、代行してくれる業者や行政書士に依頼することも可能です。
5. 石材店に撤去工事を依頼する
改葬許可証を取得したら、いよいよ墓石の撤去工事に進みます。撤去費用は業者によって差があるため、複数の石材店から見積もりを取るのがポイントです。
- 墓石の解体・運搬・処分
- 墓地の整地(更地に戻す)
- ご遺骨の取り出しと運搬
指定業者しか使えない霊園もあるため、あらかじめ墓地管理者に確認しておくことが大切です。
6. 新しい納骨先での供養を行う
ご遺骨を移した後には、納骨式や開眼供養(魂入れ)を行うのが一般的です。納骨先の施設が宗教儀礼を伴うタイプの場合、僧侶を手配し、感謝の気持ちを込めてお布施をお渡しします。
7. 相談先の選び方
初めての墓じまいで不安を感じる方も多いかと思います。以下のような相談窓口を活用すると安心です。
- 墓じまい専門の無料相談窓口(ネットや電話で相談可能)
- 一括見積もりサイト(複数業者の料金やサービスを比較)
- 石材店や霊園の管理事務所
- 行政書士や終活アドバイザー
これらを活用することで、費用面でも手続き面でも納得のいく選択がしやすくなります。

墓じまいは一見大変そうに思えるかもしれませんが、ひとつひとつ手順を踏んでいけば確実に進めることができます。不安な点は、信頼できる相談先に遠慮なく問い合わせて、後悔のない形で供養を進めていきましょう。
平日10時~18時