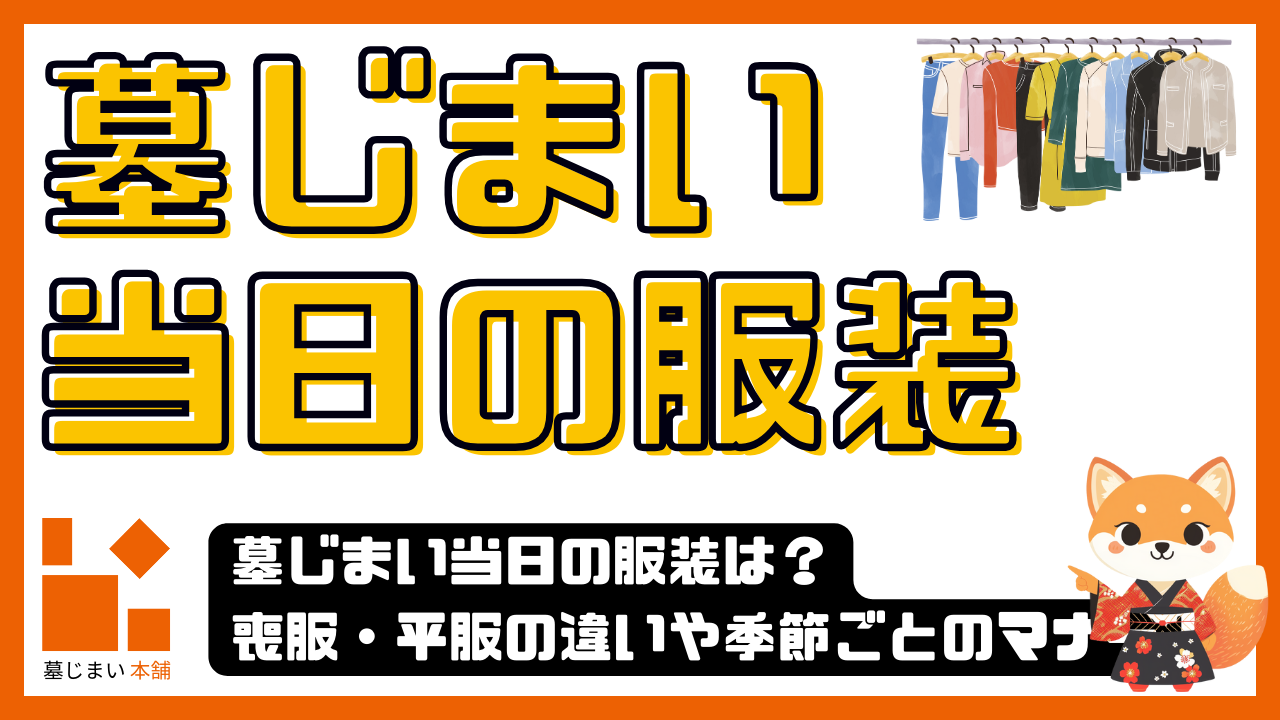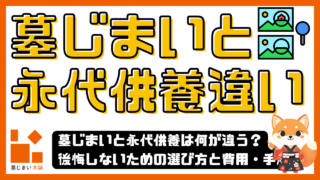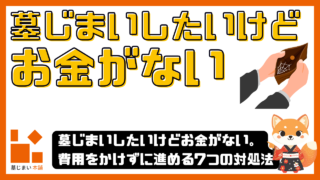本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいの服装、まず何を基準に考えるべき?
墓じまいは、故人との最後のお別れとなる大切な節目です。その場にふさわしい服装とは何か、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
服装選びで最も大切なことは、「故人への敬意を表し、周囲に不快感を与えないこと」です。
まず意識したいのは、墓じまいに立ち会う「場の雰囲気」と「誰が参列するか」です。たとえば、お寺で僧侶を招いて閉眼供養(魂抜き)を行う場合と、解体作業に立ち会うだけの場合では、求められる服装の格が異なります。
閉眼供養を伴う場合は、喪服が基本とされています。特に僧侶が読経を行う場では、正装としての喪服を選ぶことが無難です。ただし、必ずしも通夜や葬儀で着用するようなフォーマルな礼服でなければならないわけではなく、略喪服や地味な平服でも問題ないとされるケースもあります。地域や宗派によって考え方が異なるため、事前にお寺や親族と相談するのが賢明です。
一方、閉眼供養を行わず、墓石の解体工事のみ立ち会う場合は、略礼装にあたる平服で十分です。とはいえ、Tシャツやジーンズなどのラフすぎる普段着は避けましょう。平服とは「略式礼装」を意味し、きちんと感がありつつ、フォーマルすぎない落ち着いた服装のことです。
また、参列者との服装のバランスも重要なポイントです。喪服で参加する人が多い場に自分だけがカジュアルすぎる格好で行くと、場の空気を乱しかねません。服装の方針がはっきりしない場合は、喪主や家族間であらかじめ相談しておくことで、こうしたトラブルを防ぐことができます。
服装に正解はなくとも、「迷ったら控えめで落ち着いた服装を選ぶ」ことが基本です。黒や紺、グレーといった暗めの色合いをベースに、柄のない無地のアイテムを選ぶのが無難です。過剰な露出や派手なアクセサリーは避け、清潔感を大切にしましょう。
墓じまいは儀式であると同時に、家族や親族が一堂に会する機会でもあります。場に合った服装は、周囲への配慮であり、故人への礼節でもあります。何を基準にすればよいかわからないときほど、「場にふさわしいか」「周囲と調和が取れるか」という視点で服装を見直してみてください。
閉眼供養の有無で服装はどう変わる?
墓じまいにおいて、服装選びで迷いやすいポイントの一つが「閉眼供養の有無」です。この供養の有無によって、求められる服装の格が大きく変わるため、事前に内容をしっかり把握しておくことが重要です。
閉眼供養とは、お墓に宿るとされる故人の魂を抜く儀式のことです。僧侶を招いて読経が行われる、いわば法要の一種であり、その厳かな雰囲気にふさわしい服装が求められます。一般的には、通夜や葬儀で着用するような喪服が基本です。とくに親族が揃う場面では、略喪服やブラックフォーマルで統一すると、場の調和もとれやすく安心です。
一方、閉眼供養を伴わず、墓石の撤去工事のみを行うケースでは、そこまで格式ばった服装は求められません。この場合は、平服と呼ばれる略式礼装で問題ありません。ただし、平服といっても普段着とは異なり、Tシャツやジーンズ、スニーカーなどのカジュアルな服装は避けるべきです。男性ならダークカラーのジャケットにシャツとスラックス、女性なら地味な色合いのワンピースやアンサンブルが一般的です。
服装選びに迷う場合は、当日の内容だけでなく、「僧侶が来るかどうか」「どこまで親族が集まるか」も判断材料になります。僧侶が参列する場合は、法要としての位置づけが強くなるため、基本的には喪服が望ましいとされています。僧侶が来ない、または読経なども行わず、現場確認だけで済ませるような場合であれば、平服で問題ありません。
また、閉眼供養を別日に済ませており、当日は工事だけというケースもあります。その場合でも、できるだけ清潔感のある落ち着いた服装を選びましょう。現場では草地や土の上を歩くことがあるため、女性のヒールや滑りやすい革靴などは避け、歩きやすい靴を選ぶのが実用的です。

形式にとらわれすぎる必要はありませんが、墓じまいは故人への最後の敬意を示す場でもあります。「誰が参列し、どのような内容になるのか」に応じて、TPOに合った服装を選ぶことが大切です。迷ったときは、喪主やお寺に確認することで安心感が得られます。
平服の正しい選び方と注意点
「平服」と聞くと普段着を想像される方も多いかもしれませんが、墓じまいの場における平服は「略礼装」を意味します。これは、正装ほど堅苦しくないものの、一定の礼節を保った服装であり、故人や親族、僧侶に対する敬意を込めた装いです。ここでは、平服としてふさわしい服装と、避けるべきポイントについて詳しくご紹介します。
平服=普段着ではないことを理解する
平服と略されると「楽な格好でもいいのかな」と思いがちですが、実際には以下のような服装が基準になります。
- 色味は黒・紺・グレーなどのダークカラー
- 柄のない無地が基本
- 肌の露出を控える
- 清潔感のあるシンプルな服装
このように、普段のお出かけ用の服とは一線を画した、「控えめで落ち着いた服装」を意識することが大切です。
男性の平服の具体例
男性の場合、以下のような服装が一般的です。
- ダークスーツ(礼服でなくてOK)
- 白のワイシャツ
- 無地の黒や紺のネクタイ
- 黒や濃い茶の革靴(スニーカーは避ける)
夏場はジャケットを省略してワイシャツのみでも問題ありませんが、袖まくりや開襟スタイルなどラフすぎる印象にならないよう注意が必要です。
女性の平服の具体例
女性の服装は、落ち着いたデザインと動きやすさを両立させることがポイントです。
- 黒・紺・グレー系のワンピース、アンサンブル、セットアップ
- ストッキングは黒か肌色(素足は避ける)
- 靴は音が鳴らないローヒールのパンプスやバレエシューズ
スカートの場合は膝下丈が望ましく、ミニスカートやスリットが深いデザインは控えましょう。ブラウスやカーディガンを組み合わせる場合も、フリルやレースなど華美な装飾のあるものは避けた方が無難です。
子どもの平服の例
子どもが制服を持っている場合は制服が基本です。制服がない場合は以下のような服装を意識しましょう。
- 男子:白シャツ+黒や紺のズボン
- 女子:落ち着いた色合いのワンピースやスカート+カーディガン
- 靴は黒や白系のスニーカーやローファー
キャラクター入りの服、カラフルな靴、派手なリュックなどは避け、できるだけシンプルにまとめると印象が良くなります。
アクセサリー・化粧・小物の注意点
- 結婚指輪や一連のパールネックレス程度にとどめる
- ピアスは小さく控えめなものを
- 化粧はナチュラルメイクが基本
- 派手な時計や香水も控える
バッグは黒やグレーなどの布製か合皮のものが適しており、ブランドロゴの大きなものや派手なカラーのものは避けましょう。
墓地に合わせた靴選びも重要
墓じまいの現場では砂利道や傾斜、ぬかるみなども想定されます。革底の靴や高すぎるヒールは滑る原因となり危険です。特に女性や子どもは、安定感があり歩きやすい靴を選びましょう。あらかじめ防水スプレーをかけておくなど、雨への備えもおすすめです。
避けるべきNGな服装
以下のような服装は、たとえ平服であっても墓じまいにはふさわしくありません。
- ジーンズ・デニム素材の衣類
- 派手なカラー(赤・ピンク・オレンジなど)
- 半袖Tシャツやパーカー
- キャラクタープリント入りの衣類
- ミニスカートや短パン
- サンダルやクロックス
墓じまいはフォーマルな場とまではいかないものの、儀式的な意味合いが強いため、「場の格」に見合った装いが求められます。

平服とは、あくまで略式礼装であり、「カジュアル」とは異なることを意識しておくと迷いにくくなります。「派手すぎず、地味すぎず、故人への敬意が伝わる」ことを基準に、心を込めて服装を整えることが大切です。
季節・天気別|墓じまい当日の服装ポイント
墓じまいは、季節や天候によって現場の状況が大きく変わるため、事前にその日の気候を考慮した服装選びが重要です。ただし、どの季節・天候であっても「故人への敬意」と「動きやすさ・実用性」の両立が求められます。ここでは、夏・冬・雨の日における具体的な服装のポイントを解説します。
夏(6月〜9月頃)|暑さ対策をしながら清潔感を意識
暑い時期の墓じまいは、無理に喪服を着込む必要はありません。ただし、あくまでも「略礼装」であることを意識し、軽装すぎないように注意しましょう。
男性の場合
- ワイシャツ+スラックスが基本(ジャケットは省略可)
- 汗ジミが目立ちにくい色合いを選ぶ(薄グレーや濃紺など)
- 通気性の良い素材(麻混、吸湿速乾など)を活用
女性の場合
- 半袖のワンピースやブラウス+ロングスカート
- 肌の露出は最小限に(袖丈・スカート丈に注意)
- 日傘やUVカットカーディガンで紫外線対策
共通の注意点
- 汗対策として制汗シートやハンカチを用意
- サンダルやミュールはNG。必ずかかと付きの靴を選ぶ
- 帽子は控えめな色と形で、儀式中は外すのがマナー
冬(12月〜2月頃)|防寒しながら礼儀を忘れない装い
寒い時期は、外気との闘いになるため、温かさと礼節を両立させた服装が求められます。防寒アイテムの素材や色選びにも配慮しましょう。
男性の場合
- スーツや礼服の上にウールや中綿入りの黒やグレーのコート
- マフラーは無地の暗色でロゴや柄の目立たないものを
- 靴は防水性のあるビジネスシューズやブーツ(光沢のない革製)
女性の場合
- アンサンブルやワンピース+コート(フェイクファーは避ける)
- 黒の手袋・マフラー・タイツなどを組み合わせて防寒
- 長時間屋外にいる場合は、ホッカイロを腰やお腹に貼って調整
NG例
- 革ジャンや毛皮のコート(殺生を連想させるため)
- 派手な色のダウンや柄物マフラー
- ロングブーツで足元が重くなりすぎるスタイル
雨の日|雨具と足元の工夫が鍵
墓地は足元がぬかるみやすいため、雨天時は特に靴選びと服の素材に注意が必要です。傘の色や小物にも気を配りましょう。
服装の基本
- 喪服・平服のいずれでも可(閉眼供養の有無で判断)
- 撥水性のある上着やパンツを選ぶと快適
- スカートよりもパンツスタイルの方が安全
雨具の選び方
- 傘は黒・紺・グレーなど落ち着いた色(ビニール傘も可)
- 派手な傘やキャラクター柄は避ける
- レインコートを使う場合も暗色無地を選ぶ
足元の工夫
- 防水加工されたローファーやシンプルなレインブーツ
- ヒールや革靴は滑りやすいため避ける
- 靴下は替えを持参すると安心
季節を問わず持参したい服装小物
- 替えのストッキングや靴下
- 汗拭きシート(夏)/カイロ(冬)
- 折りたたみ傘や帽子(直前の天候変化に備えて)

墓じまいの現場は、舗装されていない場所や草地も多く、天候によって足元や体感温度が大きく変化します。清潔感と礼節を大切にしながら、無理のない範囲で「動きやすさ」「実用性」も取り入れた服装を選ぶことが大切です。
子ども連れでの墓じまい、服装マナーは?
子どもを連れて墓じまいに参加する場合、大人以上に服装への配慮が必要です。特に小さなお子様がいるご家庭では、「どこまで気をつけるべきか」「普段着でもよいのか」など迷うポイントも多いでしょう。ここでは、制服の有無や年齢別にふさわしい服装の選び方、マナーの基本について解説します。
学生の子どもは「制服」が基本
小・中・高校生など、制服がある年齢の子どもは、制服を着用するのが最も適切です。制服には清潔感とフォーマルさがあり、どのような宗派・場面でも失礼にあたりません。
ただし、気をつけたいのは以下の点です。
- 制服が汚れていないかを事前にチェック
- 防寒対策をする場合は、派手でないコートを羽織る(黒・紺・グレーなど)
- 靴下や靴も黒や紺などの落ち着いた色を選ぶ
- 女子の場合、スカートが短すぎないかを確認
寒い季節には、マフラーや手袋をつけることもありますが、柄のない無地のアイテムを選ぶとより印象がよくなります。
制服がない場合のおすすめ服装
制服のない未就学児や、制服のない学校に通う子どもには、ダークカラーを基調にしたシンプルな装いが好まれます。以下を目安に準備すると安心です。
- 男の子:白いシャツ+黒・紺のズボン(ポロシャツでも可)
- 女の子:黒や紺のワンピース、または落ち着いた色のカーディガンとスカート
- 靴:黒や白のスニーカー、ローファー(光る靴やキャラ入りは避ける)
- 靴下:黒・白・グレーの無地を選ぶ
特に派手なデザインやキャラクター柄の服、小さな子どもによく見られる蛍光色のアイテムなどは避けた方が無難です。
小さなお子様には「動きやすさ」も重視
3歳未満の子どもの場合、喪服や平服といった形式よりも、動きやすく清潔感のある服装を重視しましょう。大人のような厳格な礼装は求められないため、落ち着いた色味を意識するだけでも十分です。
おすすめのスタイルは以下の通りです。
- カットソーやポロシャツ+ダークカラーのズボンやスカート
- 白シャツ+ネイビーのカーディガン
- 足元は白や黒のスニーカー(脱げにくいもの)
「少しきちんと見える普段着」に近いイメージで、汚れても洗いやすく、長時間動いても疲れにくい服装を心がけると、子ども本人にも負担が少なくなります。
子ども連れで気をつけたいその他のマナー
服装以外にも、子どもと一緒に墓じまいに参加する際には以下の点にも気をつけましょう。
- 防寒・暑さ対策:体温調整できる羽織ものを持参
- 騒がないように事前に声かけ:供養中に大声を出さないよう説明しておく
- おもちゃやお菓子の持ち込みは控えめに:ぐずった場合用に、音の出ないおもちゃやお菓子をカバンに忍ばせるのは可
- 周囲に配慮した行動:大人の参列者に迷惑をかけないよう、必要があれば途中で少し離れる判断も大切
小さなお子様を連れての参列は気を遣うことも多いですが、親としての丁寧な準備と対応があれば、どのような場でも温かく受け入れてもらえるものです。

子ども連れでの墓じまいは、「子どもだから何でも許される」というわけではありませんが、年齢に応じた配慮と清潔感のある装いを意識することで、十分に礼儀を尽くすことができます。故人に対する敬意と、周囲への気配りを大切にしながら、親子で心を込めて臨みましょう。
服装に迷ったら?お寺・親族への相談がカギ
墓じまいの服装に正解はなく、地域や宗派、家族ごとの価値観によって「ふさわしい」とされる基準が異なります。そのため、「ネットで調べたけど、自分たちのケースに合っているのか不安」「親戚の中で浮かない服装って?」と迷う方も多いのが実情です。そうしたときは、事前にお寺や親族に相談することが何よりの解決策になります。
特に僧侶を招いて閉眼供養を行う場合や、親族が多く集まるケースでは、形式を重んじる傾向があります。自分では「これで大丈夫だろう」と思っていても、他の親族が正喪服で参列していた場合、自分だけ浮いてしまう可能性もあります。事前に喪主や主催者に「服装は平服で良いでしょうか?」と一言確認するだけで、こうしたズレを防ぐことができます。
また、お寺に確認することで、宗派による服装マナーの違いにも対応できます。たとえば、浄土真宗では「黒を避けるべき」といった宗派ごとの考え方がある場合もあるため、僧侶の立ち会いがある場合は特に、直接寺院に電話で確認するのが安心です。
さらに、墓じまいの際にどこまで儀式的な要素があるのかによっても、服装の方向性が変わります。たとえば「読経があるのか」「祭壇を設けるのか」「記念撮影をするのか」などを把握しておくと、それにふさわしい服装も見えてきます。
こうした確認を怠ると、たとえば「自分の家族は喪服、他の家族は全員平服だった」といった気まずい状況が生じることもあります。事前に相談することで、全体の服装バランスが整い、当日の雰囲気が和やかになりやすくなります。
なお、相談時には次のような聞き方がおすすめです。
- 「閉眼供養には喪服で参加した方がよいでしょうか?」
- 「ほかの親族の方は、どのような服装で来られる予定ですか?」
- 「お寺のご住職に、服装の指定などありますか?」
自分ひとりで判断しようとせず、まわりの意見を聞くことは、服装選びの失敗を防ぐだけでなく、故人への敬意や親族への配慮にもつながります。形式に縛られすぎる必要はありませんが、「迷ったら相談」を基本にすれば、安心して当日を迎えることができるでしょう。
墓じまいの服装以外に気をつけたい持ち物・マナー
墓じまいは、単なる作業ではなく、故人との最後のお別れとなる大切な儀式です。そのため、服装だけでなく、持ち物やふるまいにも心配りが求められます。ここでは、当日持参すべき物や、押さえておきたいマナーをわかりやすくまとめました。
持ち物リスト|忘れがちなものも事前にチェック
墓じまいの場では、準備不足がトラブルや焦りの原因になることもあります。以下のような持ち物を、チェックリスト形式で準備しておくと安心です。
必ず用意したいもの
- 数珠:仏式であれば持参が基本。宗派問わず使用可能な略式数珠でも問題ありません。
- お布施:閉眼供養を行う場合は、お寺への謝礼として「御布施」を準備。袱紗に包んで持参します。
- お供え物:果物・お菓子・故人の好物など。日持ちするものが無難です。
- 線香・ロウソク・ライター:墓前での供養には必須。風に強いライターだと便利です。
- お花:仏花(白菊・カーネーションなど)を一対で用意するのが一般的。
- 掃除道具:最後のお墓参りとして、ほうき・たわし・雑巾などがあると便利です。
状況に応じて用意したいもの
- 飲み物・ハンカチ・日傘:夏場の暑さ対策に
- 手袋・カイロ・防寒インナー:冬場の寒さ対策に
- 雨具(傘・レインコート・靴のカバー):急な天候の変化に備えて
- お礼状や案内状の控え:参列者に後日送る予定がある場合は、リストの確認用に持参
持ち物は、事前に家族で分担し、誰が何を持つかを明確にしておくと当日慌てずに済みます。
ふるまいに関するマナー|現地で気をつけたいポイント
どんなに身なりを整えても、立ち居振る舞いが雑であれば、故人や周囲への配慮が足りない印象を与えてしまいます。以下の点に注意することで、より丁寧な気持ちが伝わります。
現地での立ち振る舞い
- お墓の前では帽子を取る・会話を控えめに:故人への敬意を第一に
- スマホの電源を切るかマナーモードに:読経中やお焼香中に鳴らないよう注意
- ごみは必ず持ち帰る:供物の包装や使い終えた線香・ロウソクなどもそのままにしない
写真撮影のマナー
- 記念として撮影する場合は、供養後のタイミングに
- 僧侶や他の参列者の了解を得てから撮るのが基本
- SNSなどへの投稿は、顔や宗教的な場面が映る部分は控える
お布施や香典の扱い|タイミングと作法も確認を
僧侶をお呼びする場合には、読経の前後どちらでも構いませんが、タイミングを見て丁寧に渡すことが大切です。
- お布施の表書き:「御布施」「閉眼供養御礼」など。封筒は黄白の水引や無地のものを選びます。
- 金額の目安:1万円~5万円程度が一般的ですが、寺院との付き合い方や地域の慣習によって異なります。
- 渡し方のマナー:袱紗から取り出し、表書きが相手から読める向きで手渡しします。「本日はどうぞよろしくお願いいたします」などの一言を添えると丁寧です。
なお、香典は基本的に不要ですが、親族間の取り決めや閉眼供養の形式によっては用意することもあります。事前に確認しておくと安心です。

墓じまいは、形式以上に「気持ち」が重視される儀式です。服装だけでなく、持ち物や立ち居振る舞いに心を配ることで、故人への最後の挨拶を穏やかに、そして誠実に行うことができます。家族での事前準備をしっかり行い、当日は落ち着いて向き合えるようにしましょう。
よくある質問Q&A
Q. ジャケットなしでも大丈夫ですか?
A. 閉眼供養を行わず、解体工事のみの立ち会いであれば、ジャケットを着用しなくても問題ありません。特に夏場は、白シャツ+スラックスなど、略礼装にあたるきちんとした服装であれば十分です。ただし、他の親族との服装に差が出ないよう、事前に相談しておくのがおすすめです。
Q. 平服とは、どこまでカジュアルで良いのですか?
A. 平服とは「略式礼装」のことで、普段着とは異なります。黒や紺などの無地のスーツやワンピースを基本に、派手すぎない・露出が少ない・清潔感のある服装が望ましいです。Tシャツ、ジーンズ、スニーカー、派手な柄物などは避けてください。
Q. マスクの色は黒のほうが良いですか?
A. マスクの色に厳密な決まりはありませんが、落ち着いた色(白、グレー、黒)が望ましいです。喪服や平服に合わせて違和感のない色を選びましょう。柄入りやカラフルなマスクは控えてください。使い捨てでも布マスクでも構いません。
Q. 雨の日にレインブーツを履いても大丈夫ですか?
A. 雨天時にはレインブーツの着用も許容されます。黒や紺など落ち着いた色で、シンプルなデザインを選べば問題ありません。革靴やパンプスは滑りやすく危険なため、天候によっては実用性を優先するのがよいでしょう。
Q. 閉眼供養を別日に済ませている場合の服装は?
A. 閉眼供養をすでに行っており、当日は工事のみの場合は、平服で問題ありません。ただし、墓前でお焼香を行う場合は、派手すぎない服装を意識し、数珠を持参するなど最低限の礼儀は忘れずに対応しましょう。
Q. 靴下やストッキングに色の決まりはありますか?
A. 基本は黒か肌色の無地が無難です。白い靴下や柄入りは避けた方がよいでしょう。女性の場合、真夏以外はストッキングの着用が望ましく、素足は控えるのがマナーです。
Q. おしゃれなバッグやアクセサリーはNGですか?
A. 服装同様、バッグやアクセサリーも控えめが基本です。ブランドロゴが目立つバッグや、光沢のある素材・カラフルなアクセサリーは避けましょう。結婚指輪や一連パールなど、目立たない範囲の装飾であれば問題ありません。
Q. 子どもが制服を嫌がった場合はどうすれば?
A. 制服が望ましいですが、着用を嫌がる場合は無理に着せる必要はありません。その代わり、黒・紺・グレーなどの落ち着いた色の服装を選び、派手な色やキャラクター柄の服は避けてください。着替えを持参しておくと安心です。
Q. 喪服がない場合はどうしたらよいですか?
A. 略喪服や地味な平服でも問題ありません。特に閉眼供養を行わない場合や、簡易的な儀式の場合は、スーツやワンピースなどでも十分に対応できます。必要に応じて、家族や親族から借りる、レンタルを利用するのも一つの手段です。
Q. 化粧はどこまでしても大丈夫ですか?
A. 派手なメイクは避け、ナチュラルメイクが基本です。アイシャドウや口紅の色は控えめにし、ラメや濃いチークなどは控えるようにしましょう。香水の使用も避けた方が無難です。清潔感を意識した控えめな装いを心がけてください。
平日10時~18時