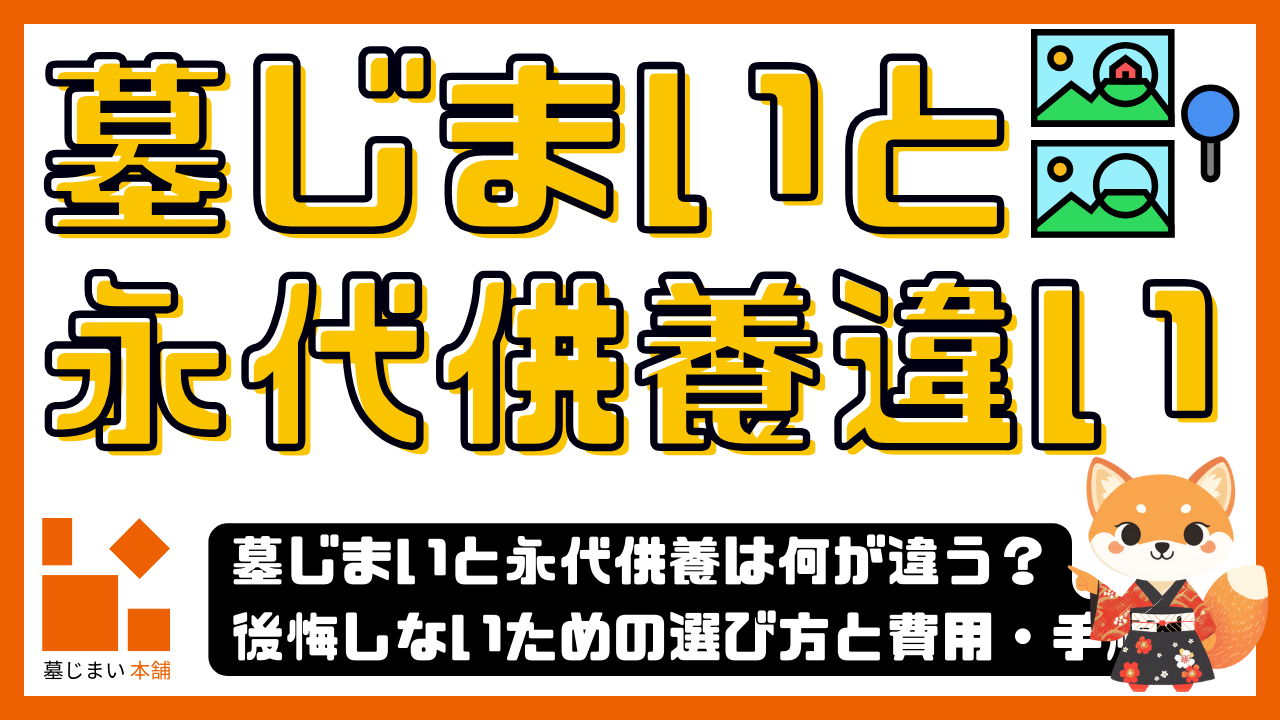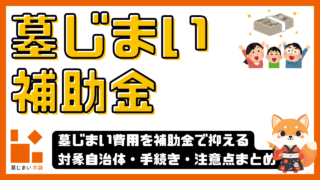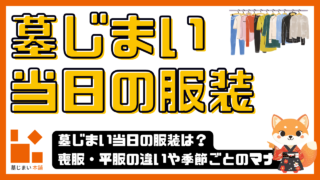本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいと永代供養はどう違う?わかりやすく解説
墓じまいと永代供養はよく一緒に語られることが多いため、同じような意味と誤解されがちです。しかし、この2つは役割や目的がまったく異なります。
ここでは、それぞれの違いをわかりやすく整理し、よくある誤解についても解説します。
墓じまいとは?
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、ご遺骨を取り出して墓地を更地に戻し、使用していた土地を墓地の管理者に返還する手続きのことです。
お墓を維持するのが難しくなったとき、家族や子供に将来の負担をかけたくないと考えたときなどに選ばれる方法です。
墓じまいはあくまで「お墓を片づけること」が目的であり、ご遺骨の供養や管理そのものは含まれていません。ご遺骨は墓じまい後に別の場所で改めて供養する必要があります。
永代供養とは?
永代供養とは、ご遺族に代わって、寺院や霊園がご遺骨を永続的に供養・管理してくれる方法です。
永代供養墓や納骨堂、合祀墓などにご遺骨を納め、一定期間は個別に供養し、その後は他の方と一緒に合祀されるケースが一般的です。
永代供養の目的は「供養と管理」であり、墓じまいとは根本的に異なる性質を持っています。また、後継者がいない方でも安心して利用できる点や、費用・管理の負担が軽減される点が選ばれる理由です。
よくある誤解と混同ポイント
1. 墓じまいをすれば自動的に永代供養になる?
→なりません。墓じまいはあくまでお墓の撤去であり、その後のご遺骨の行き先(供養方法)は別途自分で決めなければなりません。
2. 永代供養だけすれば墓じまいは不要?
→場合によります。すでにお墓がある場合は、ご遺骨を永代供養墓に移すために墓じまい(改葬手続き)が必要です。ただし、初めから永代供養墓に納骨する場合は、墓じまいは発生しません。
3. 永代供養すればずっと個別に供養してもらえる?
→施設やプランによって異なります。多くの永代供養では一定期間(たとえば33回忌など)が過ぎると、他の方と合祀されます。希望する供養形式がある場合は、契約前に確認が必要です。
4. 墓じまいは親族の同意がなくてもできる?
→基本的には同意が必要です。墓じまいは親族全体に関わる問題であり、勝手に進めるとトラブルになる可能性があります。必ず事前に話し合いをしましょう。
5. 永代供養すれば供養の気持ちは不要?
→そうではありません。永代供養はあくまで供養と管理を代行してもらうものであり、心の中で故人を偲ぶ気持ちは大切に持ち続けることが望まれます。

墓じまいと永代供養はそれぞれ役割が異なりますが、状況に応じてセットで検討する方が多いのも事実です。違いをしっかり理解することで、ご自身やご家族に合った選択ができるようになります。
墓じまいと永代供養はセットで行うことが多い理由
お墓を維持することが難しくなったとき、多くの方が選ぶのが「墓じまい」です。しかし、墓じまいは単にお墓を撤去して更地に戻す作業に過ぎず、ご遺骨の供養先を別に確保しなければなりません。
そこで注目されているのが「永代供養」です。
この2つは本来別のものですが、実際にはセットで行うケースが非常に多くなっています。
その背景には、現代の家族構成や生活環境の変化が関係しています。
墓じまい後の供養先として永代供養が選ばれる背景
現在、日本では核家族化や高齢化が進み、お墓の管理や供養を担う人が少なくなっています。お墓のある場所が遠方にあったり、子どもが都市部で生活していたりする場合、定期的なお参りや清掃が難しくなります。また、そもそも子どもがいない、または子どもにお墓の負担をかけたくないという声も多く聞かれるようになりました。
こうした事情から、お墓を撤去して身軽にしたいという思いと同時に、「それでもきちんと供養はしたい」という気持ちを持つ方が増えています。永代供養は、遺族に代わって寺院や霊園が責任を持って供養してくれるため、安心してご遺骨を託せる方法として選ばれているのです。
また、永代供養は一度費用を支払えばその後の管理費用が不要な場合が多く、経済的な負担が軽くなることも大きな理由です。墓じまいによってお墓の維持コストがなくなり、永代供養で継続的な供養を確保できる。この組み合わせが、心理的にも実務的にも多くの人に受け入れられているのです。
他の供養方法との比較
墓じまい後の供養方法には、永代供養のほかにもさまざまな選択肢があります。たとえば「手元供養」や「海洋散骨」「樹木葬」「納骨堂」などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
- 手元供養はご遺骨を自宅に保管する方法で、常に故人を身近に感じられる一方で、災害時の対応や法的な扱いが曖昧な面もあります。
- 海洋散骨は自然に還すという選択肢ですが、一度散骨するとご遺骨は二度と取り戻せません。
- 樹木葬は自然志向の方に人気ですが、地域によって対応施設が限られています。
- 納骨堂は屋内にご遺骨を安置する形式で利便性が高い反面、維持管理や契約期間に制限がある場合もあります。
こうした供養方法の中で、永代供養は「きちんと供養される安心感」「宗派にとらわれにくい自由さ」「費用面での明快さ」といったバランスの取れた特徴があり、墓じまい後の受け皿として多くの人に選ばれているのです。

このように、墓じまいと永代供養はそれぞれ目的が異なるものの、実際には非常に相性がよく、安心・経済的・実務的な理由からセットで行う方が増えています。自分や家族の将来を考え、無理なく供養を続けていくための選択肢として、セットでの検討はとても合理的な判断といえるでしょう。
墓じまいから永代供養までの流れをやさしく解説
墓じまいと永代供養を安心して進めるためには、全体の流れを正しく理解しておくことが大切です。手続きや儀式、必要な準備をひとつひとつ確認しながら進めれば、トラブルを防ぎ、後悔のない供養ができます。ここでは、ご家族やお子様と一緒に進める前提で、やさしく丁寧に流れを解説します。
親族・お寺との相談
最初に行うべきは、ご家族・親族への相談です。お墓の継承に関しては、それぞれの思いや考え方がありますので、時間をかけて丁寧に話し合うことが大切です。親族間の理解が不十分なまま手続きを進めてしまうと、後でトラブルになることもあるため、必ず「みんなの気持ちを聞いてから動く」ことを心がけましょう。
相談の際には、「なぜ墓じまいを考えているのか」「その後はどう供養するのか」を明確に伝えると、理解が得られやすくなります。
また、現在お墓を建てているお寺がある場合は、住職への相談も必要です。お寺との関係が長い場合、急な墓じまいには抵抗を感じられることもあります。感謝の気持ちを込めて、丁寧に事情を説明しましょう。檀家を離れる場合には、離檀料が必要になることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
行政手続きと必要書類
ご遺骨を別の場所へ移すためには、「改葬許可証」という書類を取得する必要があります。この手続きには、以下の3つの書類が必要です。
- 埋葬証明書:現在のお墓の管理者から受け取る
- 受入証明書:新たな納骨先(永代供養墓など)から受け取る
- 改葬許可申請書:市区町村の役所に提出する書類
これらを役所に提出すると、改葬許可証が発行されます。この証明書がなければ、ご遺骨を移すことができません。取得には数日〜1週間ほどかかる場合がありますので、余裕を持って準備しておきましょう。
なお、海洋散骨や手元供養など、改葬に当たらない供養方法を選ぶ場合は、改葬許可証が不要になるケースもあります。
墓石の撤去と閉眼供養
行政手続きが終わったら、いよいよ実際の作業に入ります。まずは墓石を撤去するために、石材店へ依頼を行います。お寺や霊園によっては指定業者がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。見積もりは複数の業者に依頼すると、費用の比較や交渉がしやすくなります。
撤去前には、「閉眼供養(へいがんくよう)」という儀式を行います。これは、お墓に宿るとされる故人の魂を抜き、墓石をただの石に戻す大切な法要です。僧侶に読経をお願いし、家族で手を合わせて感謝の気持ちを伝える時間でもあります。
閉眼供養の後、ご遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を更地に戻します。石材店の作業は1日〜数日程度で完了するのが一般的です。
永代供養墓への納骨と開眼供養
墓じまいが完了したら、ご遺骨を新たな供養先へ移します。永代供養墓に納骨する場合、施設によっては「開眼供養(かいげんくよう)」を行うこともあります。これは新しい供養場所に魂を宿すための儀式で、故人の安らかな眠りを願って行います。
納骨当日は、供養施設のスタッフや僧侶の案内に従って納骨を行い、お線香をあげて手を合わせましょう。これで、墓じまいから永代供養までの一連の流れは完了です。
ご遺骨が長期間お墓の中にあった場合、湿気を含んでいたり骨壷が劣化していることもあります。そのような場合は、納骨前に洗浄や乾燥などのメンテナンスが必要になることもあるため、施設に相談して対応してもらいましょう。

墓じまいから永代供養までは、感情的にも手続き的にも負担のかかる工程が続きますが、流れを正しく把握し、1つ1つ丁寧に進めていけば安心して供養を完了することができます。大切なのは、故人を想う気持ちを大切にしながら、ご家族全員が納得のいくかたちで選択を進めることです。
墓じまい・永代供養にかかる費用の目安と内訳
墓じまいや永代供養には、複数の費用が発生します。どちらも「いくらかかるのか分からない」と不安に思う方が多いですが、事前に相場や内訳を知っておくことで、予算の見通しが立てやすくなります。ここでは、費用の目安と、具体的にどんな支払いが必要になるのかをわかりやすく解説します。
墓じまいにかかる主な費用
墓石の撤去費用
墓じまいの中でもっとも大きな費用となるのが、墓石の撤去費です。墓地の広さや石の量、作業環境によって費用は変わりますが、1平方メートルあたり約10万円前後が相場とされています。
一般的な広さであれば、30万円〜50万円程度が目安です。ただし、墓地が山間部や重機が入れない場所にある場合は、人力作業となり、追加料金が発生することがあります。
閉眼供養(魂抜き)のお布施
撤去前に行う儀式「閉眼供養」は、僧侶に読経を依頼します。このお布施の相場は3万円〜5万円程度です。お寺によっては「お気持ちで結構です」とされる場合もありますが、不明な場合は5万円を用意しておくと安心です。
離檀料(檀家をやめる際の謝礼)
お寺に属していたお墓を墓じまいする場合、檀家を離れる際に「離檀料」を求められることがあります。これは法的義務ではなく、これまでの感謝を表す意味合いで支払うもので、相場は10万円〜20万円程度です。
ただし、まれに高額な離檀料を請求されるケースもあるため、不安な場合は親族や第三者(行政書士や弁護士)に相談することをおすすめします。
行政手続きに関する費用
墓じまいを行うには、改葬許可証の取得が必要です。
この手続きに必要な書類と目安費用は以下の通りです。
- 埋葬証明書(現在の墓地管理者から):300円〜1,500円程度
- 受入証明書(永代供養先から):無料〜数百円程度
- 改葬許可申請書(市区町村役所へ提出):無料〜1,000円程度
行政手続きの費用は数千円以内で済むのが一般的です。
永代供養にかかる主な費用
永代供養の費用は、納骨方法や施設の立地・サービス内容によって大きく変動します。ここでは代表的なプランごとの費用目安を紹介します。
合祀型(他の方とまとめて埋葬)
費用を抑えたい方に選ばれる最も安価な方法で、5万円〜30万円程度が相場です。納骨後は他の方のご遺骨と一緒に合葬され、個別の管理は行われません。
個別安置型(一定期間は個別に安置)
一定期間(13回忌・33回忌など)まで個別に納骨し、その後に合祀される形式です。20万円〜80万円程度が相場で、期間が長いほど費用は上がる傾向にあります。
個別型(永続的に個別管理)
永続的に個人または家族単位での管理が行われるタイプで、従来のお墓に近い形式です。50万円〜150万円以上が相場となり、管理費が不要なプランも多くあります。
開眼供養のお布施
永代供養墓にご遺骨を納める際に、開眼供養(魂入れ)を行うことがあります。こちらのお布施も3万円〜10万円程度が目安です。
その他の費用(刻字料・納骨手数料など)
永代供養墓では、ご遺骨の納骨にあたり名前を刻む「刻字料」や「納骨手数料」が必要になる場合もあります。刻字料は1名につき3万円〜5万円程度、納骨手数料は1万円〜3万円前後が目安です。
費用を抑えるポイントと補助制度
墓じまいや永代供養にはまとまった費用がかかるため、費用を抑える工夫も大切です。
- 見積もりは複数の業者から取る:撤去費や納骨料は業者によって差があります。必ず複数社に見積もりを取りましょう。
- 寺院や霊園のパッケージプランを活用:墓じまいと永代供養がセットになったプランは、個別手配より安くなる場合があります。
- 自治体の補助金制度を確認:一部の自治体では、墓じまいに対する補助金制度があります。対象条件や金額は地域によって異なるため、役所や市民相談窓口で確認してみましょう。
墓じまいと永代供養の費用は、一般的に合計で50万円〜100万円前後が多いですが、選ぶ供養方法や施設の内容によっては、さらに高額になることもあります。一方で、納骨後の維持費が不要になり、長い目で見れば大きな経済的負担の軽減につながる選択でもあります。

後悔のない決断をするためには、あらかじめ費用の全体像を把握し、複数の選択肢を比べながら、ご家族と相談して決めることが大切です。
墓じまい後に永代供養を選ぶメリット・デメリット
永代供養は、墓じまいのあとに選ばれることが多い供養方法のひとつです。
従来のお墓とは異なり、遺族に代わって寺院や霊園が供養を行ってくれるため、現代のライフスタイルに合った供養の形として注目されています。ここでは、永代供養を選んだ場合のメリット・デメリットを具体的に整理し、判断の参考になるようにまとめました。
永代供養のメリット
1. 管理が不要になる
永代供養は、寺院や霊園が供養やお墓の管理を代行してくれるため、遺族が掃除や管理費の支払いなどを続ける必要がありません。高齢の方や、遠方に住んでいて定期的な訪問が難しいご家族にとって、大きな安心材料となります。
2. 後継者がいなくても安心
従来のお墓は代々受け継ぐ前提で建てられていますが、少子化や未婚化の進む現代では、後継者がいないケースも増えています。永代供養であれば、家族がいなくても供養を継続してもらえるため、「自分の死後が不安」という方にも選ばれています。
3. 費用負担が軽くなることが多い
一般的な墓地に比べて、永代供養は費用面でもメリットがあります。初期費用を一度支払えば、以後の管理費は不要な場合が多く、年間での費用負担を気にする必要がありません。また、墓石を建てる必要がないプランも多く、初期費用自体も比較的抑えやすくなっています。
4. 宗教・宗派を問わない施設が増えている
最近では、無宗教・無宗派でも利用できる永代供養墓が増えてきました。そのため、家の宗派にとらわれることなく、自分や家族の希望に合った場所を選びやすくなっています。
永代供養のデメリット
1. ご遺骨の取り出しができなくなるケースがある
永代供養では、一定期間個別に管理された後に他の方と合祀(ごうし)される形式が一般的です。一度合祀されると、他のご遺骨と混ざってしまうため、後から取り出すことはできません。将来的に別の場所に移したい、分骨したいと考えている場合には注意が必要です。
2. 供養の実感が薄れると感じる人も
永代供養では定期的な法要が行われる一方で、遺族が個別にお墓参りをする場所がなかったり、合祀墓での供養となることで「手を合わせる対象がない」と感じる方もいます。供養を「心のよりどころ」としたい人にとっては、少し物足りなさを感じる場合もあるでしょう。
3. 親族との合意がないまま進めるとトラブルになることも
特に先祖代々のお墓を墓じまいして永代供養にする場合、親族との考え方の違いが表面化することがあります。「お墓を残したい」「自分の子どもにも墓参りの習慣を受け継がせたい」と考える方がいる可能性もあるため、事前の話し合いと同意形成は欠かせません。
家族でよく話し合って決めることが大切
永代供養には、多くのメリットがある一方で、供養のかたちが大きく変わるために感じるデメリットもあります。何より重要なのは、供養の形式に正解・不正解はなく、それぞれの家族や状況に合った方法を選ぶことです。

「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「子どもにお墓の負担を背負わせたくない」「きちんと供養される形を残したい」といった気持ちは、どれも大切にすべきものです。墓じまいと永代供養は一度きりの選択になることが多いため、焦らずにじっくりと考え、ご家族ともよく話し合ってから進めることが、後悔しない選択につながります。
永代供養を選ぶ人が増えている背景
近年、永代供養を選ぶ方が急速に増えています。その背景には、社会構造の変化や価値観の多様化が大きく影響しています。ここでは、「なぜ永代供養を選ぶ人が増えているのか」を、実際の声や具体的な社会的背景とともに詳しく解説します。
お墓の後継者がいない家庭が増加
かつては「家を継ぐ人=お墓を守る人」という考え方が一般的でした。しかし、少子化・晩婚化・未婚率の上昇により、子どもがいない、あるいは子どもが遠方に住んでいるという家庭が増え、今やお墓の継承が困難な状況は特別なことではなくなっています。
「自分が亡くなったあと、お墓を誰が見てくれるのか不安」
「息子は海外に住んでいて、帰省も難しい」
といった声が多く聞かれ、こうした不安を解消する方法として永代供養が選ばれています。
墓守の負担を子どもに背負わせたくないという親心
「墓じまいをして永代供養にしたい」と考える方の多くは、「子どもに迷惑をかけたくない」という親としての気持ちを語ります。
たとえば、以下のような事情があります。
- 遠方に住む子どもに年に何度も帰省させるのは気が引ける
- 管理費や法要の負担が将来の生活を圧迫しないか心配
- 家族の形が変わり、代々受け継ぐこと自体が難しい
永代供養は、こうした将来への不安や子どもへの配慮から「自分の代で完結できる供養の方法」として、高く評価されています。
管理の手間と費用を減らしたいという現実的な理由
お墓を維持するためには、定期的な掃除、草むしり、供花やお線香の準備、そして年会費や管理費といった経済的な支出がついて回ります。特に高齢者にとっては、墓参りに行く体力や時間の確保も簡単ではありません。
永代供養であれば、最初に費用を支払っておけば、後の手間や追加費用はほとんど発生しません。管理や供養は施設側が責任を持って行ってくれるため、「手がかからず、きちんと供養もされる」という安心感が、多くの方に受け入れられています。
無宗教・無檀家でも受け入れられる柔軟な選択肢
従来のお墓は、寺院に属する檀家でなければ建てられない、あるいは特定の宗派の信仰が前提となる場合が少なくありませんでした。しかし近年は、宗教や宗派にこだわらない、誰でも利用できる永代供養墓が増加しています。
これにより、たとえば次のような方でも安心して利用できます。
- 宗派にとらわれたくない
- 檀家制度を避けたい
- 親族間で宗教的な意見が分かれている
時代に合った「自由な供養のかたち」として、永代供養の受け皿が広がっていることも、人気の理由です。
地方の過疎化と都市部への人口集中
都市部に住む人が増える一方で、地方の墓地は管理されずに荒れていくという現象が全国的に問題になっています。実家のお墓が遠方にあり、アクセスが悪いため、物理的にお参りが困難になるケースも後を絶ちません。
こうした地理的な問題からも、「お参りに行けないなら、管理はお寺にまかせたい」「実家のお墓を閉じて、もっと通いやすい場所に改葬したい」という理由で永代供養が選ばれています。

このように、永代供養の普及は一過性の流行ではなく、社会の在り方そのものの変化に深く結びついた選択肢です。「家族の負担を減らしたい」「自分自身の最期を整えておきたい」と願う方にとって、永代供養は安心と合理性を両立した、現代的な供養の形といえるでしょう。
墓じまいと永代供養を後悔しないためのポイント
墓じまいや永代供養は、一度進めてしまうとやり直しが難しい選択です。そのため、後悔やトラブルを防ぐためには、事前の準備や確認、関係者との丁寧なやりとりが欠かせません。ここでは、実際の相談現場でよく聞かれる「失敗した」「もっとこうしておけばよかった」という声をもとに、後悔しないために押さえておきたいポイントを具体的に解説します。
事前の情報収集と比較は念入りに行う
「他にもっと良い選択肢があったかもしれない」と後から感じる方の多くは、情報収集や比較が不十分だったケースです。特に永代供養の内容は施設ごとに大きな違いがあり、以下のような項目は事前に確認しておく必要があります。
- 納骨方法(個別管理か合祀か)
- 管理期間(何回忌まで個別か)
- 年間管理費の有無
- 法要の頻度や内容
- お参りのしやすさ(立地・アクセス)
インターネット上の情報だけで判断せず、できれば現地を見学し、担当者の対応や雰囲気も含めて比較検討しましょう。
寺院や管理者との関係は「感情」も大切に
墓じまいや永代供養は、形式上は「契約」や「手続き」ですが、相手が人である以上、感情的なやり取りも発生します。特に檀家として長年お世話になったお寺に墓じまいを申し出る際は、敬意と感謝の気持ちを持って丁寧に伝えることが大切です。
いきなり「墓じまいします」と一方的に伝えるのではなく、「やむを得ない事情で考えざるを得なくなった」こと、「これまでお世話になったことへの感謝」を真摯に伝えることで、円満に進めやすくなります。円滑なやりとりができれば、離檀料などの費用面でのトラブルも避けやすくなります。
親族間の意見調整は最優先で行う
親族の誰かが強く反対していたにもかかわらず、話し合いが不十分なまま進めた結果、長くしこりが残ってしまったという事例は少なくありません。墓じまいは一族全体に関わるデリケートな問題であり、親族内での意見が分かれることも珍しくありません。
話し合いの場では、「なぜ墓じまいを考えているのか」「永代供養を選ぶ理由」「将来どんな形で供養していきたいのか」を丁寧に説明し、時間をかけて納得を得るように努めましょう。どうしても意見が割れる場合は、分骨や別々の供養方法を選ぶことも可能です。
書類や費用のトラブルを防ぐための確認を
墓じまいや永代供養では、多くの書類提出や費用の支払いが発生します。とくに以下のような項目は、事前に明確にしておくと安心です。
- 墓石撤去・運搬の作業内容と金額(詳細な内訳まで)
- 離檀料やお布施の金額と相場
- 改葬許可証の取得スケジュール
- 永代供養先との契約内容(契約期間・合祀のタイミングなど)
不明点はそのままにせず、見積書や契約書の確認を行いましょう。口約束だけで進めず、書面での記録を残しておくことが大切です。
実際の事例や利用者の声も参考に
インターネットや資料請求で得られる情報だけでなく、実際に墓じまいや永代供養を経験した方の体験談は大きな参考になります。たとえば以下のような口コミは、判断に役立つポイントです。
- 「最初に見積もった金額と最終金額が違った」
- 「遠方の施設にしたら、お参りに行けず後悔している」
- 「最初に家族でよく話し合っておいてよかった」
可能であれば、地域の相談窓口や終活セミナー、石材店などでリアルな体験談を聞くことも検討してみてください。

墓じまいや永代供養は、心の区切りでもあり、人生の節目ともいえる大切な選択です。情報不足や準備不足のまま進めてしまうと、あとから「こんなはずじゃなかった」と悔やむことにもなりかねません。だからこそ、「焦らず・丁寧に・周囲と協力して」進めていくことが、もっとも大切なポイントです。自分たちにとって後悔のない供養のかたちを、しっかり見つけていきましょう。
まとめ|墓じまいと永代供養は違うけれど、つながっている選択肢
墓じまいと永代供養は、それぞれ目的や役割が異なる別々の行為です。墓じまいは「お墓を撤去して土地を返すこと」、永代供養は「お寺や霊園にご遺骨を託して供養・管理してもらうこと」です。一見すると別物に思えますが、実際には多くの方がこの2つをセットで考え、実行しています。
その背景には、家族構成や生活スタイルの変化があります。核家族化が進み、遠方に住む子どもたちがお墓を管理することが難しくなるなかで、「お墓を片づけたい」「でもきちんと供養はしたい」という想いが共存するようになりました。
墓じまいを行うと、当然ながらご遺骨の新たな納め先が必要になります。そこで、供養を継続できて、なおかつ子や孫に負担をかけない方法として、永代供養が選ばれているのです。
一方で、「墓じまいさえすれば供養は終わり」「永代供養を選べば全て安心」と安易に決めてしまうのは避けるべきです。それぞれにメリット・デメリットがあり、後から「やり直したい」と思っても難しい選択です。家族や親族とよく話し合い、供養のあり方を一緒に考えることが大切です。

墓じまいと永代供養は、違うからこそ補い合える選択肢です。今あるお墓をきれいに締めくくり、これからも心の中で供養を続けていく――その一歩を、冷静に、でもあたたかい気持ちで踏み出していきましょう。
平日10時~18時