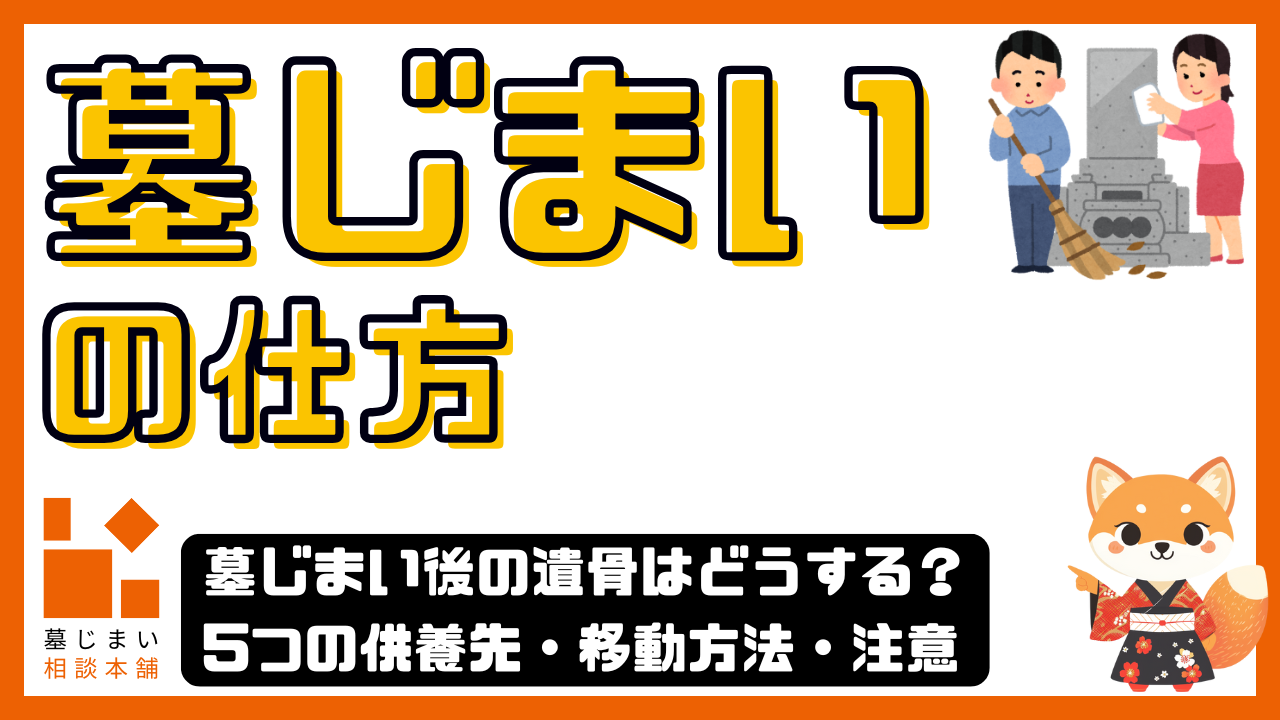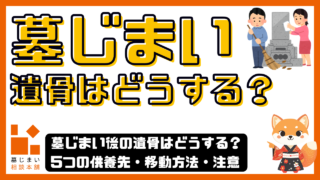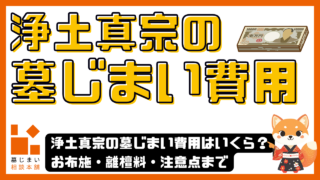本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいの仕方とは?|まずは全体像を把握しよう
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、埋葬されているご遺骨を別の場所へ移す一連の行為を指します。具体的には、お墓に納められている遺骨を取り出し、墓石を解体・撤去し、墓地を更地にして返還するまでの作業全体が「墓じまい」です。
この言葉は比較的新しく広まったもので、近年の核家族化や高齢化、少子化といった社会の変化を背景に、急激に認知されるようになりました。「自分の代でお墓を閉じたい」「子供に管理の負担をかけたくない」「遠方にある墓参りが困難」など、理由は多様ですが、共通しているのは「お墓の管理をこのままでは続けられない」という現実的な事情です。
墓じまいには法律上の手続きが伴います。単にお墓を撤去すれば済むというものではありません。たとえば、遺骨を移動するためには「改葬許可証」という公的な書類の取得が必須であり、関係機関や関係者との調整も必要です。また、寺院墓地であれば「離檀(りだん)」といって、菩提寺との関係を解消する際に感謝の意を込めたお布施(離檀料)が必要になる場合もあります。
さらに、墓じまい後のご遺骨をどうするかも重要な検討事項です。多くの方は永代供養墓や納骨堂、樹木葬などを選びますが、それぞれ費用や管理体制、宗派の有無など条件が異なります。希望に沿った場所を見つけるには事前の情報収集が欠かせません。
墓じまいの流れを正しく理解しないまま進めると、親族間のトラブルや寺院との誤解、手続きの不備による申請却下といった問題が起こり得ます。そのため、まずは全体像を把握し、どのような準備と対応が必要なのかを冷静に整理することが大切です。
墓じまいは単なる「物理的な撤去」ではなく、「供養の形を変える」という精神的な意味も含んでいます。これまで先祖代々守ってきたお墓に感謝を伝え、これからの時代に合った供養のスタイルへと丁寧に移行していく――それが墓じまいの本質です。

正しい知識を持ち、必要なステップを一つずつ確認しながら進めれば、墓じまいは決して難しいものではありません。自分や家族の事情に合った方法で、後悔のない選択をしていくことが大切です。
墓じまいの仕方【7つの手順でわかりやすく解説】
墓じまいは、一つひとつの手順を丁寧に進めることが大切です。この章では、実際に墓じまいを行う際に必要な7つのステップをわかりやすくご紹介します。終活を考える方やそのご家族が安心して進められるよう、実務的なポイントと注意点を交えて解説します。
1. 親族に相談・同意を得る
まず最初に行うべきは、親族への相談です。墓じまいはご先祖様に関わる大切な問題ですので、関係する親族全員の理解と同意を得ることが不可欠です。とくに兄弟姉妹、叔父叔母など広い範囲の親族と話し合い、納骨方法や費用分担などもこの段階でしっかり共有しておくと、後のトラブルを防げます。
2. 新しい納骨先を決める(永代供養など)
遺骨の移動先を決めてからでないと、墓じまいの申請手続きができません。選択肢としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養などがあります。子や孫の負担にならないこと、宗派を問わないか、アクセスしやすいかといった観点で検討しましょう。決定したら「受入証明書」を発行してもらいます。
3. 墓地管理者に連絡し必要書類を取得
現在の墓地を管理している寺院や霊園に墓じまいの意思を伝え、埋葬されている証明書である「埋葬証明書」を発行してもらいます。菩提寺の場合、離檀の相談も必要です。このときに離檀料の相場(5万〜20万円程度)についても確認しておくと安心です。
4. 改葬許可申請書を用意・提出する
墓じまいには法律に基づいた行政手続きが必要です。市区町村役場から「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入したうえで、「埋葬証明書」「受入証明書」とあわせて提出します。書類に不備があると再提出が必要になるため、チェックリストを使って確認しながら準備しましょう。
5. 閉眼供養を行い遺骨を取り出す
閉眼供養とは、お墓に宿った故人の魂を抜いて成仏させるための儀式です。菩提寺の住職に依頼し、親族が集まり読経を行った後、ご遺骨を丁寧に取り出します。お布施の目安は3〜5万円ほどで、当日までに準備しておきます。お墓の掃除や仏花・線香の用意も忘れずに行いましょう。
6. 墓石を撤去して更地に戻す
墓石の解体・撤去は、通常は専門の石材店に依頼します。あらかじめ見積りを取り、複数社で比較すると費用を抑えられる場合もあります。作業が完了した後は、墓地の原状回復がされているか確認しましょう。自治体によっては立ち会いを求められる場合もあります。
7. 新しい場所に納骨・供養する
改葬先に遺骨を納め、供養を行います。永代供養墓などでは、合同法要を行う施設も多く、申し込み時に納骨法要の有無や日程を確認しておくとスムーズです。散骨や手元供養を選んだ場合でも、故人への感謝を込めた小さな儀式を行うと心の区切りになります。

これらの手順を一つずつ着実に進めていくことで、心残りのない墓じまいが実現できます。不安な場合は、墓じまい専門の代行サービスに相談するのも一つの方法です。
墓じまいの手順でよくある注意点とトラブル例
墓じまいは「ただお墓を片付ける作業」ではありません。ご先祖様の魂を敬いながら、複雑な手続きや費用の調整を進める必要があるため、さまざまな注意点やトラブルが発生しやすいのが現実です。ここでは、実際によくある事例をもとに、事前に知っておきたい注意点と回避策をご紹介します。
親族間の意見が割れて話が進まない
もっとも多いトラブルが「親族間の合意形成」です。とくに、地方にお墓がある場合や代々の墓を守ってきた家系の場合、「勝手に決めるな」と反発を受けることがあります。また、遺骨の扱いや費用分担を巡って揉めるケースも少なくありません。
対策:
初期段階で関係者全員と丁寧に話し合いを行いましょう。正式な文書(同意書)にまとめて署名してもらうことで、後の言った言わないのトラブルを防げます。
菩提寺との関係で「離檀料」でもめる
寺院墓地にお墓がある場合、「離檀(檀家をやめる)」という手続きが必要です。この際に、離檀料として高額な費用を求められたり、説得を受けてなかなか離檀できないという声も多く寄せられています。
対策:
離檀の意思はできるだけ早めに住職へ伝え、丁寧に理由を説明しましょう。事前に地域相場を調べて、相場以上の金額を求められた際には第三者(自治体や消費生活センターなど)に相談することも選択肢です。
改葬許可の書類に不備があった
改葬には自治体から「改葬許可証」を取得する必要がありますが、添付書類(埋葬証明書や受入証明書)に不備があると、申請が却下されてしまうことがあります。とくに、提出先と発行元が異なる場合や記載内容にズレがあると差し戻されることもあります。
対策:
提出前にチェックリストを使って記入漏れや記載ミスがないか確認しましょう。不安な場合は、自治体の窓口に事前相談するのが安心です。
石材店とのトラブル(追加費用・工事不備など)
墓石の撤去を依頼したあとで、見積もりにない追加費用を請求されたり、工事完了後の現地が荒れたままになっているといったトラブルもあります。悪質な業者に依頼してしまうと、撤去後の処分証明書を出してもらえないことも。
対策:
複数社から見積もりを取り、口コミや実績を確認したうえで契約するようにしましょう。また、撤去前後の写真撮影を依頼することで、工事の品質確認にも役立ちます。
納骨後に「やっぱり手元に戻したい」と後悔
永代供養や合祀墓などに納骨したあと、「思った以上に距離が遠くてお参りできない」「家族の了承を得ていなかった」などの理由で後悔するケースもあります。合祀後は遺骨を個別に取り出すことができなくなるため、慎重な判断が求められます。
対策:
現地の見学を必ず行い、アクセスや雰囲気を自分の目で確認しましょう。また、納骨前に家族全員で意見をすり合わせておくことが重要です。
墓じまい後の気持ちの整理がつかない
手続きは完了しても、「本当にこれでよかったのか」「ご先祖様に申し訳ない」という気持ちを引きずる方も少なくありません。とくに、儀式やお別れの機会を設けずに終えてしまうと、心に区切りがつかないことがあります。
対策:
閉眼供養や納骨式を丁寧に執り行い、家族で手を合わせる機会をつくることが、気持ちの整理につながります。形にこだわらなくても、自宅での手元供養やメモリアルスペースを設けるのも一つの方法です。

これらの注意点をあらかじめ把握しておくだけでも、墓じまいにともなう不安やトラブルを大きく減らすことができます。事前準備と丁寧なコミュニケーションが、後悔のない墓じまいを実現するカギとなります。
墓じまいの費用と相場|自分でやる・業者に頼む場合
墓じまいにはさまざまな費用がかかりますが、内容を正しく理解すれば無駄な出費を避け、納得のいく選択ができます。このセクションでは、自分で手続きを進める場合と業者に依頼する場合に分けて、具体的な費用の内訳と相場をご紹介します。
自分でやる場合の主な費用と相場
自分で墓じまいを行うと、費用は比較的抑えられますが、そのぶん労力と時間がかかります。以下は必要となる主な費用項目です。
| 項目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 閉眼供養のお布施 | 3万〜5万円 | 僧侶にお経をあげてもらう儀式。御車代・御膳料が別途必要なことも |
| 離檀料(寺院墓地の場合) | 5万〜20万円 | 菩提寺との関係を解消する際のお布施。金額は地域差が大きい |
| 改葬許可申請の費用 | 0円〜 | 申請自体は無料だが、郵送や証明書の取得に数百円〜数千円程度 |
| 墓石の撤去・処分費 | 10万〜30万円程度 | 墓石の大きさや立地条件で変動。1㎡あたりの単価で見積もられることも |
| 遺骨の洗浄・運搬費 | 1柱あたり数千円〜1万円 | 古い骨壺の場合は洗骨・新しい容器への移し替えが必要なことも |
| 新たな納骨先の費用 | 5万〜50万円以上 | 永代供養墓、納骨堂、樹木葬など種類によって大きく異なる |
合計で見積もると、自分で手続きを進めた場合の費用は30万〜70万円前後が目安となります。
業者に依頼する場合の費用とサービス内容
自分での手続きに不安がある方は、墓じまい専門の業者や石材店に依頼するのも一つの方法です。費用は高くなりますが、代行サービスの内容によっては精神的な負担が大きく軽減されます。
| サービス内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 墓じまい一式パック(手続き代行・墓石撤去含む) | 20万〜50万円 |
| 書類取得・改葬許可申請代行 | 2万〜5万円 |
| 僧侶手配・閉眼供養代行 | 3万〜8万円(お布施込み) |
| 遺骨の引き取り・納骨先への移送 | 1柱あたり5千〜1万円程度 |
| 散骨・合祀・永代供養手配 | 3万〜30万円(内容により変動) |
一式で依頼した場合、40万〜100万円前後になることが多いですが、「追加料金なし」「撤去後の写真付き報告書あり」など安心できるサービスを選ぶことが重要です。
費用を抑えるための工夫ポイント
- 複数の業者に見積もりを依頼する:相見積もりを取ることで、過剰請求を防ぎ、相場感がつかめます。
- 公営墓地や自治体の補助金制度を活用する:地域によっては墓じまい費用の一部を助成している場合があります。事前に役所で確認しましょう。
- 遺骨の一部を手元供養にする:改葬先の費用を抑えつつ、気持ちの面でも納得できる供養方法です。
- 閉眼供養と墓石撤去を同日に行う:僧侶と石材店のスケジュール調整が必要ですが、訪問回数が減るぶん費用も抑えられます。

墓じまいの費用は、選ぶ方法や業者によって大きく変わります。「何にどれだけかかるのか」を事前に把握し、家族とよく相談したうえで進めることが、納得のいく墓じまいにつながります。
書類の書き方と入手方法|改葬許可申請書とは?
墓じまいを行う際、最も重要な手続きのひとつが「改葬許可申請書」の提出です。この申請書がなければ、遺骨を現在の墓地から新しい納骨先に移すことは法律上できません。つまり、改葬許可申請書は“墓じまいのカギ”ともいえる存在です。
改葬許可申請書とは何か?
改葬許可申請書とは、現在の墓地に埋葬されている遺骨を、別の場所へ正式に移動(=改葬)するための申請書類です。厚生労働省が定める「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、墓地がある自治体(市区町村)に提出し、改葬許可証を発行してもらう必要があります。
この書類は、行政手続き上の形式を満たしていることはもちろん、遺骨が適切な形で移動されることを担保するためのものです。不正な遺骨の移動や無縁墓の発生を防ぐためにも、必ず提出が求められます。
改葬許可申請書の入手方法
改葬許可申請書は、以下のいずれかの方法で入手できます。
- 役所の窓口でもらう:直接市区町村役場へ出向いて申請書を受け取る方法です。不明点をその場で職員に質問できるというメリットがあります。
- 自治体のホームページからダウンロード:多くの自治体ではPDF形式の申請書を公開しており、自宅で印刷して記入できます。
- 郵送で取り寄せる:遠方に住んでいる場合や高齢者の方にとっては、郵送での取り寄せが便利です。封筒に返信用封筒と切手を同封して依頼します。
どの方法であっても、改葬元の自治体で発行された様式を使用することが大切です。引越し先の自治体の様式では受理されないので注意しましょう。
書類の記入例と注意点
改葬許可申請書に記載する主な項目は以下の通りです。
- 申請者の氏名・住所・電話番号
- 現在の墓地の所在地・墓地名
- 改葬する遺骨の情報(氏名、埋葬日、続柄など)
- 改葬先の名称・所在地
- 改葬の理由(「お墓の老朽化」「墓守がいないため」など簡潔で問題ありません)
記入時は黒のボールペンまたは万年筆を使用し、間違えた場合は修正テープや二重線ではなく、役所で新しい申請書をもらいましょう。誤記があると受付を断られることがあります。
添付が必要な書類一覧
改葬許可申請書と一緒に、以下の書類を添付して提出します。
| 書類名 | 入手先 | 用途 |
|---|---|---|
| 埋葬証明書 | 現在のお墓の管理者(寺院や霊園) | 遺骨が埋葬されていることの証明 |
| 受入証明書 | 新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂など) | 遺骨を受け入れることを証明 |
| 身分証明書の写し | 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど) | 本人確認用として |
なお、遺骨が複数ある場合は、1体につき1通の改葬許可申請書が必要になります。また、家族であっても埋葬者と申請者が異なる場合には、戸籍謄本や委任状が求められるケースもあります。
提出から改葬許可証の発行までの流れ
- 必要書類を揃え、役所に提出(窓口または郵送)
- 内容の確認と審査(数日〜1週間程度)
- 問題なければ、改葬許可証が発行される
- 改葬許可証を持って、墓石の解体や納骨の手続きへ進む
改葬許可証は遺骨1体につき1通が発行され、新しい納骨先に提出することで、正式に納骨が認められます。万が一、紛失してしまった場合は再発行が必要になるため、発行後は大切に保管してください。

改葬許可申請書の提出は、一見すると煩雑に感じられますが、手順を丁寧に踏めば難しくはありません。高齢の親世代のために手続きを代行する子世代も増えています。家族の負担を減らすためにも、余裕を持って準備を進めましょう。
墓じまいの仕方に迷ったら?代行サービスという選択肢
墓じまいには、親族との話し合いや寺院との交渉、自治体への書類提出、石材店とのやり取りなど、慣れない作業が数多くあります。初めての経験で手探り状態のなか、すべてを自力でこなすのは精神的にも体力的にも負担が大きく、「どこから手をつけていいかわからない」と感じる方も少なくありません。
そのようなときに検討したいのが、墓じまい専門の代行サービスです。複雑な工程をプロが代わりに進めてくれるため、手続きの不安や時間的な制約を大きく軽減できます。
墓じまい代行サービスとは?
墓じまい代行サービスとは、専門の業者が墓じまいに必要な各種手続きを一括で引き受けてくれるサービスです。サービス内容は業者によって異なりますが、一般的には以下のような作業をカバーしています。
- 墓地管理者との交渉(埋葬証明書の取得など)
- 改葬許可申請書の作成・提出代行
- 閉眼供養の僧侶手配
- 墓石の撤去・更地戻し
- 遺骨の洗浄・運搬・新たな供養先への納骨手配
- 写真付き報告書の作成
- 永代供養・樹木葬・散骨など新しい供養方法の紹介・手配
こうした一連の流れをプロに任せることで、事務的な負担が軽くなるだけでなく、手続きミスやトラブルのリスクも最小限に抑えることができます。
どんな人に向いている?
墓じまいの代行サービスは、次のような方に特に適しています。
- 自分で役所や寺院に連絡するのが難しい高齢者
- お墓が遠方にあって現地に何度も行けない方
- 忙しくて書類や手配に時間を割けない方
- 手続きに不安があり、プロのサポートを受けたい方
- 家族や親族の了承は得たが、自力での進行に限界を感じている方
特に、高齢の親の代わりに手続きを進める子世代が増えており、事務処理から現場対応までワンストップで任せられる安心感は大きな魅力です。
信頼できる代行業者の選び方
代行サービスを利用する際には、信頼できる業者を見極めることが重要です。選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 墓じまい専門の実績が豊富で、口コミや評判がよい
- 見積もりが明確で「追加料金なし」と明記されている
- 改葬許可証や各種書類の取得サポートが含まれている
- 施工後の写真や報告書などを提供してくれる
- 永代供養墓や納骨堂との提携実績がある
- 石材店・僧侶との調整も一括対応できる
特に注意したいのは、安さだけで選ばないことです。見積りには入っていない「運搬費用」や「供養代」があとから請求されるケースもあるため、契約前にすべての費用項目を確認しましょう。
気になる費用感は?
墓じまい代行サービスの費用は、内容や地域によって異なりますが、おおよそ以下のような相場が目安です。
| サービス内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 書類手続き代行 | 3万〜5万円 |
| 閉眼供養の僧侶手配 | 3万〜8万円(お布施込み) |
| 墓石撤去・更地戻し | 10万〜30万円(規模による) |
| 遺骨の運搬・納骨先手配 | 5万〜15万円 |
| 永代供養墓の納骨 | 10万〜30万円程度 |

すべてをセットにしたパッケージプランを提供している業者も多く、相場はおおよそ40万〜80万円前後です。必要な作業だけを選んで依頼できる「部分代行」もあり、予算に合わせた柔軟な対応も可能です。
自分だけで抱え込まず、プロの力も選択肢に
墓じまいは一生に一度あるかないかの大切な節目ですが、決して一人で無理に進める必要はありません。大切なのは、ご先祖様をきちんと供養し、家族にとって納得のいく形で完了させることです。
「何から始めればいいのか分からない」「できる限りスムーズに終えたい」という方にとって、代行サービスは非常に心強いパートナーとなります。信頼できる業者を選べば、精神的な負担も大きく軽減できるでしょう。
自分たちの事情に合った方法を選び、無理なく、後悔のない墓じまいを実現してください。
よくある質問Q&A|墓じまいの不安を解消しよう
墓じまいを考えている方やそのご家族からは、多くの不安や疑問の声が寄せられます。ここでは、実際によくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。手続きや供養に関する不安を少しでも軽くできるよう、実務と心情の両面から丁寧にお答えします。
Q1. 墓じまいにかかる期間はどのくらい?
一般的には2〜3ヶ月程度かかるケースが多いです。ただし、寺院とのやり取りや役所の対応、新しい納骨先の手配状況によって前後します。寺院墓地の場合は、離檀の話し合いに時間を要することもありますので、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
Q2. 墓じまいに親族全員の同意は必要?
法律上、必ずしも全員の同意が必要というわけではありません。ただし、のちのちのトラブルを避けるためには、できるだけ関係者全員に説明し、理解を得てから進めるのが望ましいです。とくに兄弟姉妹間や長男・長女など立場が異なる場合は、話し合いを丁寧に行いましょう。
Q3. 墓じまい後、遺骨を自宅で保管しても大丈夫?
はい、自宅での保管(手元供養)は法律上問題ありません。ただし、土葬や庭への埋葬は法律で禁止されています。室内で骨壺や専用の保管容器を用いて、湿気の少ない場所に安置するようにしてください。将来的には永代供養などへの移行を前提に保管する方が多いです。
Q4. 改葬許可証は代理で取得できる?
可能です。家族が高齢で手続きが難しい場合など、親族が代理で申請できます。ただし、自治体によっては委任状や本人確認書類のコピーの提出を求められる場合があります。事前に申請先の市区町村へ確認しておきましょう。
Q5. 墓じまいはどの季節に行うのがベスト?
特に決まった時期はありませんが、春や秋は気候も安定しており、閉眼供養や撤去作業を行いやすい時期とされています。反対に、お盆やお彼岸は僧侶や業者の繁忙期にあたるため、日程が取りづらくなる傾向があります。早めに予定を立てて調整するのがおすすめです。
Q6. 閉眼供養に親族全員の出席は必要?
出席者に決まりはありません。故人と縁が深かった家族や代表者のみの参加でも問題ありません。大切なのは、心を込めて供養を行うことです。参加できない方には、後日ご挨拶や写真を送るなどして気持ちを伝えると丁寧です。
Q7. 離檀料は必ず支払う必要がありますか?
必須ではありませんが、菩提寺との関係を円満に終えるために感謝の気持ちとしてお渡しするのが一般的です。金額は決まっていないため、相場を調べた上で無理のない範囲で包みましょう。対応に不安がある場合は第三者機関に相談するのも一つの方法です。
Q8. 自治体の補助金は誰でももらえますか?
すべての自治体で実施しているわけではありませんが、一部の市町村では墓じまいに対する助成金制度があります。条件として「市内在住者」「特定の霊園」などが定められていることも多いため、役所の窓口やホームページで確認することが必要です。
Q9. 納骨堂や永代供養墓でも供養は続けられる?
はい、多くの納骨堂や永代供養墓では、年に数回の合同法要や個別の供養の機会が設けられています。宗派を問わず利用できる施設も増えており、アクセスしやすい都市部に立地しているケースもあります。供養のスタイルは多様化しており、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。
墓じまいは、大切な家族やご先祖様の供養のかたちを見直す機会でもあります。不安や疑問を一つひとつ解消しながら、納得のいく選択をしていくことが、後悔しない墓じまいにつながります。わからないことがあれば、役所や専門業者への相談も積極的に活用しましょう。