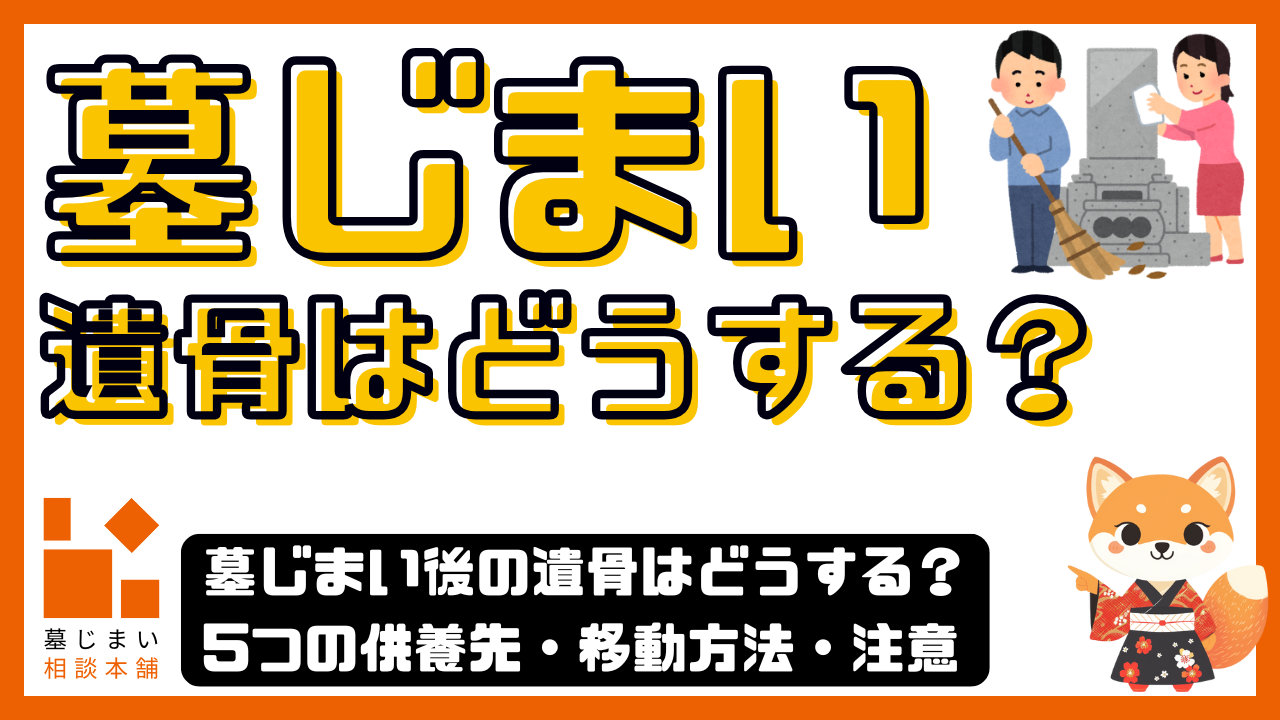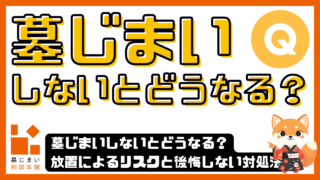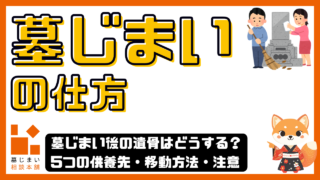本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまい後、遺骨はどうなる?最初に知っておくべきこと
墓じまいとは、お墓を撤去し、そこに納められている遺骨を新しい場所に移すことです。
単にお墓を処分するだけでは終わらず、「遺骨をどのように供養するか」をきちんと決めておく必要があります。墓石は石材店に引き取ってもらうことができますが、遺骨だけはご家族で責任を持って供養先へ移動させなければなりません。
勝手な処分は法律違反にあたる可能性も
遺骨は「人の遺体の一部」として法的に扱われており、勝手に捨てたり、山や川に埋めたりする行為は「遺棄罪」に問われる恐れがあります。たとえ不要になったと感じたとしても、遺骨は大切な故人の一部。必ずしかるべき方法で供養を行いましょう。
墓じまい=「遺骨の移動」がセットで必要
お墓の管理が難しくなったからといって、墓石だけを撤去して終わりにすることはできません。墓じまいは「お墓を閉じる手続き」と「遺骨を新たな供養先へ移す手続き」がセットになって初めて成立します。逆に言えば、遺骨の行き先が決まらない限り、墓じまいの計画は前に進みません。
まず「どこに遺骨を移すか」を家族で話し合う
遺骨の移動先にはいくつかの選択肢がありますが、どの方法にも特徴や費用、宗教的な意味合いがあります。家族の思いやライフスタイル、経済的な状況などを考慮しながら、どの供養方法が最もふさわしいかを話し合うことが大切です。
特に親が高齢であったり、子どもが遠方に住んでいたりする場合、「誰が供養を続けていくのか」という視点も忘れてはいけません。全員が納得した上で遺骨の行き先を決めておくことで、のちのトラブルや後悔を防げます。
遺骨の行き先を決めてから墓じまいを進める
墓じまいを業者に依頼する前に、必ず新しい納骨先を決めておきましょう。石材店や霊園では遺骨の一時預かりを行っていないのが一般的です。新しい供養先が決まっていないまま遺骨を取り出すと、家の中で保管せざるを得ず、トラブルや不安の種になりかねません。

「墓じまいの第一歩は、遺骨の行き先を決めること」――これが最も大切なポイントです。しっかりと準備をしておくことで、心穏やかに次の供養へ進むことができます。
遺骨の新しい供養方法|5つの選択肢と費用目安
墓じまいを行ったあと、取り出した遺骨は必ず新しい供養先に移す必要があります。ここでは、代表的な5つの供養方法と費用の目安をご紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあり、家族構成や経済状況、故人への思いによって適した方法が異なります。
永代供養墓|後継者がいなくても安心して任せられる
永代供養墓とは、寺院や霊園が遺族に代わって供養・管理をしてくれるお墓のことです。墓参りが難しい家庭や、継承者がいない方に選ばれています。個別に供養される期間の後、他の方と一緒に合祀されるケースが一般的です。
費用の目安:10万円〜50万円前後(合祀の場合)/30万円〜150万円前後(個別安置期間あり)
維持費が不要なため、一度支払えば追加費用が発生しにくいのが特徴です。ただし、合祀されると遺骨の取り出しはできなくなるため、事前に家族の同意を得ておくことが大切です。
散骨|自然へ還すという新しい選択肢
粉骨(遺骨を細かく粉砕)したうえで、海や山などに撒く供養方法です。自然志向の方や、お墓を持ちたくないという希望がある方に人気があります。
費用の目安:5万円〜20万円前後(業者による委託散骨の場合)
故人が好きだった海へ撒く「海洋散骨」や、山林への「山林散骨」など、希望に応じて選べます。法律的に禁止されているわけではありませんが、近隣住民や環境への配慮が求められるため、専門業者に依頼するのが安心です。
手元供養|いつでも身近に感じられる供養スタイル
遺骨の一部または全部を自宅で保管し、日々手を合わせて供養する方法です。ミニ骨壺やメモリアルペンダントなど、コンパクトな供養用品が多く用いられます。
費用の目安:3万円〜10万円前後(骨壺・アクセサリー代など)
物理的に近くに遺骨があることで心の安定につながる一方、家族間で「自宅に遺骨を置くことへの賛否」が分かれる場合があります。また、自身の死後にどうするかという問題もあるため、後継者とよく相談したうえで選びましょう。
納骨堂・新しいお墓|アクセス重視の現代的な選択
屋内施設に遺骨を安置する「納骨堂」や、新たに墓地を購入して建てる「新しいお墓」も選択肢の一つです。交通アクセスが良い立地に多く、天候に左右されずお参りできる点が支持されています。
費用の目安:納骨堂=20万円〜80万円前後/新しいお墓=60万円〜200万円前後
納骨堂は屋内で管理がしっかりしており、エレベーター付きの施設もあります。新しいお墓を建てる場合は自由度が高い反面、費用はやや高めになる傾向があります。
分骨|家族でそれぞれに供養する柔軟な形
1人分の遺骨を複数に分けて、それぞれの場所で供養する方法です。たとえば「一部は永代供養墓へ、一部は手元に」「親戚ごとに分けて納骨する」など、家族の事情に応じた柔軟な供養が可能です。
費用の目安:分骨自体は無料〜数千円(分骨証明書取得・容器代など)+各供養方法の費用
分骨を行う場合は、墓地管理者や火葬場で「分骨証明書」の発行を受ける必要があります。適切な手続きを行えば法律上の問題はありませんが、仏教的に否定的な考えを持つ寺院もあるため、事前に確認しておきましょう。

供養方法は一度選んだらやり直しが難しいものもあります。それぞれの特徴や費用、家族の思いを踏まえて納得のいく供養先を決めることが大切です。
遺骨の移動方法|車・郵送・納骨代行など3つの手段
墓じまいで遺骨を取り出した後、新しい供養先へどのように移動させるかは、多くの方が悩むポイントです。移動方法を誤ると、思わぬトラブルや手間が発生することもあるため、事前にそれぞれの方法と注意点を把握しておくことが重要です。ここでは、代表的な3つの移動手段について詳しくご紹介します。
自家用車や公共交通機関での持参
もっともシンプルで費用もかからないのが、自分で遺骨を運ぶ方法です。車があれば安全かつ他人の目を気にせず移動できます。公共交通機関を使う場合も、特別な制限はないため持ち込みは可能です。
ただし、骨壺は割れ物であり、衝撃にも弱いため、必ず緩衝材(新聞紙・プチプチなど)で包み、ダンボール箱に収めて持ち運びましょう。見た目が気になる場合は風呂敷などで包むとよいでしょう。電車やバスを利用する際は、座席の下や膝の上など目立たない場所に置くなど、周囲への配慮も忘れずに行うことが大切です。
ゆうパックによる郵送(送骨)
遠方の納骨先に遺骨を送りたい場合は、日本郵便の「ゆうパック」を利用すれば、遺骨を郵送することが可能です。ただし、どの配送業者でも扱っているわけではなく、ヤマト運輸や佐川急便などでは受け付けていないため注意が必要です。
ゆうパックで遺骨を送る場合は、以下の点をしっかり確認しましょう。
- 骨壺内の水分を除去する:納骨堂や地中にあった骨壺には、湿気や結露により水が溜まっていることがあります。梱包前にしっかりと乾燥させてください。
- 蓋の固定:骨壺の蓋が外れないよう、ガムテープでしっかりと留めましょう。
- 丁寧な梱包:新聞紙や緩衝材を使って骨壺を保護し、二重のダンボールで梱包するのがおすすめです。
また、送付先(寺院や納骨堂など)では遺骨の受け取りに対応していない場合もあるため、必ず事前に連絡・確認を取りましょう。
専門業者・NPO法人の納骨代行サービス
自身での持ち運びや郵送に不安がある方には、納骨代行サービスの利用が便利です。専門のNPO法人や業者が、遺骨の回収から新しい供養先への納骨までを一括で対応してくれるプランもあります。
このサービスでは、以下のようなサポートを受けられます。
- 送骨用の梱包キット(段ボール・緩衝材・申込書など)の送付
- ゆうパックでの遺骨発送サポート
- 合祀墓などへの納骨手続き代行
- 改葬許可証など、必要書類の確認支援
費用相場は3万円〜5万円前後とされており、「身寄りがなく手続きが難しい」「遠方のため移動が困難」といった方にも利用されています。サービス提供元によっては、故人の宗派に合わせた供養や法要も一緒に手配できる場合があり、柔軟に対応してもらえる点も魅力です。

遺骨の移動は、精神的にも肉体的にも負担の大きい作業です。ご自身やご家族の状況に応じて、無理のない方法を選ぶことが大切です。また、どの手段を選ぶ場合でも、「遺骨は大切な存在である」という意識を忘れず、丁寧に扱うことが何よりの供養となります。
墓じまいで遺骨を取り出すときの注意点
墓じまいでは、遺骨の取り出し作業が最も大切な工程の一つです。遺骨の扱いを誤ると、精神的な後悔や親族間のトラブル、法的な問題にまで発展する恐れがあります。ここでは、取り出しの際に気をつけたいポイントを詳しく解説します。
閉眼供養は必要かどうか事前に確認を
閉眼供養(へいがんくよう/魂抜き)は、墓石や納骨室に宿ったご先祖様の魂を抜くための儀式です。地域の慣習や宗派によって必要性が異なりますが、多くの石材店や僧侶は「必ず行ってから遺骨を取り出すべき」としています。
儀式を省略した場合、遺骨の取り出しを断られるケースもあるため、事前にお寺や石材店と確認を取りましょう。特に菩提寺がある場合は、勝手に省略するとトラブルの原因になることがあります。
遺骨の取り扱いに関する親族への事前相談を忘れずに
遺骨の取り出しには、家族や親族の理解と同意が不可欠です。特に「墓じまい」の決断自体に対して抵抗を感じる人も少なくありません。
取り出した遺骨をどこに移すのか、自宅に一時保管するのか、いつ取り出すのかなど、事前に丁寧な説明をしておきましょう。
親族の一部が知らないまま事後報告になってしまうと、「なぜ勝手に遺骨を動かしたのか」と非難され、信頼関係にヒビが入る可能性もあります。
石材店や霊園では遺骨の一時預かりは原則不可
取り出した遺骨は、どこかへ保管または納骨する必要がありますが、石材店や霊園では基本的に一時預かりを行っていません。
そのため、新しい納骨先が未定のまま遺骨を取り出してしまうと、自宅で保管せざるを得なくなります。
衛生面や精神的な負担を考えると、事前に「納骨先が確定してから取り出す」という順番を守ることが重要です。
骨壺や遺骨が劣化している場合は洗骨・粉骨の検討を
長年土中や納骨堂に保管されていた骨壺の中には、湿気やカビで傷んでいることがあります。中には水がたまっていたり、臭いが発生している場合もあります。
そのような場合は、専門業者による「洗骨(遺骨の洗浄)」「乾燥処理」「粉骨(粉末化)」のサービスを活用することで、衛生的かつ安心して新たな供養先に納骨できます。
特に納骨堂や手元供養を選ぶ場合は、骨壺の見た目や状態を気にされる方も多く、洗骨はよく利用されています。
遺骨が土に還っている場合の対応
古いお墓や関西圏に多い「土葬に近い形」の納骨では、骨壺を使わずに直接土中に遺骨を埋めていることがあります。この場合、取り出す際には「土と遺骨を分ける」作業が必要になります。
取り出した骨は、さらしや布袋に包み、新しい骨壺に収めて移動・納骨するのが一般的です。対応に不安がある場合は、経験豊富な石材店に依頼することをおすすめします。
法的手続きは忘れずに
遺骨を別の納骨先へ移す場合には、自治体へ「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を取得しておく必要があります。改葬許可証がないと、新しい納骨先で受け入れてもらえない場合があるため注意しましょう。
また、郵送や納骨サービスを利用する際もこの改葬許可証の同封が求められるケースがあるため、必ず事前に準備しておきましょう。

遺骨の取り出しは、物理的な作業であると同時に、故人への敬意や家族への配慮が強く求められる繊細な工程です。一つ一つの手順を丁寧に確認し、心残りのない形で墓じまいを進めていきましょう。
よくあるQ&A|いらない遺骨は処分できる?法律との関係は?
墓じまいを進める中で、「すでに供養が済んでいる遺骨」や「関係が薄いご先祖の遺骨」をどうするか悩まれる方も少なくありません。特に「いらない遺骨」として処分を考える場合、法律や社会的なマナーの観点から慎重な判断が求められます。
遺骨を勝手に捨てると「遺棄罪」に問われる可能性あり
日本の刑法では、遺骨をみだりに遺棄・損壊・奪取する行為は「遺棄罪」として処罰の対象になります。たとえ悪意がなかったとしても、「山林や河川に埋める」「自宅のゴミと一緒に処分する」といった行為は、社会的・道義的にも大きな問題とされます。
刑法第190条には「遺骨等を損壊、遺棄した者は3年以下の懲役に処する」と明記されており、過去には駅のロッカーや公園に遺骨を放置したケースが刑事事件として扱われた事例もあります。
「いらない遺骨」も、必ずしかるべき形で供養を
遺骨がどうしても引き取り先のない場合でも、処分という表現ではなく「供養」という形で対応する必要があります。以下のような費用を抑えた供養方法を選ぶことで、法律にも心情にも配慮した解決が可能です。
- 合祀墓(ごうしぼ):他の遺骨と一緒に埋葬される供養方法です。費用は1体あたり数万円からで、永代供養がセットになっている施設が多くあります。一度合祀すると取り出せない点は要確認です。
- 委託散骨:業者に粉骨・散骨を一任する方法です。海洋散骨であれば費用は5万円前後から。無縁になりやすい遺骨の処理として選ばれることが増えています。
- NPO法人や自治体の支援制度:地域によっては、経済的な理由で供養が困難な家庭向けに、永代供養や共同墓地の無料または低額利用を提供しているケースもあります。
一時的に自宅で安置するのも合法
事情によりすぐに納骨できない場合、自宅での一時安置も違法ではありません。仏壇の近くや押し入れなどに、布で包んで丁寧に置いておく方も多くいます。供養の意思をもって安置する限り、問題視されることはありません。
ただし、長期間そのままにしておくと「管理できない遺骨」として親族間のトラブルに発展することもあります。可能であれば、早めに新しい納骨先を探すことをおすすめします。
判断に迷うときは霊園や寺院、専門業者に相談を
どうしても気持ちの整理がつかない場合や、法的な判断に自信がない場合は、寺院や霊園の管理者、または墓じまい専門の業者に相談してみましょう。近年は遺骨の扱いに関する無料相談を受け付けている団体も増えており、安心して供養を進められるサポート体制が整っています。

遺骨は物ではなく、大切な命の痕跡です。たとえ「いらない」と感じてしまったとしても、その扱いには最大限の配慮が必要です。正しい知識と穏やかな心で、納得のいく供養方法を見つけていきましょう。
まとめ|遺骨の行き先を決めてから「墓じまい」を進めましょう
墓じまいは、お墓の撤去だけでなく「遺骨をどのように供養するか」が本質です。多くの方が見落としがちですが、遺骨の行き先を決めないまま墓じまいを始めてしまうと、思わぬトラブルや心理的な負担を招くことがあります。
遺骨は法律上「尊重されるべきもの」として扱われ、処分には厳しい制約があります。そのため、新たな供養先を決めずに遺骨を一時保管するのは避けるべきです。石材店などに一時的に預けることもできないため、自宅で管理せざるを得ないケースでは保管方法や家族間の意見調整が問題になりがちです。
また、選ぶ供養先によって必要な費用や準備も変わってきます。たとえば永代供養墓であれば供養料が一括で発生し、散骨を選ぶなら粉骨や洗骨といった追加作業が必要になります。さらに、分骨や手元供養を希望する場合には、分骨証明書の取得など行政手続きが関わってくるため、計画段階から確認しておきましょう。
大切なのは、家族や親族とよく話し合いながら「自分たちにとって無理のない、納得できる供養の形」を見つけることです。現代では多様な選択肢が存在するからこそ、焦らず慎重に、気持ちの整理をつけながら一歩ずつ進めることが重要です。

遺骨の行き先が決まれば、墓じまいの計画もスムーズに進みます。安心して供養を続けていける環境を整えることこそが、故人への最も丁寧な「おくり方」といえるのではないでしょうか。