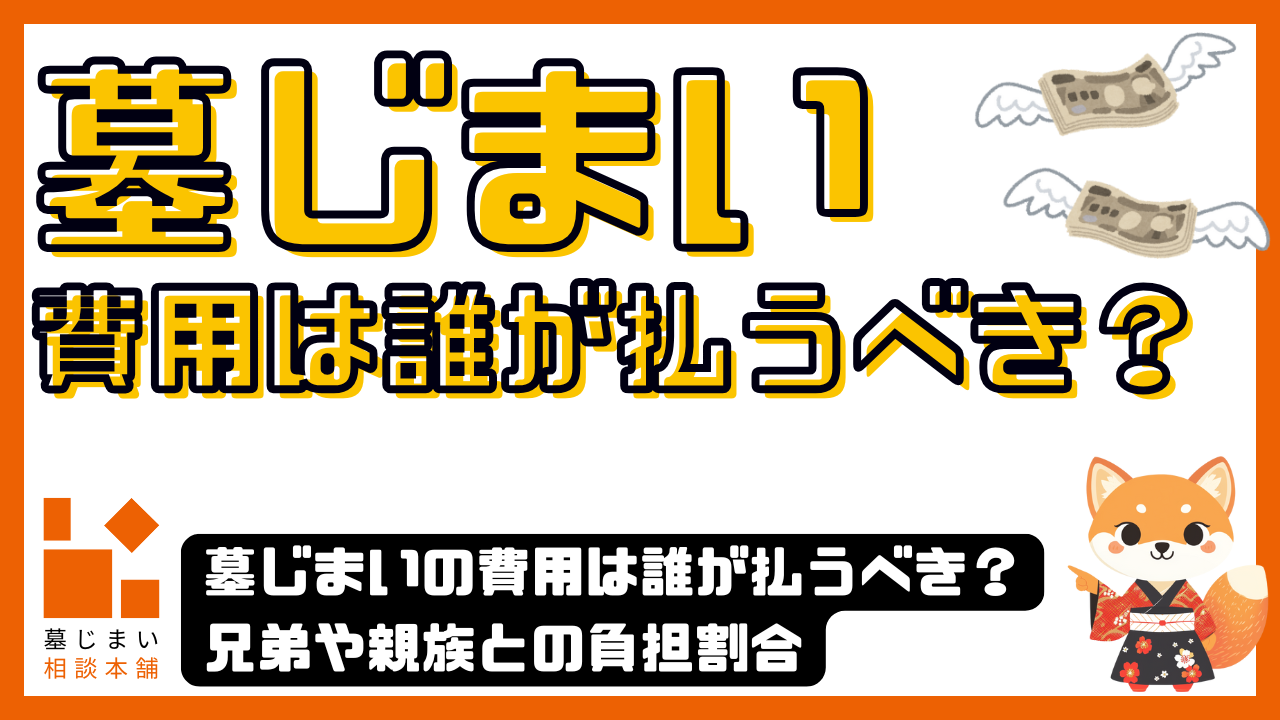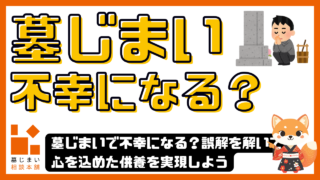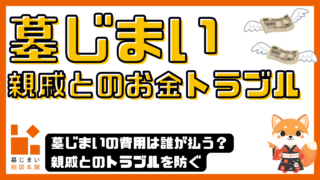本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまいの費用は誰が払う?|基本的な考え方
墓じまいを行う際、多くの方が最初に悩むのが「費用を誰が負担するべきか」という問題です。お墓を撤去して供養を移すには、撤去費用・改葬費用・魂抜きのお布施など、数十万〜百万円以上の費用がかかることも少なくありません。負担が大きいため、一人で抱え込むのではなく、家族や親族と分担できるのかを正しく理解することが大切です。
まず前提として、法律上「誰が支払わなければならない」という明確な義務はありません。一般的には、お墓を引き継いだ「祭祀承継者」が費用を負担するケースが多く見られます。祭祀承継者とは、お墓や仏壇などを引き継ぎ管理する人を指します。家系や宗派によっては長男が担うこともありますが、現代では家族の事情に応じて柔軟に決められています。
ただし、承継者一人にすべてを負担させる必要はありません。お墓は家族全体のつながりや供養の象徴でもあるため、家族で話し合って費用を分担することは決して珍しいことではないのです。実際には、長年お墓を守ってきた方が多めに負担したり、兄弟で均等に出し合ったり、遺産を多く受け取った人が費用を多く持つなど、さまざまな形があります。
また、費用の分担だけでなく「なぜ墓じまいをするのか」「どのような供養方法にするのか」といった価値観の共有も非常に重要です。費用だけの話になると不満や誤解を生みやすいため、ご先祖様への思いや供養のあり方を丁寧に伝えることで、家族の協力を得やすくなります。
近年では、墓じまいをきっかけに親族間のトラブルが起きる事例も増えています。特に費用負担の曖昧さは争いの原因になりやすいため、あらかじめ誰が何をどのくらい負担するかを話し合い、可能であれば書面に残しておくと安心です。

墓じまいは、物理的なお墓を閉じるだけではなく、家族で供養のあり方を見直す貴重な機会でもあります。誰が払うかという一点にとらわれすぎず、ご先祖様の供養を家族全体のものとして考えることが、納得感のある墓じまいにつながります。
墓じまいの費用を兄弟で分担するケース
墓じまいにかかる費用は、数十万円から場合によっては100万円以上にのぼることがあります。そのため、兄弟姉妹で協力して費用を分担するケースは少なくありません。特に、喪主を務めた長男やお墓の承継者がすべてを負担するのが難しい場合には、兄弟間での費用分担が現実的な選択肢となります。
実際には、兄弟それぞれの家庭状況や経済力、これまでのお墓への関わり方によって、分担の方法は多様です。たとえば、これまでお墓の掃除や管理を担ってきた兄が多めに出し、遠方に住む弟や妹は少額を負担するといった柔軟な分け方が行われています。ほかにも、均等に分担する「折半方式」や、遺産の相続割合に応じて費用を案分する方法もあります。
兄弟間で分担する際に重要なのは、事前に丁寧な話し合いを持つことです。特に、墓じまいというテーマはデリケートで感情的にもなりやすいため、「金額」だけでなく「気持ち」の面でも納得できる形を目指す必要があります。話し合いの場では、墓じまいを決めた理由や供養への想いをしっかり伝えることが、協力を得る第一歩になります。
話しづらさを感じる方は、まず「相談ベース」で切り出してみるとよいでしょう。たとえば「もし一部費用を分担してもらえるとしたら、どれくらいが現実的か」などと質問形式で聞くことで、相手に配慮を示しながら本音を引き出しやすくなります。
また、費用の負担割合や支払いのタイミングについては、後々のトラブルを避けるためにも書面に残しておくことが望ましいです。簡単なメモやLINEのやり取りでも記録が残っていれば、後日の誤解を防ぐ材料になります。

兄弟で費用を分け合うことは、ただの金銭的な協力にとどまりません。家族全員でご先祖様の供養に向き合う姿勢を示すことにもつながります。負担の重さに一人で悩まず、できる範囲で助け合うことで、納得のいく墓じまいを実現できるでしょう。
墓じまい費用を親族にもお願いしてよいのか?
墓じまいは、お墓の撤去費用や供養の移転費用など、まとまった出費が伴うため、家族内だけで負担するのが難しいと感じる方も多いです。こうした場合、兄弟姉妹以外の親族──たとえば叔父・叔母・いとこなどに費用負担を相談してもよいのか、不安を感じる方もいらっしゃいます。
結論から言うと、親族に費用の一部を相談することは決して非常識ではありません。ただし、配慮や誠意をもって説明することが非常に大切です。
まず考えておきたいのは、対象となる親族の故人との関係性です。たとえば、お墓に眠る方がその親族の実の兄弟姉妹であった場合や、長年お墓参りを共にしていたような関係であれば、一定の金額を相談することに納得を得られやすい傾向があります。一方で、関係性が希薄であった場合には、無理に負担を求めることは避け、あくまでも「ご厚意として援助をお願いする」という立場で伝えることが望ましいです。
伝え方のポイントは、「金額ありき」ではなく、「供養の思い」を先に共有することです。たとえば「父のお墓を無縁にせず、きちんと供養したいと思っています」といった想いを伝えた上で、「もし可能であれば、墓じまい費用の一部をお力添えいただけないでしょうか」といった表現にすることで、相手に配慮を感じてもらえます。
費用のお願いをする際は、具体的な金額や内訳も併せて説明すると、親族としても納得しやすくなります。たとえば「お墓の撤去費が〇万円、改葬先の永代供養費が〇万円、合計で〇〇万円ほどになります」と整理し、そのうちの一部について相談する形をとるとスムーズです。
また、どの範囲まで援助をお願いするかも明確にしておくと、話がこじれにくくなります。たとえば「魂抜きのお布施は当方で負担し、撤去費用の一部のみご相談させていただきたい」といった具体的な線引きを伝えると、トラブルの予防につながります。
親族にお願いをする際は、断られる可能性もあることを前提に、無理のない範囲でのご協力をお願いする姿勢を忘れないことが大切です。「負担してもらえなかった」ことに不満を感じるのではなく、あくまで助けてくれる可能性のある“協力者”として関係性を保つ意識が求められます。

親族から少額でも援助を得られれば、金銭的な助けになるだけでなく、皆でご先祖様を想う「供養の気持ち」も共有できます。墓じまいは、お墓を閉じる作業であると同時に、ご家族・ご親族との絆を再確認する機会でもあります。想いを丁寧に伝え、無理のない協力を得ながら進めていきましょう。
払えないときの選択肢と支援制度
墓じまいを考えていても、「費用が高くて今は難しい」と感じている方も少なくありません。実際、墓じまいには墓石の撤去費や改葬先の納骨費用、お布施などを含めて数十万~百万円以上かかることもあります。ですが、費用が払えないからといって諦める必要はありません。いくつかの現実的な選択肢や支援制度を活用することで、無理なく墓じまいを進めることができます。
自治体の補助金制度を確認する
一部の自治体では、墓じまいにかかる費用の一部を助成する補助金制度があります。たとえば、墓石の撤去費用や改葬に関する手続き費用が補助対象となる場合があります。支給額は数万円から20万円程度が相場で、地域によって条件や上限額が異なります。
補助金の対象となるには、以下のような条件が求められることがあります。
- 公営霊園や市営墓地にあるお墓であること
- 墓石の撤去が完了していること
- 墓地使用料や管理料の滞納がないこと
- 改葬許可証の提出など、必要な行政手続きを行っていること
補助金制度は全国一律ではなく、導入している自治体は限られています。まずはお住まいの市区町村の役所や、墓地がある自治体に問い合わせをしてみましょう。「墓じまい 補助金 + 地域名」で検索するのも有効です。
メモリアルローン(墓じまい専用ローン)を活用する
一括で費用を支払うのが難しい場合には、分割払いが可能な「メモリアルローン」の利用も選択肢となります。これは、墓じまいや永代供養・改葬などの供養関連費用に使える専用ローンで、銀行や信販会社が取り扱っています。
一般的な特徴としては、
- 金利が比較的低めに設定されている
- 無担保で利用できることが多い
- 墓じまい業者が提携している金融機関を通じて申し込める
利用するには審査が必要ですが、年金受給者や専業主婦でも申込み可能な場合があります。無理のない月額返済プランで供養を進めたい方には、現実的な手段といえるでしょう。
費用を抑えた供養方法を選ぶ
墓じまい後の供養先によっては、全体の費用を大きく削減できることもあります。とくに予算を重視したい方は、以下のような選択肢も検討してみてください。
- 合祀墓(ごうしぼ):他のご遺骨と一緒に納骨する形式で、個別の墓石は設けられません。費用は3万円〜10万円前後と安価です。
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とする自然志向の供養方法。初期費用が20万円前後からと比較的リーズナブルです。
- 永代供養墓:寺院や霊園が永続的に供養を行ってくれるお墓で、維持費がかからず安心です。合祀型や個別型があり、費用の幅は広めですが、全体的に従来型のお墓より費用を抑えられます。
供養方法の変更は一度決めると後戻りが難しいため、ご家族と相談しながら進めることが大切です。費用面とご先祖様への想いのバランスを大切にしたうえで、最適な方法を選びましょう。
無理をせず、まずは相談することが大切
費用の問題で墓じまいを先送りにしてしまうと、結果的にお墓が無縁化し、さらに大きな負担が家族に残ってしまうこともあります。無理のない方法を選ぶためにも、まずは墓じまいの専門家や石材店に相談してみることをおすすめします。無料で見積もりやアドバイスを受けられるサービスも多く用意されています。

「費用が払えない=墓じまいできない」ではありません。制度や工夫を上手に活用すれば、経済的な負担を減らしつつ、心のこもった供養を実現できます。
墓じまい費用をめぐるトラブルと予防策
墓じまいは、ご先祖様への想いを形にする大切な行為ですが、費用の負担や進め方をめぐって家族間でトラブルが生じることもあります。特に、誰がどれだけ費用を負担するのかという問題は、金銭の話に直結するだけに感情が絡みやすく、親しい間柄であっても関係がぎくしゃくしてしまう原因になりかねません。ここでは、よくあるトラブルの実例と、その予防策について解説します。
相談不足による不信感の悪化
もっとも多いのが、墓じまいを進める際に他の家族へ事前に相談せず、後になって「もう業者に依頼した」「費用を払ってほしい」といった形で話を持ちかけるケースです。とくに、離れて暮らしている兄弟姉妹にとっては「勝手に決められた」「既成事実を押しつけられた」と受け取られがちです。
このような行き違いを防ぐには、できるだけ早い段階で「相談ベース」で話を始めることが重要です。「まだ決まっていないんだけど」と前置きするだけでも、相手に心の余裕が生まれ、話を聞く姿勢を持ってもらいやすくなります。
「不公平感」を抱かせる分担方法
費用の負担割合について、相談が不十分なまま決定してしまうと、「なぜ自分ばかり多く払うのか」といった不満が生まれやすくなります。たとえば、長男だから・近くに住んでいるからという理由だけで一方的に多く負担を求められると、不満を抱えてしまうこともあります。
そこで大切なのは、「納得感のある分担」を作ることです。以下の3つのステップが有効です。
- 過去の関わり方を共有する
誰がどれだけお墓の管理や供養を行ってきたかを、客観的に振り返ります。 - 現在の経済状況や生活事情を理解し合う
今の生活にどれくらい余裕があるのかを互いに尊重しながら確認します。 - それぞれの気持ちや希望を話す
お墓への想いや、今後どのように供養していきたいのかを共有し、金額だけにとらわれない話し合いを行います。
このような対話を通して、「金額的な公平さ」ではなく「気持ちの納得」が得られやすくなります。
口約束だけで進めてしまう危険性
口頭だけの合意に頼ると、後から「そんなこと言っていない」「聞いていなかった」といったトラブルにつながるリスクがあります。とくにお金が絡む話では、記録が残っていないことが後々の誤解を招きやすいのです。
そのため、話し合った内容は必ずメモやLINEなどの記録として残すことをおすすめします。正式な契約書でなくても、「○月○日にこういう話をした」「費用は○円ずつ出すことにした」など、簡単なやり取りで十分です。できれば、家族グループのチャットなど、他の家族も確認できる場所での共有が望ましいです。
進め方が不透明なことによる不安
墓じまいの流れや手続きに関して情報を持っている人が偏っていると、他の家族が「自分は蚊帳の外」と感じたり、「何をどこまで進めたのか分からない」という不安を抱くことがあります。
これを防ぐには、進行状況や費用の見積もりを定期的に共有する仕組みを整えておくと安心です。たとえば、「見積もりが出たので共有します」「今週末、業者と打ち合わせします」など、段階ごとに報告するだけで、家族の安心感と信頼関係が高まります。
トラブルを避けるためのまとめ
- 墓じまいの話は「相談ベース」で早めに始める
- 分担方法は「気持ちの納得感」を重視して話し合う
- 話し合った内容は記録を残しておく
- 進行状況はこまめに共有する

墓じまいは、単なる手続きや費用の問題ではなく、「家族の絆」を再確認する時間でもあります。少しの気配りや工夫で、大きなトラブルを未然に防ぐことができ、結果としてご先祖様への温かい供養にもつながります。
まとめ|誰が払うかより「家族で話し合うこと」が大切
墓じまいを進めるうえで、多くの方がまず悩むのが「誰が費用を払うのか」という点です。実際、法律や制度に明確なルールはなく、お墓の承継者が負担するケースもあれば、兄弟姉妹や親族で分担することもあります。ですが本当に大切なのは、「誰が何円出すか」ではなく、「どうやって家族で納得し合える形をつくるか」という視点です。
費用の問題は、家族の事情やそれぞれの立場によって答えが異なります。たとえば、遠方に住んでいるから手続きには関われないが、少しでも費用を出したいという気持ちを持っている方もいれば、経済的に余裕がなく負担できなくても、気持ちのうえで協力したいと考える方もいます。そうした気持ちのすれ違いを防ぐためにも、家族で率直に話し合う場を設けることが重要です。
また、墓じまいは単なる「支出の問題」ではなく、ご先祖様の供養のあり方を家族で考え直す機会でもあります。今後の供養をどうするのか、誰がどのように関わっていくのかを丁寧に話し合うことで、単なる作業ではなく「家族の意思」がこもった供養にすることができます。
金額だけでなく、誰がどれだけの手間をかけるのか、どのような思いで墓じまいを進めたいのか。こうした「気持ちの共有」が、結果的に家族の理解や協力を得るための最大の鍵となります。
もし、どうしても話し合いがうまく進まない場合は、墓じまい専門の相談窓口を活用するのも一つの方法です。第三者の専門家に入ってもらうことで、冷静に話を進めるきっかけになります。

墓じまいを成功させるポイントは、「誰が払うか」ではなく「どうやって家族で納得して進めるか」。その本質を見失わず、無理なく、そして気持ちのこもった供養を目指しましょう。