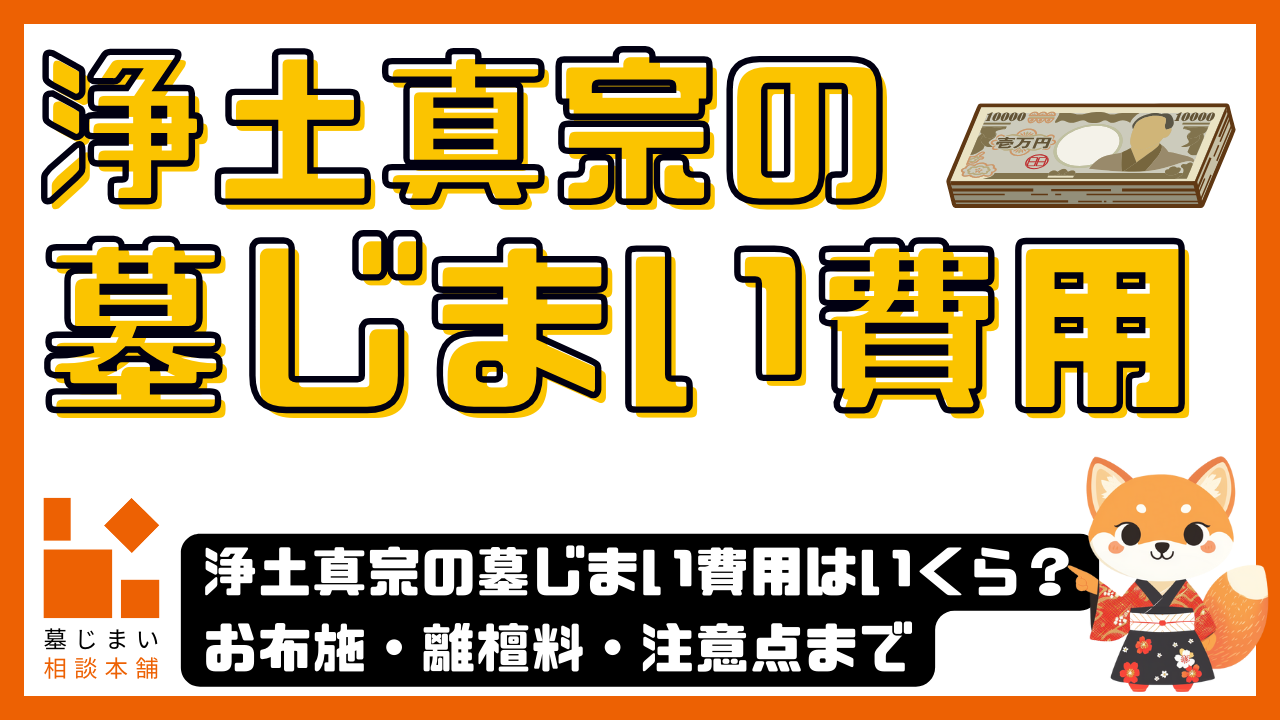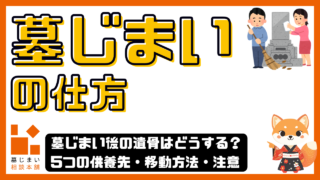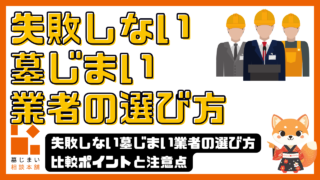本ページはプロモーションが含まれています。
目次
浄土真宗の墓じまいとは?他宗派との違い
浄土真宗の墓じまいは、他の宗派と比べて大きな思想的違いがあるため、儀式や費用の内訳にも独自の特徴があります。まず知っておくべきなのは、「墓じまい=供養」という考え方が、浄土真宗では必ずしも当てはまらないという点です。
他宗派では「故人の魂はお墓に宿っている」とされ、墓じまいの際に魂を抜く儀式(閉眼供養)が重要視されます。しかし、浄土真宗では阿弥陀如来の力によって、亡くなった瞬間にすべての人が極楽浄土へ往生できると考えられているため、魂が墓に留まっているという前提がありません。これが、浄土真宗で閉眼供養を行わない最大の理由です。
その代わりに行われるのが「遷仏法要(せんぶつほうよう)」です。これは、故人の魂を送る儀式ではなく、お墓に安置されていたご本尊(阿弥陀如来)を別の場所へ移すための仏教的儀式です。外見上は閉眼供養と同じように僧侶による読経や儀式が行われますが、意味合いは大きく異なります。
また、墓じまい後に新たなお墓を建てた場合、他宗派であれば開眼供養(魂を新たな墓に迎え入れる儀式)を行いますが、浄土真宗ではこれも必要ありません。その代わりに、「建碑法要(けんぴほうよう)」という形式で、お墓の建立を仏前に報告し、仏縁を結ぶ儀式を行います。
このように、浄土真宗の墓じまいは「供養」ではなく「信仰の表現」に重点を置いている点が他宗派と異なります。そのため、宗派の教義に則った儀式を選びつつ、故人への想いを大切にすることが求められます。
さらに、墓石のデザインや刻まれる言葉にも宗派特有の特徴があります。多くの宗派で用いられる「〇〇家之墓」といった表現は避けられ、「南無阿弥陀仏」や「倶会一処(くえいっしょ)」といった浄土真宗独自の言葉が刻まれます。これは、故人や先祖との再会を極楽浄土で願うという教えに基づいたものです。
卒塔婆(そとば)や五輪塔のような、供養のための塔や木片も使用されません。これも、「追善供養」を必要としない教えによるものです。

以上のように、浄土真宗の墓じまいは、仏教の儀式としての側面よりも、阿弥陀如来への信仰や家族の理解、そして故人への想いを重視した宗教的判断が色濃く反映されています。したがって、一般的な墓じまいの手順や費用とは異なる考慮点が必要です。浄土真宗に沿った方法を選ぶことで、無理のない円満な墓じまいが可能になります。
浄土真宗の墓じまいにかかる費用相場
浄土真宗の墓じまいにかかる費用は、一般的に総額で35万円〜150万円が目安とされています。これは他の宗派と大きく異なる金額ではありませんが、儀式や納骨方法の違いによって、内訳には浄土真宗特有の特徴があります。
総額の目安:35万円〜150万円
墓じまいにかかる費用の総額は、主に次の要素から構成されます。
- 墓石の撤去費用:30〜50万円
- 行政手続き費用:数百円〜1,000円程度
- 遷仏法要のお布施:3〜10万円
- 離檀料:3〜20万円
- 新たな納骨先にかかる費用:30〜100万円
立地条件や墓地の広さ、納骨先の種類によって費用は変動するため、複数の業者や寺院から見積もりを取ることが重要です。
他宗派との金額の違いはあるのか?
費用面での違いはほとんどありません。ただし、儀式の内容には明確な違いがあります。他宗派では閉眼供養や開眼供養が必要ですが、浄土真宗ではそれに代わる「遷仏法要」や「建碑法要」を行います。これらの法要も僧侶による読経やお布施が発生するため、実質的な費用負担に大きな差はありません。
一方で、卒塔婆の費用や五輪塔の設置がないため、墓石周りの構成や管理費用に関しては抑えられるケースがあります。加えて、仏教的な意味合いよりも「信仰の表明」としての法要が中心となるため、納骨先に強い宗教的制限がない民間霊園を選択するケースも多くなっています。
また、浄土真宗では「供養するための儀式」よりも「仏縁を結ぶための法要」として捉えられるため、檀家制度を離れることに理解のある寺院も比較的多く、離檀料をめぐるトラブルも少ない傾向にあります。

実際の費用を正確に把握するには、次のステップで具体的な内訳を確認しながら準備することが大切です。事前に地域の石材店や寺院、納骨先に直接相談することで、予想外の出費を避けることができます。
浄土真宗の墓じまい|費用の内訳を解説
浄土真宗で墓じまいを行う際にかかる費用は、「何に」「いくらかかるのか」が分かりにくく、初めての方にとっては不安が大きいポイントです。この章では、宗派特有の考え方をふまえながら、費用の内訳をわかりやすくご紹介します。
墓石の撤去費用(30〜50万円)
墓じまいの中で最も大きな出費がこの「墓石の撤去費用」です。石材店に依頼して墓石を解体し、墓所を整地して更地に戻す作業が含まれます。費用はお墓の広さや立地によって異なり、たとえば重機の入らない山間部や狭い墓所では高くなりやすい傾向にあります。
さらに、撤去時には遺骨の取り出し作業も必要です。土葬されていた場合は、改めて火葬しなければならないこともあり、これに別途費用がかかるケースもあります。
行政手続きの費用(数百円〜1,000円)
墓じまいを進めるには「改葬許可証」の取得が必要です。この許可証を得るために、以下の書類を用意します。
- 埋蔵証明書(300〜1,500円):今あるお墓の管理者に依頼
- 受入証明書(無料):新たな納骨先から発行
- 改葬許可申請書(無料〜1,000円):市区町村役場に提出
自治体ごとに金額は異なりますが、総額で1,000円以内に収まることがほとんどです。
遷仏法要のお布施(3〜10万円)
浄土真宗では、他宗派で行われる「閉眼供養」の代わりに「遷仏法要(せんぶつほうよう)」を行います。これは墓石に安置していたご本尊を移す儀式で、僧侶に読経を依頼するためお布施が必要です。
お布施の相場は3万円〜10万円程度ですが、地域の慣習やお寺との関係によって異なります。金額に決まりはないため、不安な場合は直接お寺に相談すると安心です。
離檀料の目安(3〜20万円)
墓じまいと同時にお寺との檀家関係を終了する場合、「離檀料」をお渡しするのが通例です。これは、お寺とのこれまでの関係に対する感謝の気持ちを形にするもので、法的な義務ではありません。
費用は3万円〜20万円が一般的ですが、こちらも地域や寺院の方針によって変動します。「離檀料の請求がなかった」というケースもあれば、「具体的な金額を提示された」ということもあります。納得できる形で話し合いを進めましょう。
新しい納骨先の費用(30〜100万円)
遺骨の新たな受け入れ先を用意する必要があります。納骨方法によって費用は大きく変動します。
- 永代供養墓:5〜80万円
- 樹木葬:10〜100万円
- 納骨堂:20〜150万円
- 一般墓(新規建立):100万円以上
浄土真宗では永代供養という考え方が本来ありませんが、永代経供養を行う寺院や宗派不問の民営霊園を選ぶことで、多くの方が問題なく納骨を行っています。
また、新しいお墓を建てる場合は「建碑法要(けんぴほうよう)」を行うのが一般的です。こちらも僧侶へのお布施が発生し、相場は3万〜5万円程度です。

以上が、浄土真宗の墓じまいにかかる費用の主な内訳です。全体の費用は、これらの項目を合計しておおよそ35万円〜150万円程度になることが多いです。希望に合った納骨先の選定と、信頼できる業者選びが費用を抑えるカギとなります。
浄土真宗の墓じまい後に選べる納骨方法と費用
墓じまいを終えた後、取り出したご遺骨をどこに納めるかは大きな選択です。特に浄土真宗では、永代供養の考え方が他宗派と異なるため、納骨先の選定には宗派の教えを理解したうえで判断することが大切です。ここでは、浄土真宗の教義に配慮しながら選べる納骨方法と、それぞれにかかる費用の目安をご紹介します。
宗旨不問の永代供養墓
永代供養墓は「お墓の後継ぎがいない」「子どもに負担をかけたくない」といった理由から近年選ばれている納骨方法です。浄土真宗には本来「永代供養」という概念はありませんが、宗旨宗派不問の民営霊園を利用することで、問題なく納骨できます。
- 費用相場:5万円〜80万円
- 特徴:管理費不要/宗教行事なしでも利用可/合祀タイプは費用が安い
- 注意点:合祀後はご遺骨の取り出しができない場合があるため、事前確認が必要です
樹木葬
自然に還るという考え方に共感する方に人気なのが樹木葬です。墓石の代わりに樹木を墓標とし、故人が自然と一体になるイメージで選ばれる方が増えています。
- 費用相場:10万円〜100万円
- 特徴:宗教色が薄く、自由度が高い/個別区画のある樹木葬は管理も安心
- 注意点:使用期限が設けられている場合があるため、永続性を確認しましょう
納骨堂
屋内で管理される納骨施設で、都市部を中心に増えている選択肢です。気候に左右されずお参りができ、設備や防犯面でも安心感があります。
- 費用相場:20万円〜150万円
- 特徴:ロッカー式・仏壇式・自動搬送式など形式が豊富/参拝がしやすい立地が多い
- 注意点:年間管理費が発生する施設もあるため、契約内容をよく確認しましょう
浄土真宗の本山・寺院への納骨
浄土真宗では、親鸞聖人が眠る本山への納骨という選択もあります。本願寺派は「大谷本廟」、真宗大谷派は「大谷祖廟」で納骨を受け付けています。
- 費用相場:1万円〜数万円(分骨・納骨の方法により異なる)
- 特徴:教義に則った供養が受けられる/宗派に強くこだわりがある方に適している
- 注意点:本山への納骨は「分骨」で行うケースが多く、遺骨の一部のみを納める形になります
個別安置型の永代供養墓(石碑タイプ)
従来のお墓に近いスタイルを維持しながら、管理は任せたいという方には、個別区画のある永代供養墓も選ばれています。一定期間は個別で安置し、その後合祀されるケースが多いです。
- 費用相場:50万円〜120万円
- 特徴:個人や家族単位で区画があるため、従来のお墓の雰囲気を重視する方におすすめ
- 注意点:期間終了後に合祀される流れや、追加費用の有無を契約時に確認する必要があります

どの納骨方法を選ぶかは、費用だけでなく「将来的な供養のあり方」や「家族の希望」「信仰心」も含めて総合的に考えることが大切です。浄土真宗の教えに配慮した選択をすることで、家族全員が納得できる墓じまいと、その後の供養につながります。納骨先の資料を複数取り寄せたり、現地見学を通じて比較検討することも後悔しない判断につながります。
浄土真宗の墓じまいの流れと注意点
浄土真宗の墓じまいを行う際は、宗派特有の作法をふまえたうえで、トラブルのないよう段取りよく進めることが大切です。ここでは、実際の流れに沿って具体的な注意点も交えながら解説します。
1. 家族や親族と話し合う
墓じまいの第一歩は、家族や親族とよく話し合うことです。お墓は個人の所有物というより「家全体の象徴」として扱われることが多いため、自分の判断だけで進めてしまうと、親族との対立や感情的なトラブルを招くことがあります。
特に浄土真宗では先祖への感謝や信仰が重視されているため、伝え方も重要です。感情に配慮しながら、「管理が難しい」「将来的に継ぐ人がいない」といった理由を丁寧に説明し、理解を得てから手続きを進めましょう。
2. 墓地の管理者・菩提寺に相談する
家族の合意が得られたら、次は現在のお墓を管理しているお寺や霊園に墓じまいの意思を伝えます。菩提寺の場合、これまでお世話になった感謝の気持ちを伝えるとともに、墓じまいの理由や今後の方針を丁寧に説明することが大切です。
浄土真宗では、檀家を離れる場合に「離檀料」を求められることがありますが、金額の決まりはなく、あくまで「お礼」として渡すものです。交渉に不安がある場合は、石材店や終活相談窓口など第三者に相談してもよいでしょう。
3. 納骨先を決める
墓じまい後に遺骨を納める先としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などがあります。浄土真宗では永代供養の概念は本来存在しませんが、近年では「永代経供養」という形で、宗派に沿った納骨を受け入れる寺院も増えています。
特に「本山納骨」も人気があり、本願寺派は大谷本廟、真宗大谷派は大谷祖廟が受け入れ先となります。分骨して納めることも認められているため、信仰を大切にしたい方には有力な選択肢です。
4. 石材店を選んで撤去を依頼する
墓石の撤去は、専用の重機を扱う専門の石材店に依頼します。撤去費用は墓所の広さや立地条件で変動します。複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく実績や評判も比較すると安心です。
一部の寺院や霊園では、指定業者でしか作業できないケースもあるため、事前確認は必須です。
5. 改葬許可申請を行う
お墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すには、役所から「改葬許可証」を取得する必要があります。申請に必要な書類は以下の3つです。
- 埋蔵証明書(現在のお墓の管理者が発行)
- 受入証明書(新しい納骨先の管理者が発行)
- 改葬許可申請書(市区町村役場で取得)
改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要なので、複数の遺骨がある場合はそれぞれの手続きを行います。
6. 遷仏法要を行う
浄土真宗では、閉眼供養の代わりに「遷仏法要(せんぶつほうよう)」または「遷座法要(せんざほうよう)」を行います。これは仏像や位牌を別の場所に移すための儀式であり、魂を抜く目的ではありません。
遷仏法要では僧侶に読経を依頼し、終了後にお布施を渡します。お布施の相場は3万〜10万円程度ですが、地域やお寺によって異なるため、事前に相談しておくと安心です。
7. 墓石の撤去・更地化
遷仏法要が終わったら、石材店が墓石を撤去し、墓所を整地して更地に戻します。整地後の墓地は、お寺や霊園に返還することで契約が終了します。
もし墓所に土葬された遺骨がある場合は、改めて火葬を行う必要があるため、事前に確認しておきましょう。
8. 新しい納骨先に遺骨を納める
最終ステップは、改葬許可証とともに遺骨を新しい納骨先に納めることです。浄土真宗では、開眼供養は行わず、「建碑法要(けんぴほうよう)」という儀式を通じて新しいお墓の建立を仏前に報告します。
納骨の際には、施設や寺院ごとに必要な手続きが異なる場合があります。事前に確認し、丁寧に進めることで、故人やご先祖への敬意を保った形での供養が可能となります。

以上が、浄土真宗の墓じまいの一般的な流れとその際に注意しておきたいポイントです。宗派の教えを尊重しつつ、家族や親族との円満な話し合いを大切に進めることで、後悔のない墓じまいが実現できます。
よくある質問 浄土真宗で墓じまいを検討する方へ
魂抜き(閉眼供養)は本当に必要ないのですか?
はい、浄土真宗では「魂抜き」と呼ばれる閉眼供養を行いません。その理由は、浄土真宗の教義にあります。浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに阿弥陀如来のはたらきによって極楽浄土に往生するとされており、「魂が墓に宿る」という考え方自体がありません。そのため、墓石から魂を抜く必要がなく、供養という目的での閉眼法要は行わないのです。
代わりに行うのが「遷仏法要(せんぶつほうよう)」です。これは、墓所に安置していたご本尊(阿弥陀如来像)を別の場所へ移すための儀式で、浄土真宗における信仰的な意味を持ちます。僧侶による読経などの流れは他宗派の閉眼供養と似ていますが、内容と意義は全く異なります。
永代供養は本当にできないのですか?
浄土真宗には「永代供養」という言葉そのものは存在しません。なぜなら、故人は死後すぐに成仏するとされ、供養を通して成仏を願う必要がないからです。
ただし、実際には「永代供養墓」という形で納骨できる場は増えており、信仰の実践として「永代経供養(えいたいきょうくよう)」を行う寺院もあります。これは、故人のためというよりも、仏の教えを絶やさず伝えていくために読経を続けるという意味合いを持っています。
宗旨宗派不問の民間霊園や、永代供養墓を設置している浄土真宗の寺院を利用すれば、実質的には永代供養と同様の形式でご遺骨を預けることが可能です。
菩提寺が墓じまいに協力してくれない場合はどうしたらよいですか?
まずは丁寧に事情を説明し、理解を得る努力をしましょう。「子どもに負担をかけたくない」「お墓の管理が困難になった」など、具体的な理由を率直に伝えることが大切です。
それでも協力が得られない場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 地域の石材店や行政窓口に相談して、改葬に必要な書類をそろえる
- 檀家制度に依存しない民営霊園や宗派不問の納骨先を選ぶ
- 墓じまいの代行サービスを利用して、お寺との交渉をサポートしてもらう
また、離檀料について過大な請求を受けた場合は、地域の消費生活センターや宗教者の相談機関へ問い合わせるのも一つの方法です。
浄土真宗の墓じまいで気をつけるべきマナーはありますか?
宗派の教えに従いつつも、これまでお世話になった寺院への感謝を忘れないことが何よりも大切です。たとえば、以下のような配慮が求められます。
- 口頭ではなく文書で墓じまいの意向を丁寧に伝える
- 法要やお布施を省略せず、宗派の作法に沿った形で行う
- ご住職への挨拶や感謝の言葉をしっかり伝える
宗教的な儀式以上に、「心を込めて丁寧に対応する姿勢」が、円満な墓じまいには不可欠です。
お布施や離檀料の金額に決まりはありますか?
お布施や離檀料に明確な決まりはありませんが、一般的な相場は以下の通りです。
- 遷仏法要のお布施:3万円〜10万円
- 建碑法要のお布施:3万円〜5万円
- 離檀料:3万円〜20万円
ただし、これらはあくまで目安です。地域性や寺院ごとの考え方にも違いがあるため、不安な場合は直接ご住職に尋ねるのが一番確実です。「この金額で失礼がないか」など、事前に確認することでトラブルを防ぐことができます。
お墓の魂はどこに行くのですか?
浄土真宗では「魂はこの世にとどまらず、亡くなったその瞬間に阿弥陀如来のはたらきで極楽浄土へ往生する」とされています。つまり、墓石や遺骨に魂が宿っているという考え方はなく、「供養して成仏させる」といった意識は必要ありません。
このような教義を知っておくと、墓じまいに対する不安や罪悪感が少し軽くなるかもしれません。仏さまの教えに従いながら、今できる最善の形で故人を偲ぶことが、何よりの供養になるというのが、浄土真宗の基本的な考え方です。