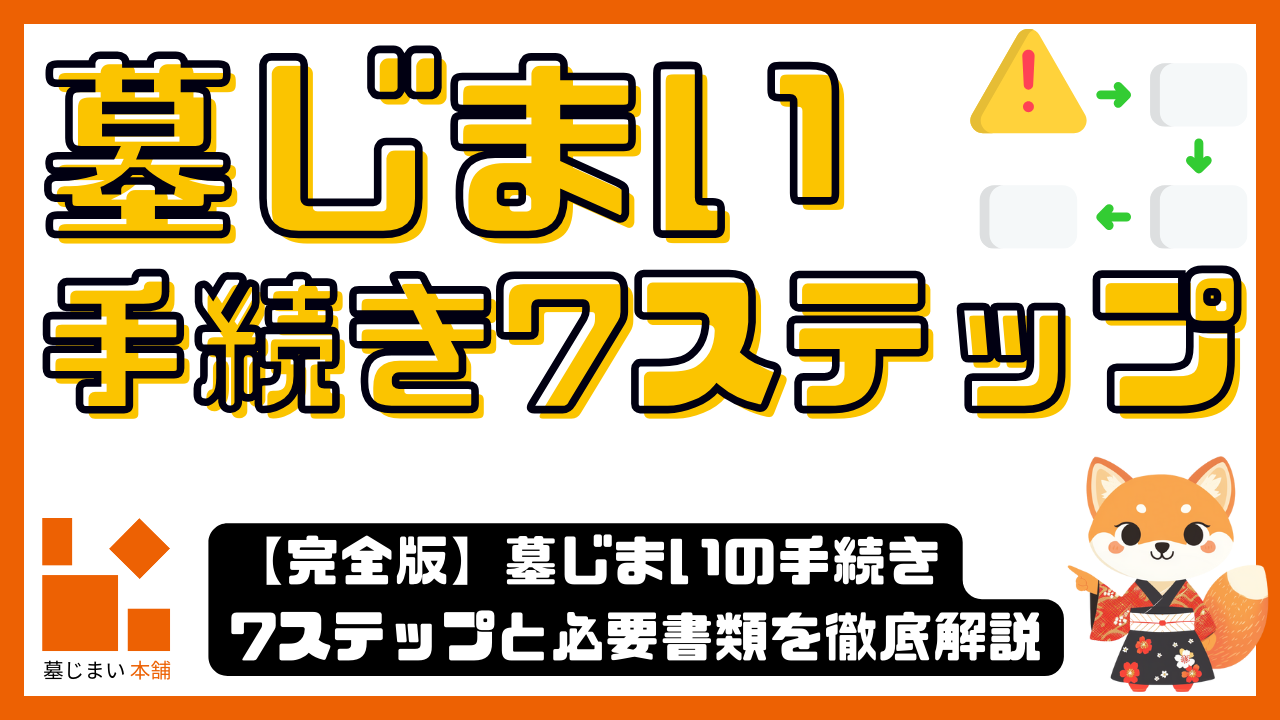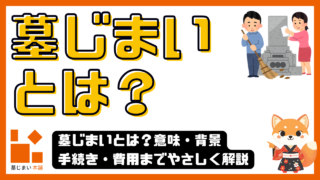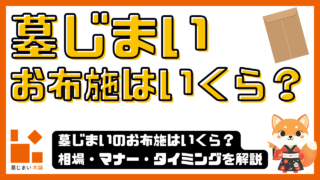本ページはプロモーションが含まれています。
目次
墓じまい手続きとは?
墓じまいの手続きとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を新たな供養先へ移すために必要な一連の届け出や準備のことを指します。
ただお墓を壊すだけでなく、「行政への申請」「新しい納骨先の確保」「宗教的な儀式」など、いくつかの重要な工程を順序よく進める必要があります。
まず最初に必要なのは、自治体への「改葬許可申請」です。これは、現在の墓地から遺骨を取り出して別の場所に移すための法的な手続きであり、無許可で遺骨を移動することは法律上認められていません。改葬許可申請を行うには、いくつかの書類を揃える必要があり、取得先も異なるため、事前の確認が重要です。
さらに、現在のお墓の管理者(寺院や霊園)から「埋葬証明書」をもらい、新しい納骨先からは「受入証明書」を取り寄せる必要があります。これらの書類を基に自治体で申請を行い、「改葬許可証」を発行してもらうことで、ようやく遺骨を取り出すことが可能になります。
遺骨を取り出す前には、宗教的な儀式である「閉眼供養(へいがんくよう)」を行うことが一般的です。これは、お墓に宿った魂を抜き、お墓としての役割を終えるための儀式で、主に寺院に所属している場合に必要になります。
また、墓石を撤去して更地に戻し、墓地を返還する工程もあります。これには石材店に依頼して、解体・整地作業を行ってもらいます。撤去工事には事前見積もりやスケジュール調整が必要となるため、手続きと並行して準備しておくとスムーズです。
このように墓じまいには、法的・宗教的・物理的な手続きが複数関わっており、それぞれの段階での準備が非常に重要です。特に、役所への書類提出やお墓の管理者との連携はミスが許されない部分ですので、書類の確認と早めの行動がポイントとなります。

親族間での意見調整や、各所への連絡、必要書類の取得など、やるべきことは多岐にわたりますが、手続きを正しく進めることで、トラブルなく墓じまいを完了させることができます。終活の一環として墓じまいを検討される方や、親の代わりに手続きを進めるお子様世代にとって、この流れを正確に理解しておくことは非常に大切です。
墓じまいの手続き7ステップ流れ
墓じまいの手続きは、いくつかの段階に分かれており、それぞれの工程をしっかり確認しながら進めることが大切です。以下の7ステップに沿って行動すれば、無理なく、法律的にも宗教的にも適切な形で墓じまいを完了できます。
1. 親族の同意を得る
墓じまいをするうえで、まず最初にやるべきことは、親族の同意を得ることです。お墓は家族全体のものであるため、たとえ費用を自分で負担するとしても、他の家族に無断で進めるとトラブルの原因になります。特に兄弟姉妹、故人の孫世代なども含めて話し合い、理解を得ることが不可欠です。
また、墓じまいの理由(高齢化で管理が難しい、跡継ぎがいない、遠方で維持できないなど)をしっかりと説明しましょう。同意を得る際には、墓じまいにかかる費用や、遺骨をどこへ移すか、どのように供養するかといった点も共有しておくと安心です。
ポイント
- 墓じまいの最初の一歩は親族の同意
- 理由や背景を丁寧に説明して納得を得る
- 費用負担や供養方法も合わせて話し合う
2. 自治体で必要書類を確認する
墓じまいを行うには、自治体への申請が必要になります。しかし、必要な書類や提出方法、申請窓口などは市区町村によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。お墓のある地域の役所(多くは環境衛生課または住民課)に電話するか、ホームページを確認するとよいです。
申請書類の様式や添付資料の種類、記載方法、手続きにかかる日数などを確認しておくことで、無駄な手間や二度手間を防ぐことができます。また、一部の自治体では郵送手続きに対応している場合もあります。
ポイント
- 自治体によって必要書類が異なる
- お墓のある地域の役所で確認する
- 様式や提出方法、受付期間をチェック
3. 新しい納骨先を決めて「受入証明書」を取得する
墓じまいでは、遺骨の新しい納め先を決めておく必要があります。新たな納骨先としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓などがあります。いずれの場合も、契約時に「受入証明書」またはそれに相当する書類を発行してもらいます。これは改葬許可申請の際に必須です。
選定の際には、アクセスのしやすさ、費用、供養方法、宗教・宗派の対応などを比較検討しましょう。できれば実際に見学したり、管理体制や年間費用などを担当者に確認したりすることをおすすめします。
ポイント
- 永代供養や納骨堂など新たな供養先を決める
- 受入証明書は改葬申請に必須
- 見学や相談を通じて納得できる場所を選ぶ
4. 現在の墓地管理者から「埋葬証明書」をもらう
次に行うのが、現在の墓地を管理する寺院や霊園、公営施設などから「埋葬証明書」を発行してもらうことです。これは「この墓地に確かに遺骨が埋葬されている」という事実を証明する書類で、改葬許可の手続きに必要です。
管理者への連絡は早めに行いましょう。寺院墓地の場合は「離檀料(りだんりょう)」と呼ばれるお布施が求められることがあります。また、長年管理されていなかった墓などでは管理者が不明なケースもあり、その場合は自治体に相談すると対応してもらえることがあります。
ポイント
- 埋葬証明書は改葬許可申請に必要
- 管理者には早めに墓じまいの意向を伝える
- 離檀料が発生することもあるので注意
5. 改葬許可申請書を提出して「改葬許可証」を取得する
必要な書類(受入証明書・埋葬証明書)をそろえたら、改葬許可申請書を作成して提出します。提出先はお墓がある自治体で、申請者は遺骨の管理者(原則として名義人)となります。複数の遺骨がある場合は、原則として1体ごとに1通必要です。
改葬許可証の発行には数日から1週間程度かかることが多いですが、自治体によっては即日交付できる場合もあります。改葬許可証がなければ遺骨の移動ができないため、石材店や寺院とのスケジュール調整にも配慮して早めに申請しておきましょう。
ポイント
- 必要書類を添えて改葬許可申請書を提出
- 遺骨1体ごとに許可証が必要な場合もある
- 改葬許可証がないと遺骨は移せない
6. 閉眼供養(魂抜き)を行い、遺骨を取り出す
改葬許可証を取得したら、遺骨をお墓から取り出す前に「閉眼供養(へいがんくよう)」という宗教儀式を行います。これは、仏教においてお墓に宿った魂を抜く「魂抜き(たましいぬき)」の意味を持ちます。供養の際は僧侶に読経をお願いするのが一般的です。
日時の調整やお布施の準備も必要になります。閉眼供養が終わったあとに、遺骨を丁寧に取り出して、骨壺の清掃・再梱包を行います。状況に応じて、石材店が立ち会うこともあります。
ポイント
- 閉眼供養で魂を抜き、お墓の役目を終える
- 僧侶への依頼とお布施の準備が必要
- 遺骨の取り出しには丁寧な対応が必要
7. 墓石を解体・更地にして墓地を返還する
最後の工程は、墓石の解体と墓地の返還です。墓石は非常に重いため、専門の石材店に依頼して撤去工事を行います。費用は墓地の広さや立地、石材の大きさによって異なりますが、10万〜30万円程度が一般的です。
解体後は更地に整地し、墓地の管理者に返還手続きを行います。寺院墓地の場合は現地確認があることもあります。工事日程や業者の選定は早めに動き、できれば数社に見積もりを取り比較すると安心です。
ポイント
- 石材店に依頼して墓石を解体・更地に戻す
- 費用は条件により異なるため事前見積もりが重要
- 墓地はきれいな状態で返還する

このように、墓じまいは段取りと書類の確認がすべてといっても過言ではありません。それぞれの工程を丁寧に進めることで、気持ちの上でも区切りをつけることができ、故人への敬意を保ちつつ安心して新しい供養の形へ進むことができます。
平日10時~18時
各手続きに必要な書類と取得方法
墓じまいでは、手続きを円滑に進めるために複数の書類を揃える必要があります。書類の内容や取得先を正しく把握していないと、申請が遅れたりやり直しになったりする可能性があります。ここでは、実際に必要となる主要な書類とその取得方法について、具体的に解説します。
改葬許可申請書
遺骨を現在の墓地から別の場所へ移すために、自治体に提出する申請書です。申請者が直接記入する必要があります。
取得方法
- お墓のある自治体の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロード
- 郵送対応している自治体もあるため、遠方の場合は確認が必要
記入のポイント
- 遺骨1体につき1通が基本(複数記載可の様式も一部あり)
- 申請者本人が記入しなければならない(代筆不可)
備考
- 記入ミスや不備があると再提出が必要になるため、記入前に見本を確認するのがおすすめです
埋葬証明書(埋蔵証明書)
現在のお墓に遺骨が埋葬されていることを証明する書類です。改葬許可申請書と一緒に提出します。
取得方法
- 墓地の管理者(寺院・霊園管理事務所など)に依頼して発行してもらう
- 記載内容に管理者の署名・捺印が必要
注意点
- 管理者が不明な場合は、墓地のある自治体に相談する
- 墓地の種類(寺院墓地、公営霊園、民間霊園、共同墓地)により対応窓口が異なる
備考
- 書式は自治体指定の場合と、管理者が独自に作成する場合があるため確認が必要です
受入証明書
遺骨を移す先の施設が、確実に遺骨を受け入れることを証明する書類です。改葬の目的地が決まっていないと発行してもらえません。
取得方法
- 新しい納骨先(永代供養墓、納骨堂、樹木葬など)の管理者に依頼して発行
- 契約手続き後に受け取るのが一般的
書類に記載される内容
- 納骨先の名称・住所・管理者名
- 納骨予定者の情報
- 管理者の捺印または署名
備考
- 「受入証明書」ではなく「使用許可証」や「契約書の写し」が代用になる場合もある(自治体による)
墓地名義人の承諾書(必要な場合)
改葬申請者と墓地の名義人が異なる場合に、名義人からの承諾を証明するために必要な書類です。
取得方法
- 墓地の名義人から署名・捺印をもらう
- 様式は自治体で配布されていることが多く、ホームページでダウンロードできる場合もある
注意点
- 相続登記などで名義変更が済んでいない場合は、別途対応が必要になることもある
- 名義人が故人の場合は、戸籍謄本などによる相続関係の証明を求められる場合もある
本人確認書類
申請時に本人であることを証明するための書類です。窓口申請・郵送申請のどちらでも必要になります。
利用可能な書類
- 顔写真付き:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(1点)
- 顔写真なし:健康保険証、年金手帳、介護保険証など(2点)
提出方法
- 窓口の場合は提示
- 郵送の場合はコピーを同封
注意点
- 代理申請をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要になります
書類の提出先と提出方法
必要書類が揃ったら、墓地の所在地を管轄する市区町村の役所(多くは住民課や生活衛生課)に提出します。提出方法は、窓口持参または郵送が基本です。
提出前のチェックリスト
- 改葬許可申請書(記入済み)
- 埋葬証明書
- 受入証明書
- 承諾書(該当者のみ)
- 本人確認書類(原本または写し)
備考
- 提出後、審査を経て「改葬許可証」が発行されます(数日~1週間程度)
- 改葬許可証がないと、遺骨の取り出し・移動は法的にできません
書類の準備は墓じまいにおける最も重要な工程の一つです。書類の不備や記載ミスがあると、改葬許可が下りず予定が大きくずれる恐れもあります。早めに必要な書類を確認し、疑問点は自治体窓口や墓地・納骨先の管理者に事前に問い合わせておくと安心です。
改葬許可証の取り方と注意点
墓じまいにおいて「改葬許可証」は、遺骨を今の墓地から別の納骨先へ移すために絶対に必要な公的書類です。この許可証がなければ、遺骨の取り出しも移動も法律上できません。手続き自体は難しくありませんが、いくつかの注意点があるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
改葬許可証はどこで取得するのか
改葬許可証は、遺骨が埋葬されている墓地がある自治体(市区町村)の役所に申請して取得します。申請先は「住民課」や「生活衛生課」など、自治体によって異なるため、役所に事前に問い合わせて確認しましょう。申請方法は「窓口での手続き」か「郵送」で行うのが一般的です。
遠方にお墓がある場合、郵送での申請に対応している自治体もあります。役所のホームページを確認し、必要書類と提出方法を確認しておきましょう。
改葬許可申請に必要な書類
改葬許可証を取得するためには、以下の3つの書類が揃っている必要があります。
- 改葬許可申請書
自治体で配布されている専用様式で、ホームページからダウンロードできるケースもあります。申請者本人が記入します。 - 埋葬証明書
現在の墓地管理者(寺院・霊園など)から発行してもらいます。遺骨が実際に埋葬されていることを証明する書類です。 - 受入証明書
遺骨の新しい納骨先(永代供養墓、納骨堂、樹木葬など)から発行される「遺骨を受け入れることを証明する書類」です。納骨契約後に取得できます。
必要な書類は自治体によって多少異なる場合もありますので、事前に確認することが大切です。
改葬許可申請書は「本人記入」が原則
申請書の記入は原則として申請者本人が行う必要があります。これは、改葬に関わる意思確認の意味もあるため、代筆や業者による代理記入は認められないのが一般的です。ただし、申請そのものは委任状があれば代理人が提出することも可能です。
また、改葬する遺骨が複数ある場合は、基本的に1体につき1通の申請書が必要になります。一部の自治体では、1枚の申請書に複数の遺骨をまとめて記載できる様式もあるため、事前に確認するとスムーズです。
複数の遺骨がある場合の注意点
代々のお墓には、複数の遺骨が納められていることが珍しくありません。この場合、以下の点に注意が必要です。
- 遺骨の人数分の申請書が必要(または人数を明記)
- 申請書に記載する名前や関係性の確認
- 改葬先でも人数分の納骨スペースが必要
古いお墓で誰が埋葬されているか不明な場合もありますが、そのようなケースでは墓地管理者に確認するか、開墓時に把握することになります。曖昧なまま進めてしまうと、改葬先での納骨や供養に支障が出る可能性があるため注意が必要です。
改葬許可証が発行されるまでの時間
改葬許可証は、書類に不備がなければ即日または数日〜1週間程度で発行されるのが一般的です。役所の混雑状況や郵送対応の場合はさらに日数がかかることもあります。
改葬許可証は、以下の2つの場面で必ず必要になります。
- 遺骨を現在のお墓から取り出すとき
- 遺骨を新しい納骨先に納めるとき
いずれの場合も「改葬許可証がなければ作業ができない」ため、工事や納骨のスケジュールを考慮し、余裕をもって申請しましょう。
紛失や再発行に注意
改葬許可証は再発行できない自治体がほとんどです。万一紛失してしまうと、もう一度すべての申請手続きをやり直すことになる可能性もあります。発行されたら、コピーを取っておき、原本は大切に保管しましょう。
また、遺骨の移動中に提示を求められる場面もありますので、納骨が完了するまでは常に持ち歩くか、すぐ取り出せる状態にしておくと安心です。
改葬許可証の申請は、墓じまいの中でも最も重要なステップのひとつです。必要書類を正確に揃えること、記載内容にミスがないこと、そして発行までの日程を逆算して動くことが、スムーズな手続きのカギとなります。初めての手続きで不安な場合は、自治体の担当窓口に電話で相談すれば丁寧に教えてもらえます。
墓地管理者とのやりとりで必要なこと
墓じまいを円滑に進めるには、現在の墓地の管理者との連携が欠かせません。墓地の種類(寺院墓地・公営墓地・民間霊園・共同墓地)によって対応の仕方が異なるため、手続きの前に確認すべきポイントや注意点を把握しておきましょう。
埋葬証明書を取得する方法
墓じまいにあたり、まず管理者から「埋葬証明書(埋蔵証明書)」を発行してもらう必要があります。この証明書は、墓地に遺骨が実際に埋葬されていることを自治体に証明するためのものです。改葬許可申請には必須となるため、早めに依頼しておきましょう。
寺院墓地では住職、公営や民間霊園では管理事務所、共同墓地では町内会や区長などが窓口になります。発行には名義人の情報や墓所番号などが必要になることが多いため、事前に確認してから連絡するとスムーズです。
管理者が不明な場合の対処法
長年放置されていた墓や古くからの共同墓地では、誰が管理しているのかわからないケースがあります。このような場合は、墓地がある地域の市区町村役場に相談しましょう。多くの自治体では、地域の慣習や過去の届け出から管理者を把握している場合があります。
また、墓地の管理台帳が失われていたり、個人の土地にある無届墓地などでは、管理者不在とみなされ、特別な手続きが必要になることもあります。行政書士や石材業者が間に入って調査を進めるケースもあるため、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。
寺院墓地でのやりとりの注意点
寺院が管理している墓地の場合、住職とのやりとりには特に配慮が必要です。墓じまいは「離檀(りだん)」といって、菩提寺の檀家を辞めることにあたるため、宗教的・感情的な問題を含むことがあります。
このため、墓じまいの意向はできるだけ早めに丁寧に伝えることが重要です。挨拶を兼ねて直接伺うか、電話や書面で誠意をもって説明しましょう。
多くの場合、離檀料(いわばこれまでの供養への感謝と今後の関係を円満に終えるためのお布施)を求められることがあります。金額に明確な基準はありませんが、一般的には数万円〜20万円程度が相場とされており、事前に相談のうえで納得した金額を包むようにしましょう。
また、閉眼供養の日程や読経の内容についても住職と調整が必要です。寺院によっては「新しい納骨先が決まるまでは離檀できない」と伝えられることもあるため、柔軟かつ丁寧に対応する姿勢が求められます。
管理費の清算と墓所返還の確認
墓じまいを終える際には、墓地の使用契約の解除や、未納があれば管理費の精算を行う必要があります。これを怠ると、手続きが進まず、後日トラブルになることがあります。
また、墓石を撤去し更地に戻した後は、墓所をきれいに整地してから返還の手続きを行いましょう。寺院や霊園によっては、現地確認を行い、原状回復を確認したうえで書面で返還完了を通知するケースもあります。
墓地管理者とのやりとりは、墓じまい全体の進行に大きな影響を与えます。誠意をもって丁寧に対応し、必要な書類や費用、儀式の内容についてしっかり確認することで、不要なトラブルを避け、気持ちよく供養を終えることができます。特に寺院墓地の場合は宗教的背景をふまえた柔軟な姿勢が大切です。
墓じまい手続きの所要期間とタイミング
墓じまいにかかる手続きの期間は、平均して1〜3ヶ月程度とされています。ただし、準備の進め方や地域の事情、関係者との調整状況によっては、これより短くなる場合もあれば、半年以上かかることもあります。ここでは、主な工程ごとにかかる時間の目安と、適切なタイミングの考え方について解説します。
全体の所要期間の目安
墓じまいに必要な手続きの流れをすべて完了するまでにかかる期間の目安は以下の通りです。
| 手続き・工程 | 所要期間の目安 |
|---|---|
| 親族の同意 | 1〜2週間程度 |
| 書類準備(証明書の取得など) | 2〜4週間程度 |
| 改葬許可申請~許可証発行 | 1週間〜10日程度 |
| 閉眼供養・墓石撤去の準備 | 2〜3週間程度(業者調整含む) |
| 実際の撤去作業と納骨 | 1〜2日(事前予約必須) |
これらを並行して進める場合でも、最低1ヶ月前後の期間を見ておく必要があります。特に親族間の話し合いや寺院との調整に時間がかかるケースが多く、早めに取り掛かることが大切です。
手続きを始めるタイミングは「納骨時期」から逆算する
墓じまいのスケジュールを立てる際は、「新しい納骨先に遺骨を納める日」を起点に逆算して計画を立てるとスムーズです。
たとえば、永代供養や納骨堂で「〇月〇日に納骨予定」と決めている場合は、その日から逆算して1〜2ヶ月前には手続きを始める必要があります。改葬許可証が間に合わなければ納骨ができないため、書類の準備は余裕を持って行うのが基本です。
また、閉眼供養や墓石解体の予約も希望日にすぐ取れるとは限りません。特にお彼岸やお盆などの繁忙期は僧侶や石材店の予約が取りづらくなるため、これらの時期に合わせる場合はさらに早い段階で準備を始めましょう。
スケジュール調整で気をつけたい点
以下のような点に注意してスケジュールを組むと、無理のない進行が可能になります。
- 石材店・僧侶・親族の都合を先に確認しておく
各方面との予定調整には時間がかかります。特に寺院墓地の場合は住職の都合を最優先に配慮する必要があります。 - 役所が閉まっている期間を避ける
役所での書類申請や受け取りには平日の開庁時間中に行く必要があります。年末年始やゴールデンウィーク前後は混雑や長期休業もあるため注意が必要です。 - 天候リスクも考慮する
墓石撤去作業などの屋外作業は、天候によって延期になる可能性があります。梅雨や台風シーズンを避けると安心です。
早めに動くことで得られる安心
「まだ先のことだから…」と後回しにしていると、いざというときに書類が間に合わなかったり、希望する納骨先が予約できなかったりすることがあります。また、親族間での合意形成が難航し、予定がずれ込むケースも少なくありません。
とくに高齢の親の代わりにお子様が墓じまいを検討している場合は、時間をかけて段階的に進めることが大切です。1つ1つの工程を早めに着手することで、気持ちの余裕を持って故人と向き合い、丁寧な供養につなげることができます。

墓じまいの手続きは、単なる「作業」ではなく、故人やご先祖との別れに向き合う大切な過程でもあります。スケジュールに余裕をもたせ、納得できる形で進められるよう、早めの行動と準備を心がけましょう。
平日10時~18時
墓じまい手続きのよくある質問(Q&A)
Q1. 改葬許可証が不要な場合もあるのですか?
はい、あります。代表的なのは「遺骨が埋葬されていないお墓(生前に建てただけのもの)」を撤去する場合です。この場合は、遺骨の移動を伴わないため、改葬許可証は不要です。また、土葬だったお墓で遺骨がすでに土に還っていて形を留めていない場合も、自治体によっては申請不要とされることがあります。ただし、判断は各自治体により異なるため、事前に問い合わせて確認するのが確実です。
Q2. 申請書の記入は家族が代筆してもよいですか?
基本的に、改葬許可申請書は申請者本人が自筆で記入することが求められます。これは「本人の意思による申請であること」を明確にするためです。どうしても本人が書けない場合でも、代筆は原則認められず、申請そのものを代理人が行う場合は委任状と本人確認書類の写しが必要になります。書類を提出する前に、各自治体の担当窓口で詳細を確認しておきましょう。
Q3. 墓じまいの手続きは郵送でもできますか?
はい、自治体によっては改葬許可申請の手続きを郵送で受け付けている場合があります。特に遠方にお墓がある場合や、高齢などで役所まで出向くのが難しい方にとっては便利な方法です。ただし、郵送対応していない自治体もあるため、必ず事前に「必要書類・提出先・封筒の記載方法」などをホームページや電話で確認しておきましょう。
Q4. 土葬のお墓でも墓じまいできますか?
できますが、少し特殊な手続きになる可能性があります。土葬は火葬と異なり、遺骨が完全な形で残っていない場合もあるため、改葬許可証の必要性について自治体の判断が分かれます。一部でも骨が残っていれば申請が必要になりますし、全く遺骨がないと判断されれば申請が不要になることもあります。不明点がある場合は、自治体に相談しながら進めることをおすすめします。
Q5. 無縁墓や管理者がいない墓の手続きはどうすれば?
まずは墓地がある自治体に相談することが第一歩です。管理者が不明な墓地(特に古い共同墓地など)では、改葬許可に必要な「埋葬証明書」の取得が難しい場合があります。その際は、自治体が管理者代行の立場をとる場合や、法務局・行政書士・弁護士などを通じて特別な手続きを行うケースもあります。個人で判断せず、専門家や役所に相談しながら対応するのが安全です。
Q6. 遺骨が入っていない「空き墓」も手続きが必要ですか?
遺骨が一度も納められていない「空き墓」や、生前に建てただけの記念碑的なお墓の場合、改葬許可申請は不要です。しかし、墓石の解体工事をする際には、管理者との契約解除や返還手続きが必要になるため、勝手に撤去せず、事前に墓地の管理者に相談してから進めてください。
Q7. 墓じまいした遺骨は必ず納骨しなければなりませんか?
法律上、遺骨は「適切な方法で供養」する必要があります。納骨堂や永代供養墓、樹木葬などへの納骨が一般的ですが、自宅保管(自宅供養)や散骨という選択肢もあります。散骨の場合は自治体の条例に抵触しないよう、専門業者に依頼することが推奨されます。自宅供養は法律上問題ありませんが、将来的に手元から離れるときの対応も考慮しておくと安心です。
Q8. すでにお墓を放置している場合でも墓じまいできますか?
はい、可能です。ただし、長年放置していた場合は「無縁墓」として扱われ、すでに管理者側で合祀や撤去されていることもあります。その場合は、改葬ではなく供養のやり直しが必要になることもあります。現在のお墓の状況を確認し、自治体や墓地の管理者に現地調査を依頼することから始めてください。
Q9. 複数の遺骨がある場合は申請書も複数必要ですか?
基本的には遺骨1体につき1通の改葬許可申請書が必要です。ただし、一部の自治体では、1枚の様式に複数人分の情報を記載できる場合もあります。お墓を開けるまでは遺骨の正確な数が不明なこともあるため、あらかじめ墓地管理者に埋葬状況を確認し、必要書類の部数を余裕を持って用意しておくと安心です。

これらの質問は、多くの方が実際に墓じまいの手続きで戸惑いや不安を感じるポイントです。一つひとつ確認しながら進めることで、トラブルややり直しを防ぎ、スムーズに供養のステップを進めることができます。不明点があれば、遠慮せず自治体や専門業者に相談しましょう。
まとめ:正しい手続きで安心・確実な墓じまいを
墓じまいは、法的・宗教的・精神的な配慮が必要な大切な節目のひとつです。遺骨の取り扱いには法律が関わり、改葬許可証の取得をはじめとした手続きを正しく踏む必要があります。また、親族間での合意形成や寺院・墓地管理者との円滑なやりとりも不可欠です。
大切なのは、「焦らず、段階を踏んで進めること」です。たとえば書類は一つでも不備があると再申請が必要になり、予定していた日程が大幅にずれる恐れもあります。管理者への連絡や閉眼供養の調整なども含め、ひとつひとつ丁寧に確認しながら進めることで、後悔のない墓じまいが実現できます。
書類の取得、改葬許可の申請、新しい納骨先の選定、墓石の解体と返還といった複数の工程は、それぞれに異なる担当者や機関が関わるため、スムーズに進めるには全体の流れを把握した上で、早めに準備を始めることが重要です。特に納骨や閉眼供養の日程が決まっている場合は、そこから逆算して行動することで、トラブルや延期を防ぐことができます。
もし手続きややりとりに不安がある場合は、墓じまいの経験がある石材店や行政書士などの専門家に相談するのもひとつの手です。自分たちで進めるよりも確実で、精神的な負担を減らすことにもつながります。

お墓の整理は、これまで故人を大切に思ってきた家族の想いを未来へつなぐ行為でもあります。正しい知識と準備をもって進めることで、心から納得できるかたちで故人を見送り、これからの供養へとつなげていくことができるでしょう。
平日10時~18時